2015年の介護報酬の改定で生活行為向上リハ実施加算が新設された。介護予防とか日常生活総合支援事業においても都道府県単位でPTやOTの研修会が行われている。
だから「活動と参加」って言うと生活期とか維持期で実践するというようなイメージを持っているセラピストが多いんじゃあないだろうか。
もし活動と参加=生活期とあなたが考えているならそれは間違い。
厚労省もそんなこと言っていません。むしろ、急性期や回復期でも活動と参加を見据えたアプローチをすべきといってます。
以下の文書は厚労省のサイトより引用。
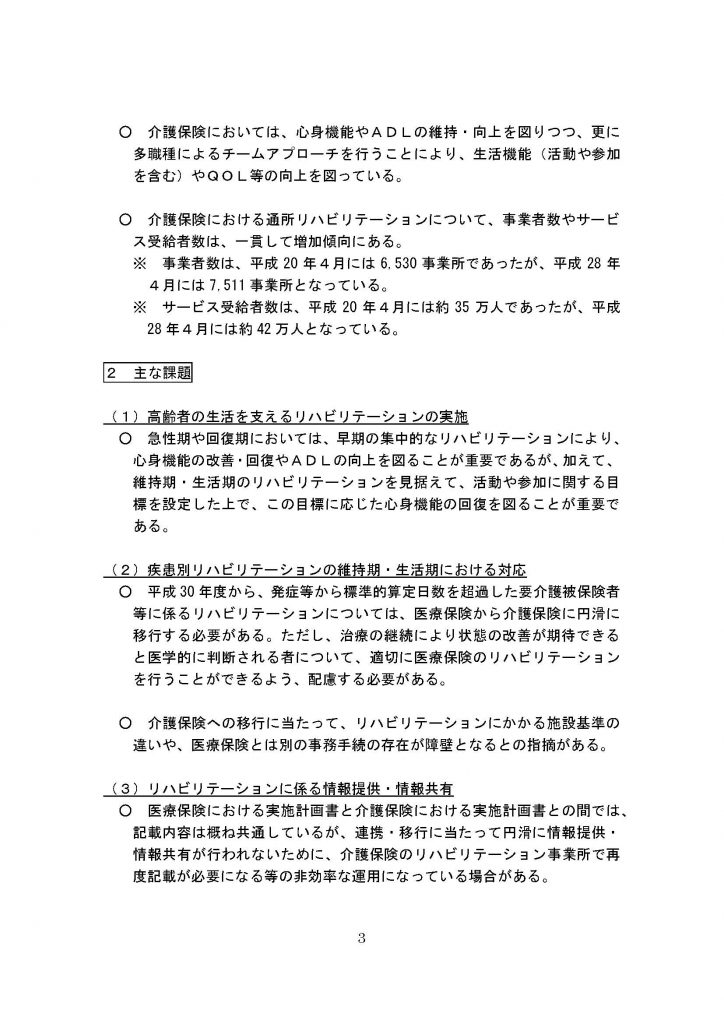
活動と参加の第一歩
活動と参加に回復期でアプローチするには、目標設定のプロセスがものすごく重要になってくる。
リハビリテーション実施計画書をだれが作っていますか?
セラピストがパソコン入力して、印刷したものを説明してハンコ押してもらって、あとはカルテの中にいれっぱなしになっていませんか?
その目標をきちんと本人や家族が理解していますか?
もっというなら、目標設定のプロセスに本人や家族は関与していますか?
その目標は利用者さんが望んでいる目標ですか?それともセラピストが望んでいる目標ですか?
リハビリテーション実施計画書をきちんと作成することが、活動と参加へのアプローチの第一歩なんです。
そんなことをノートサイトに書いてみました。
⇒【活動と参加へのアプローチ】 病院セラピストがやらなければ、誰がするの?
【スポンサー広告】
こんなお話をリアルに聞いてみたい方はこちらからどうぞ
⇒⇒講演依頼のこと
気に入ったらフォローしてください
YouTubeで動画公開しています。
やまだリハビリテーション研究所のYouTubeのチャンネル
新しい学びの形を提供します
フォロワーさんは200名くらいです!
⇒https://note.mu/yamada_ot/
Twitter
フォロワーさんは400名くらいです
⇒https://twitter.com/yamada_ot_labo
Facebookページ
フォロワーさんは2000名くらいです!
⇒https://www.facebook.com/yamada.reha.labo
やまだリハビリテーション研究所のLINE@を開設しました
![]()
ID検索の場合は
@yamada-ot.com
(@を含めて検索してね)
【↓↓週末にゆっくり読んでみてください↓↓】
生活期リハの視点で病院リハと地域リハをつなぐ・変えるマガジン
【スポンサー広告】
(スポンサー広告)

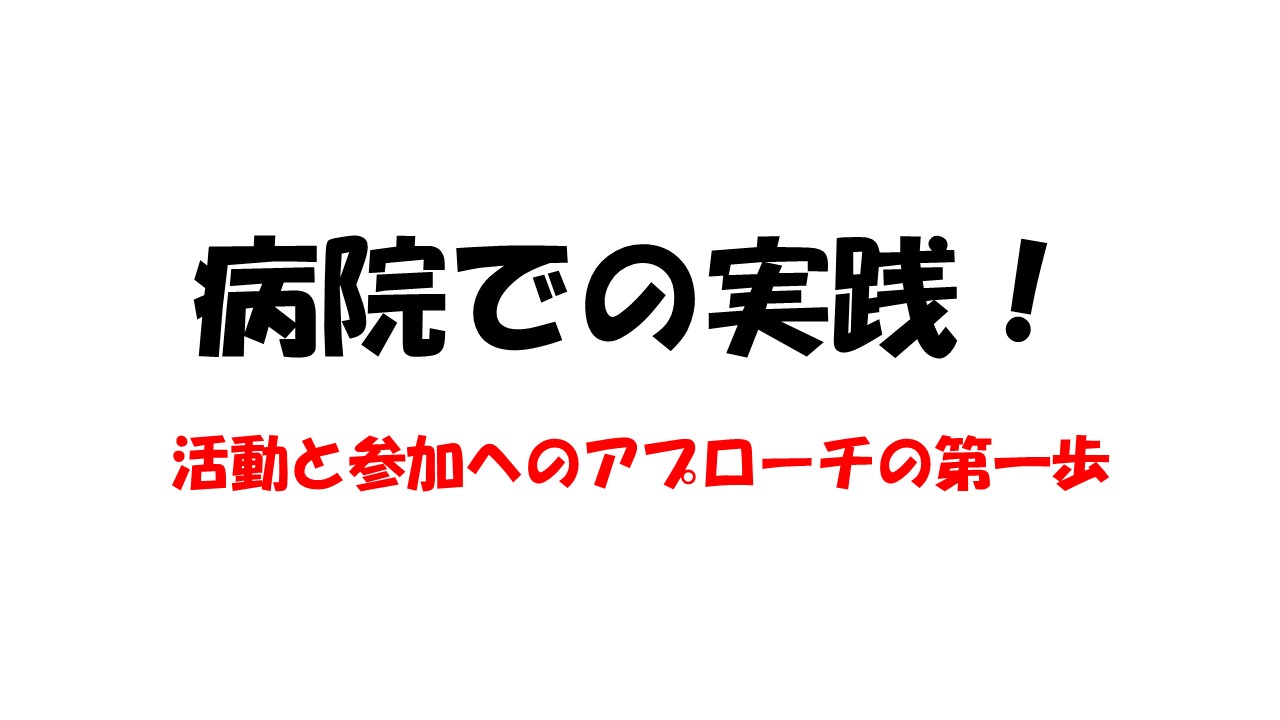

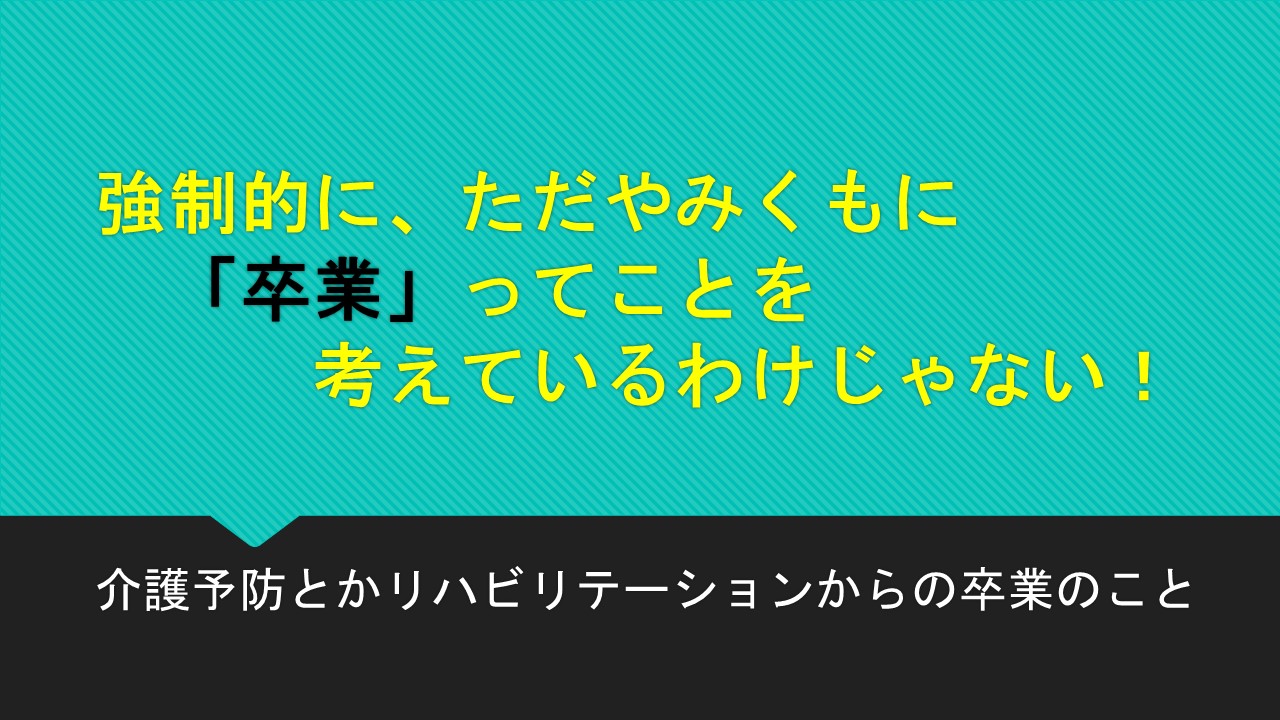
コメント