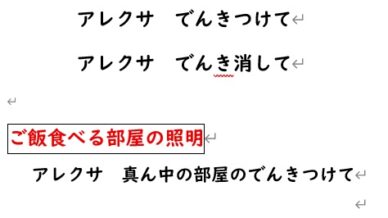 2025年
2025年 認知症の家族がリモコンをなくすのでスマートホーム化してみた
実家で姉と暮らしている母90歳は認知症。体はしっかり動くけど、記憶力は低下している。実生活で困っているのは、照明とかエアコンとかのリモコンをなくしてしまうこと。探せばどこかからは出てくるのですが、見つ...
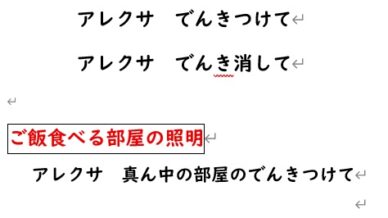 2025年
2025年 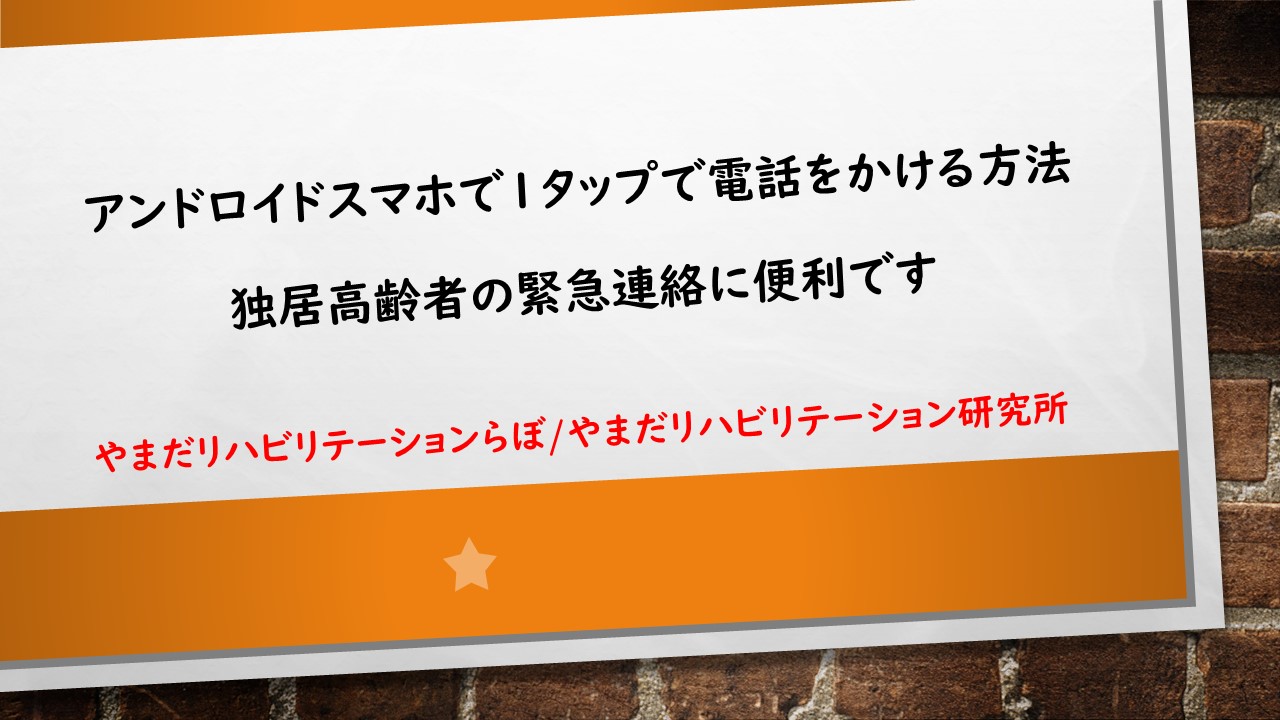 2023年
2023年 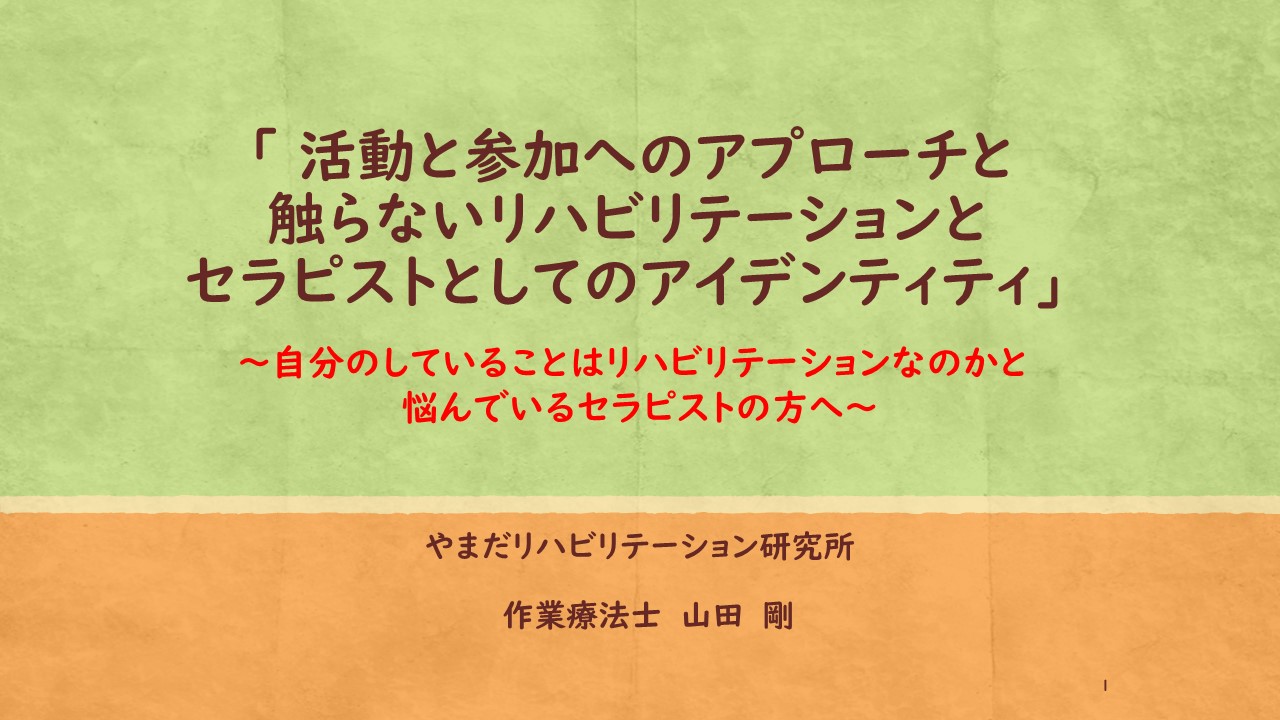 2023年
2023年 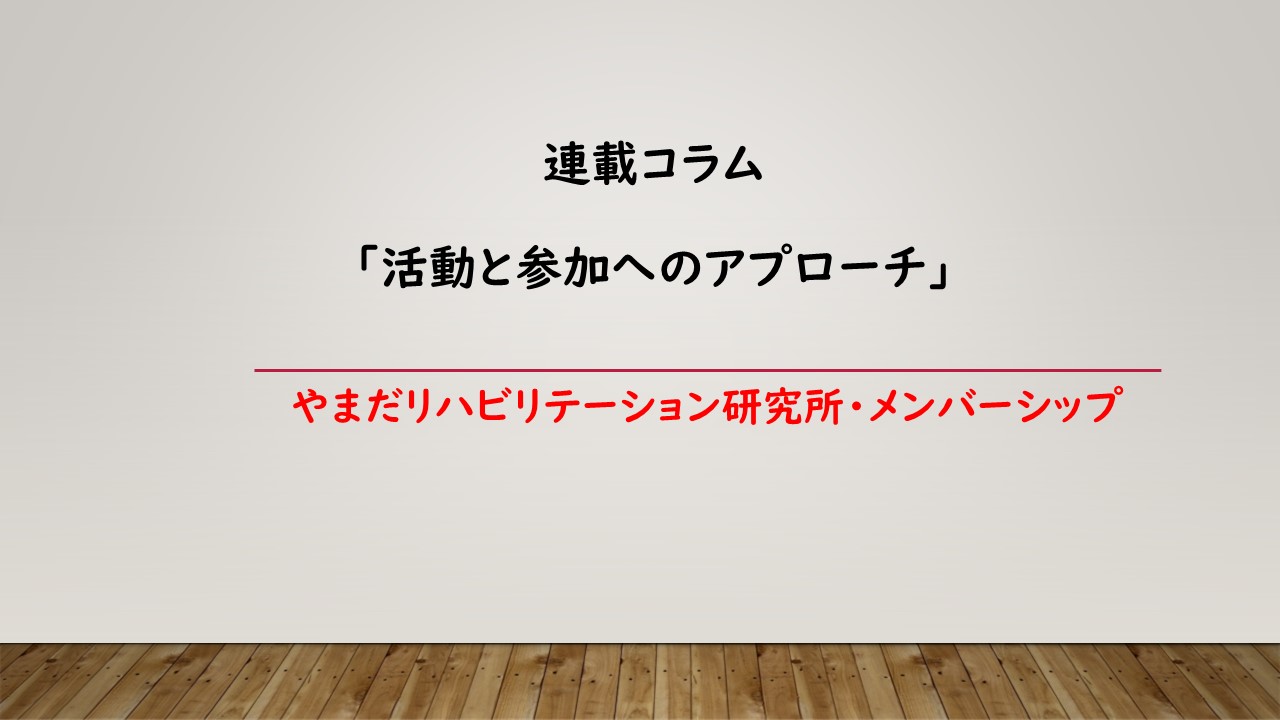 コラム
コラム  2022年
2022年 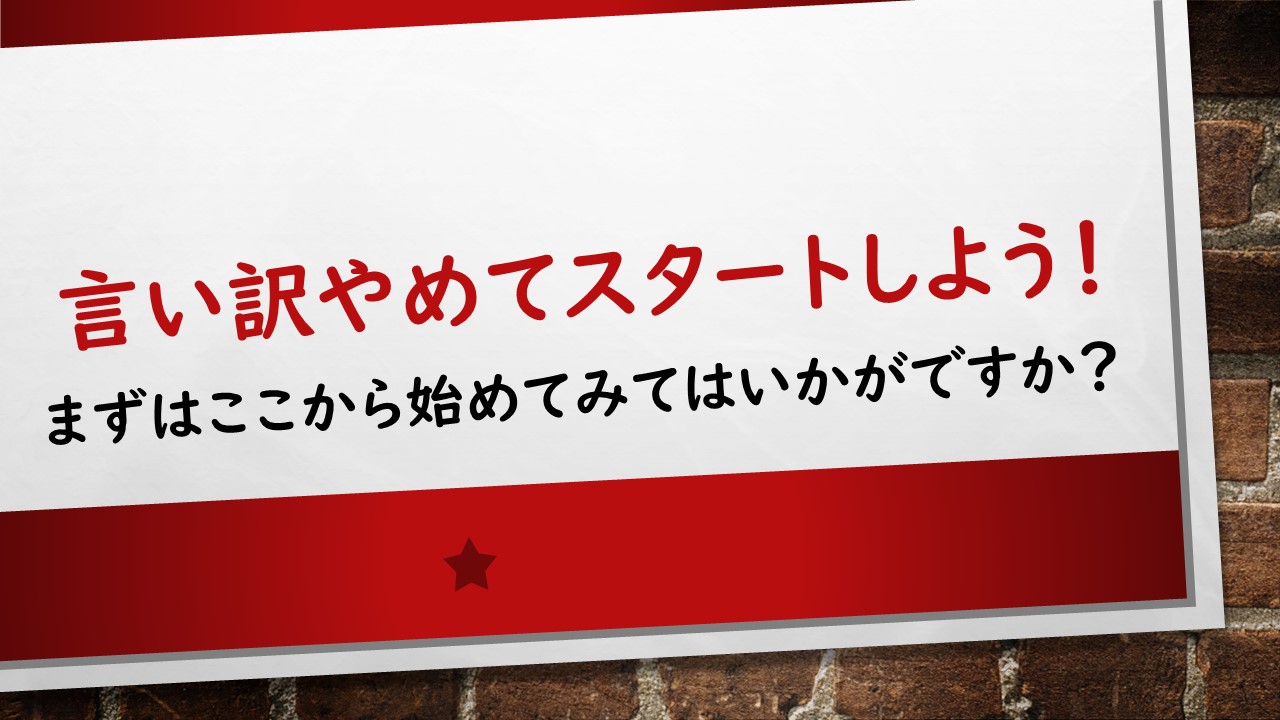 2021年
2021年 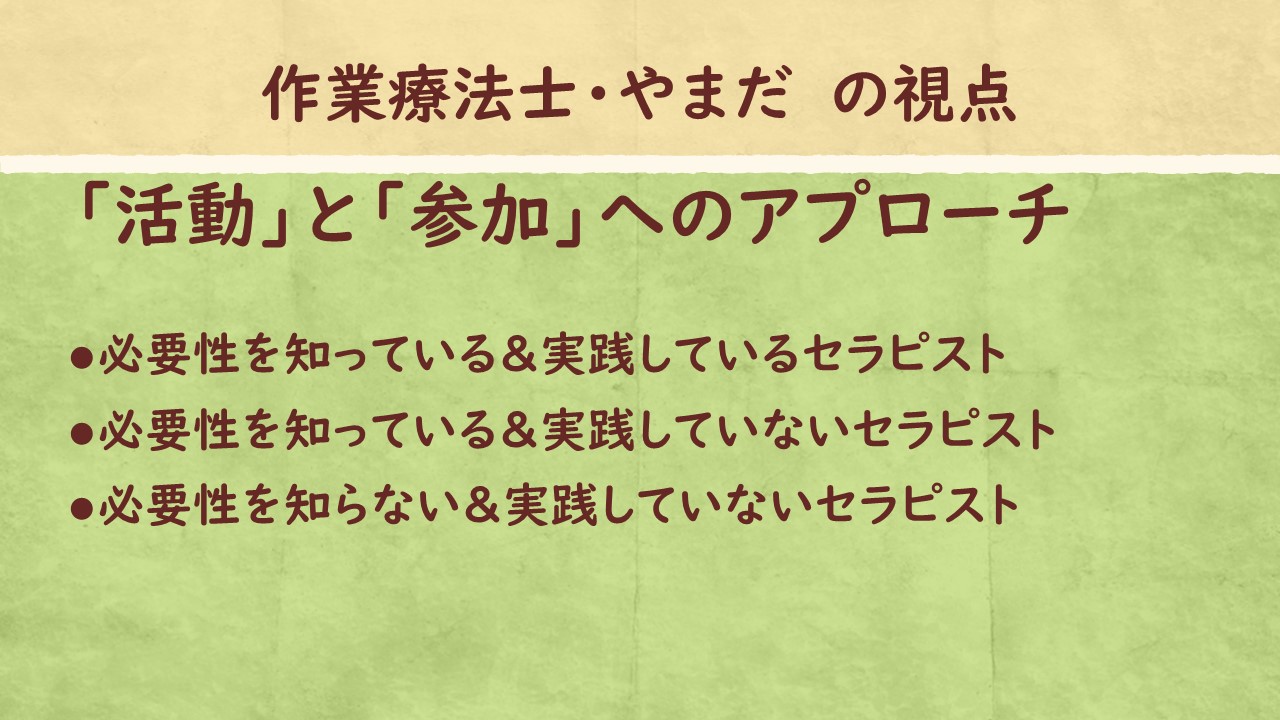 2021年
2021年 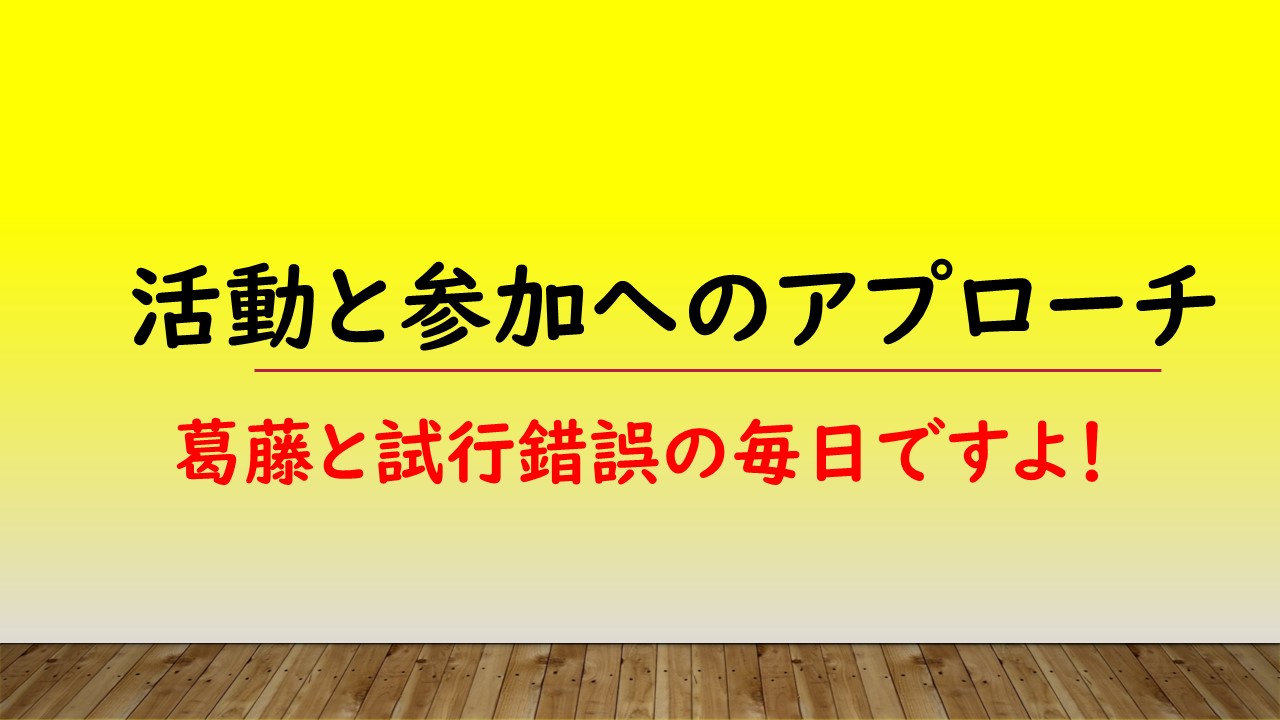 note
note 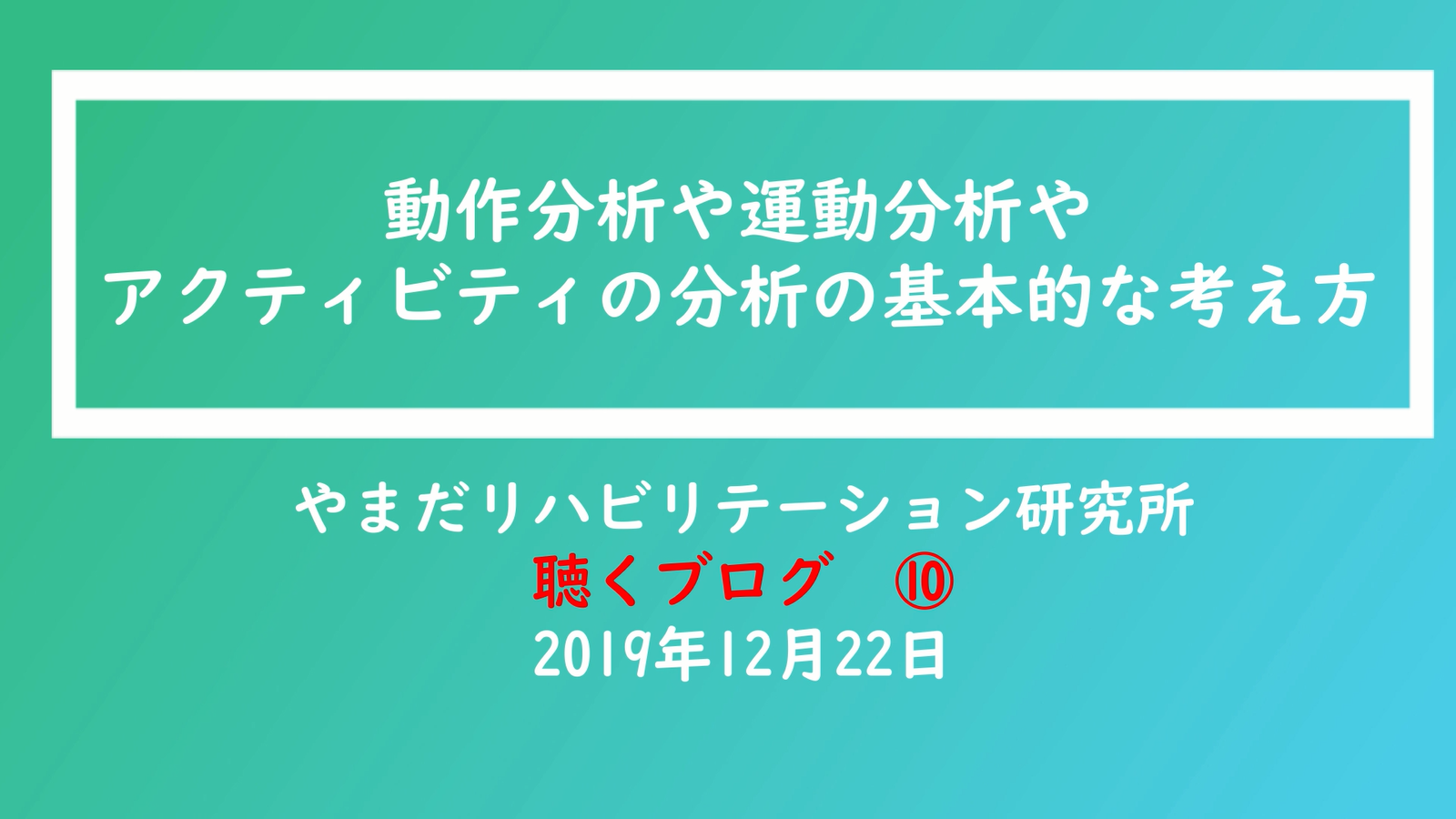 おすすめ
おすすめ 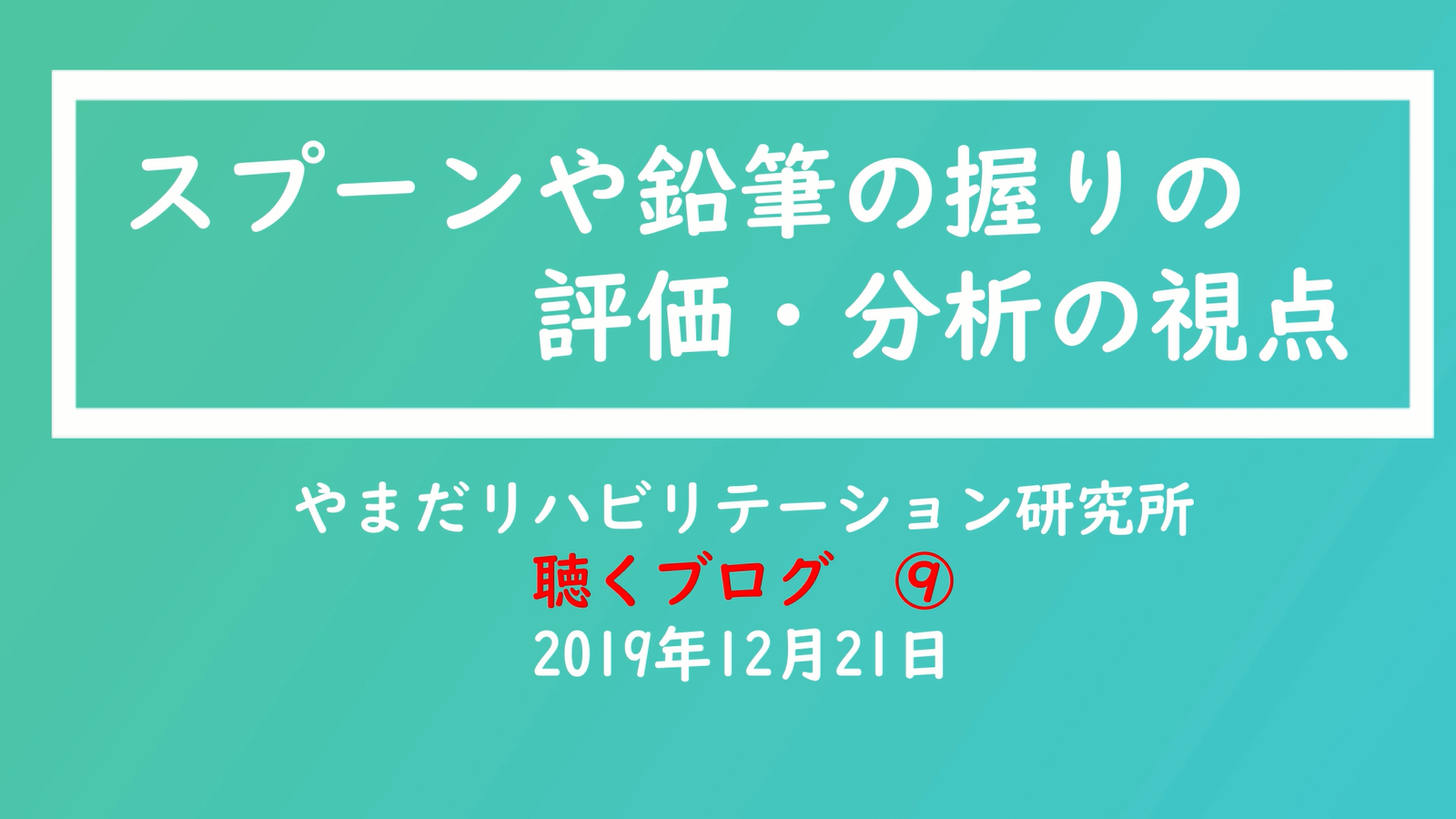 動画
動画 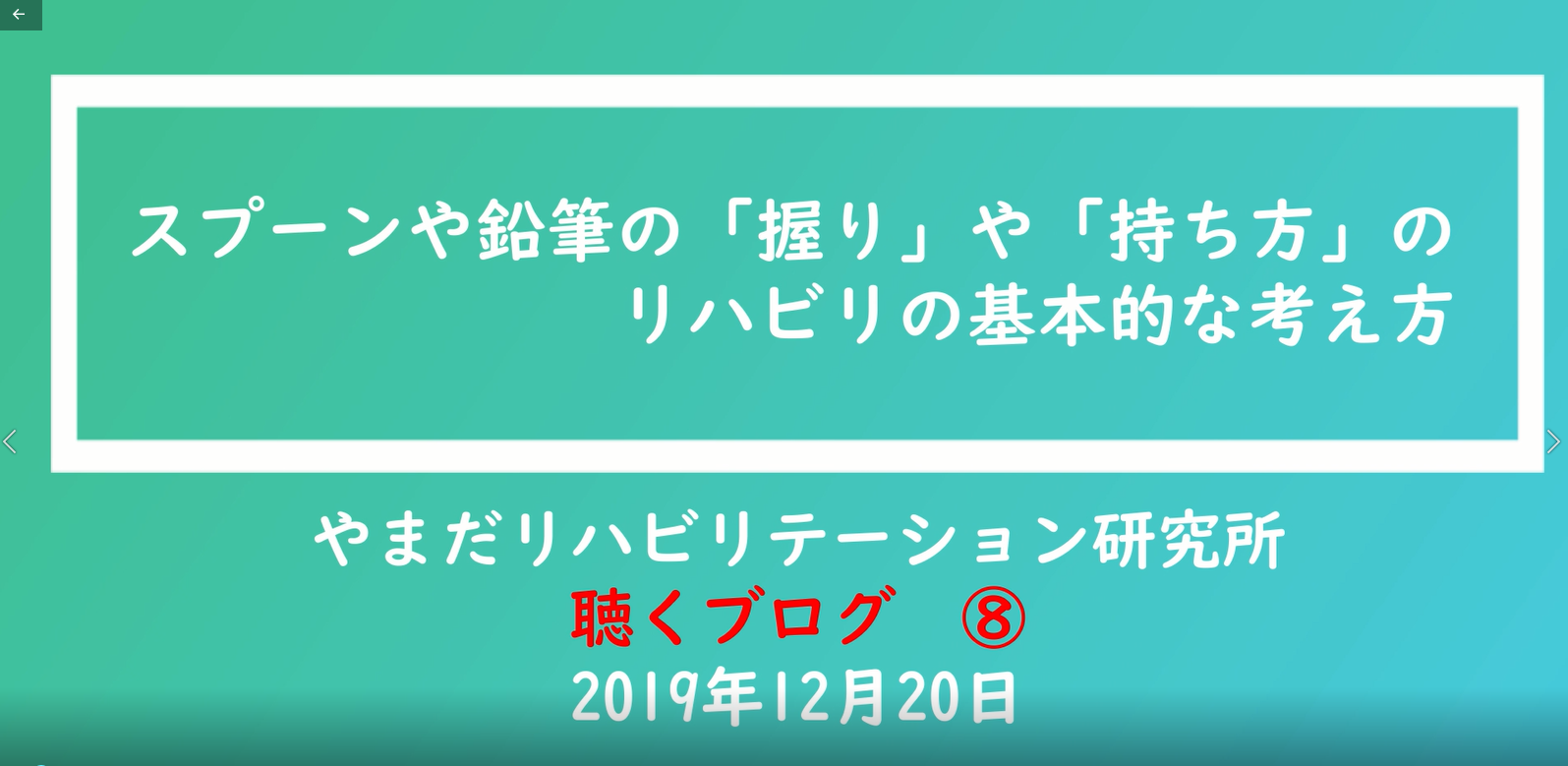 動画
動画 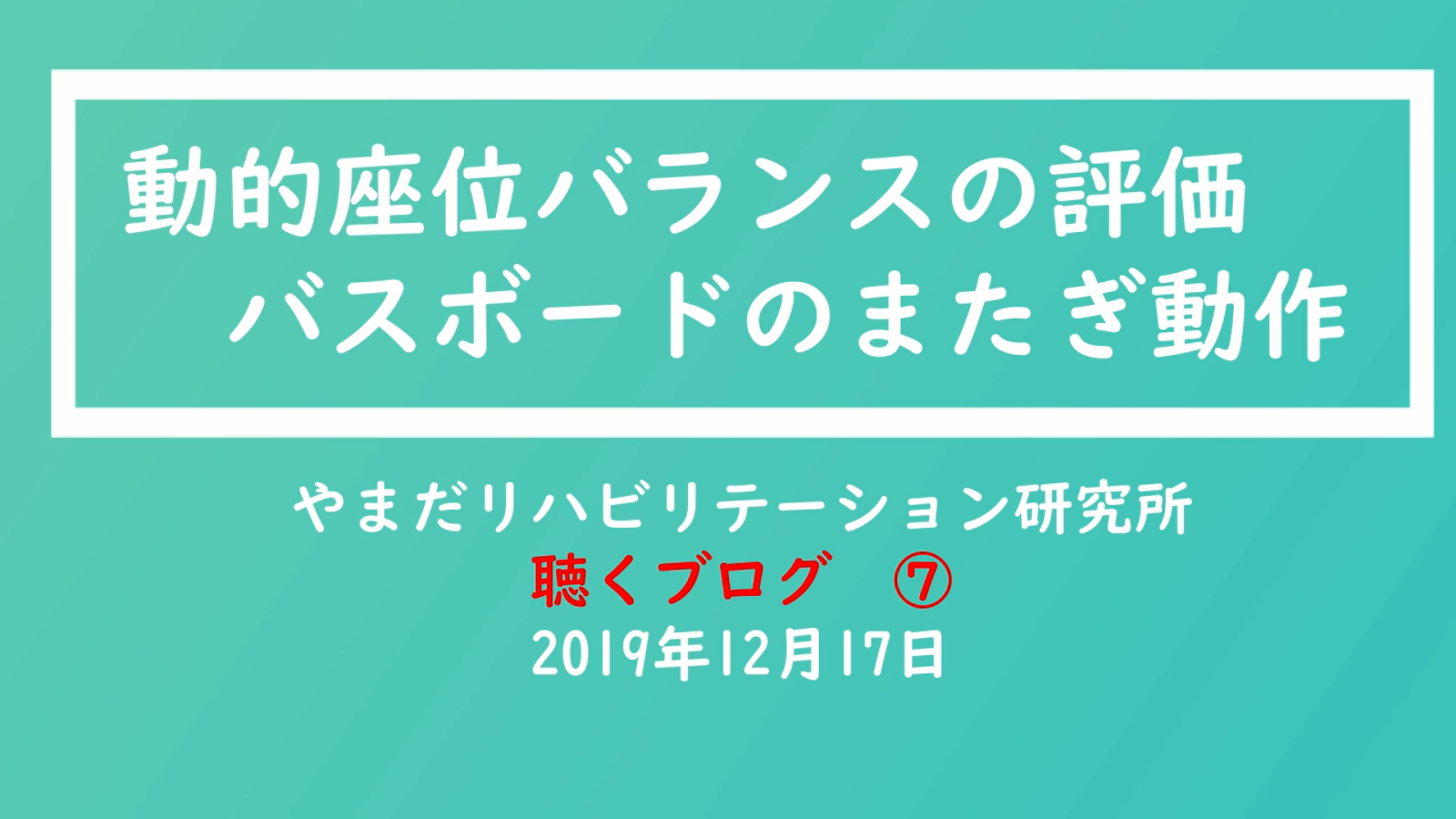 動画
動画 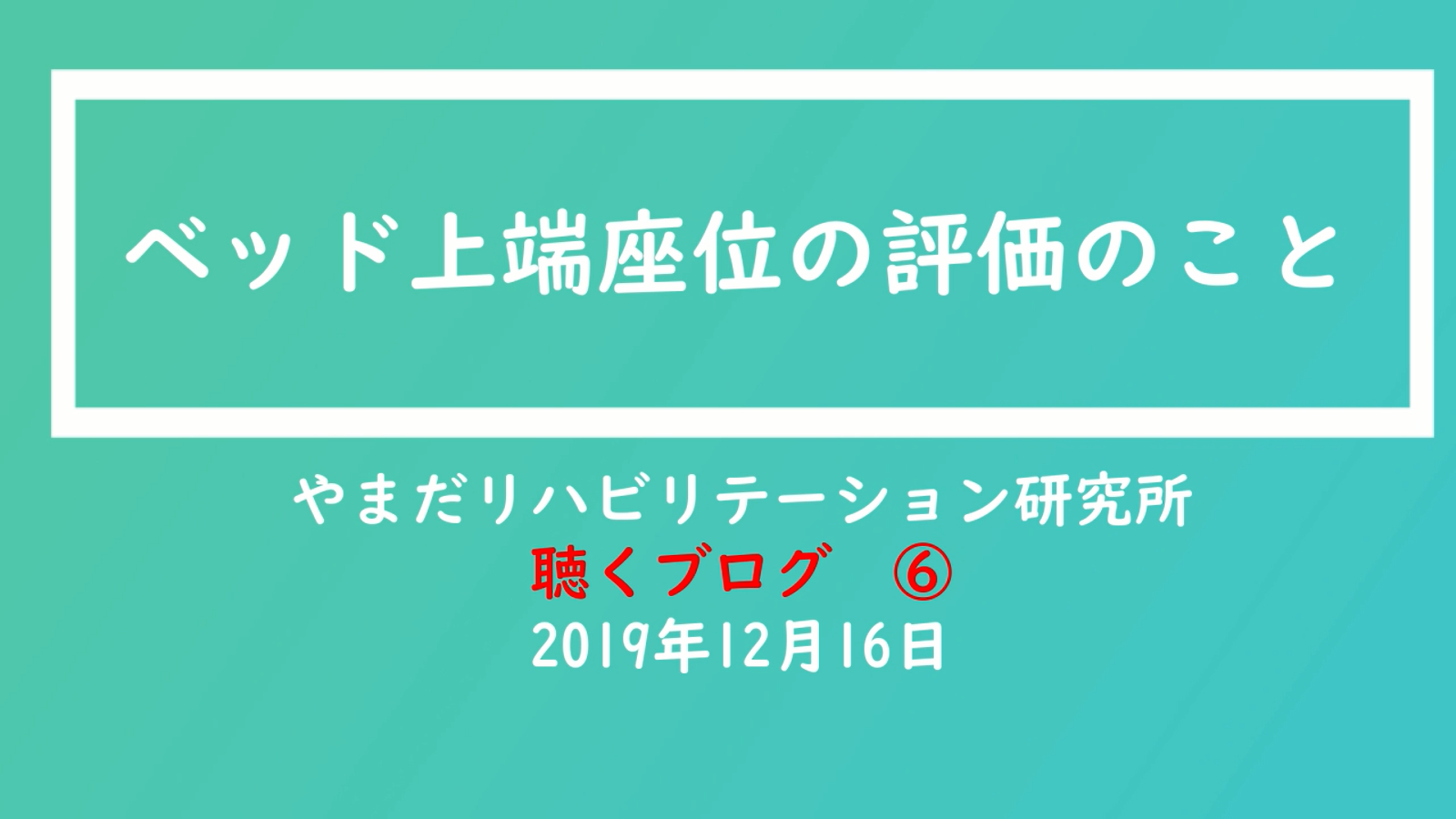 動画
動画 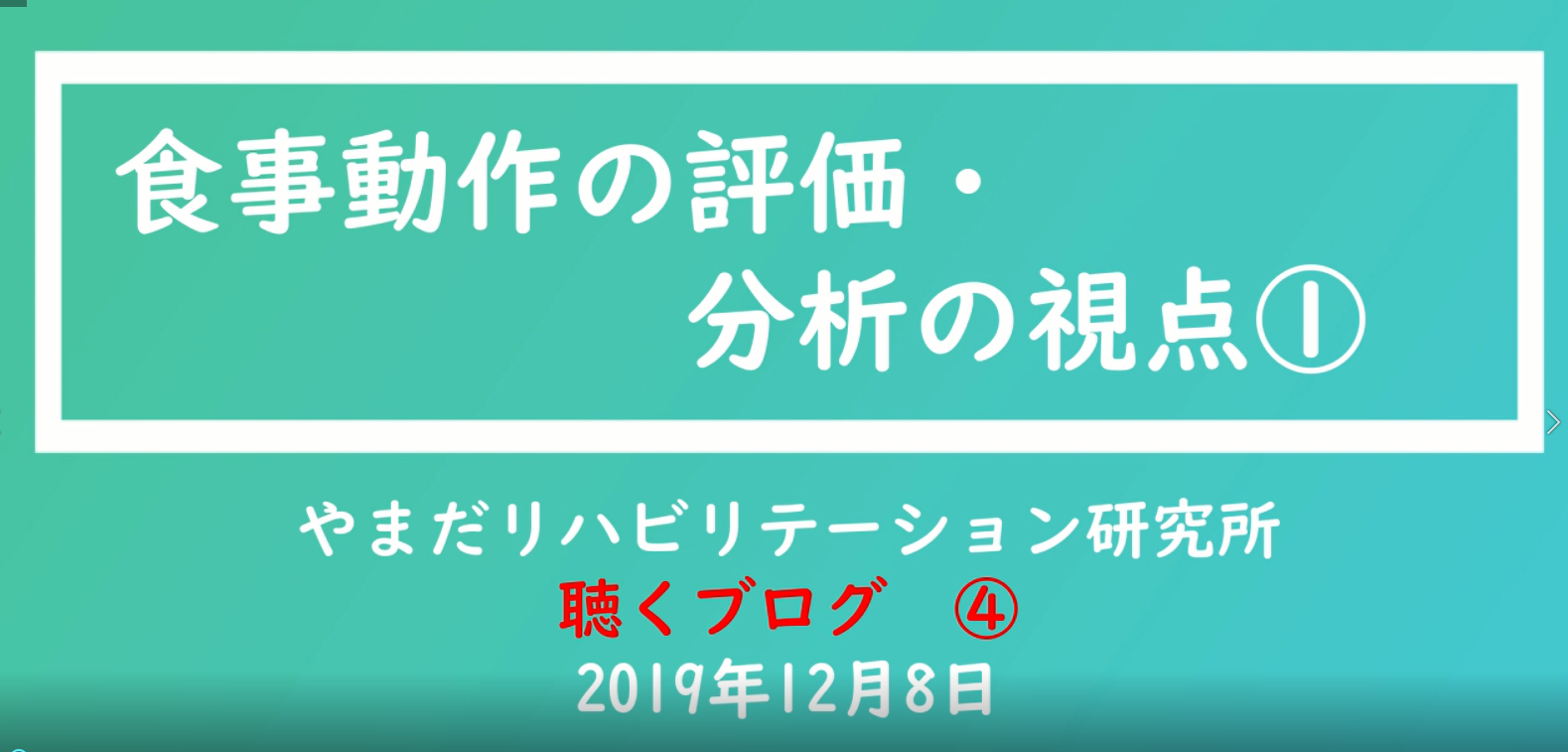 おすすめ
おすすめ 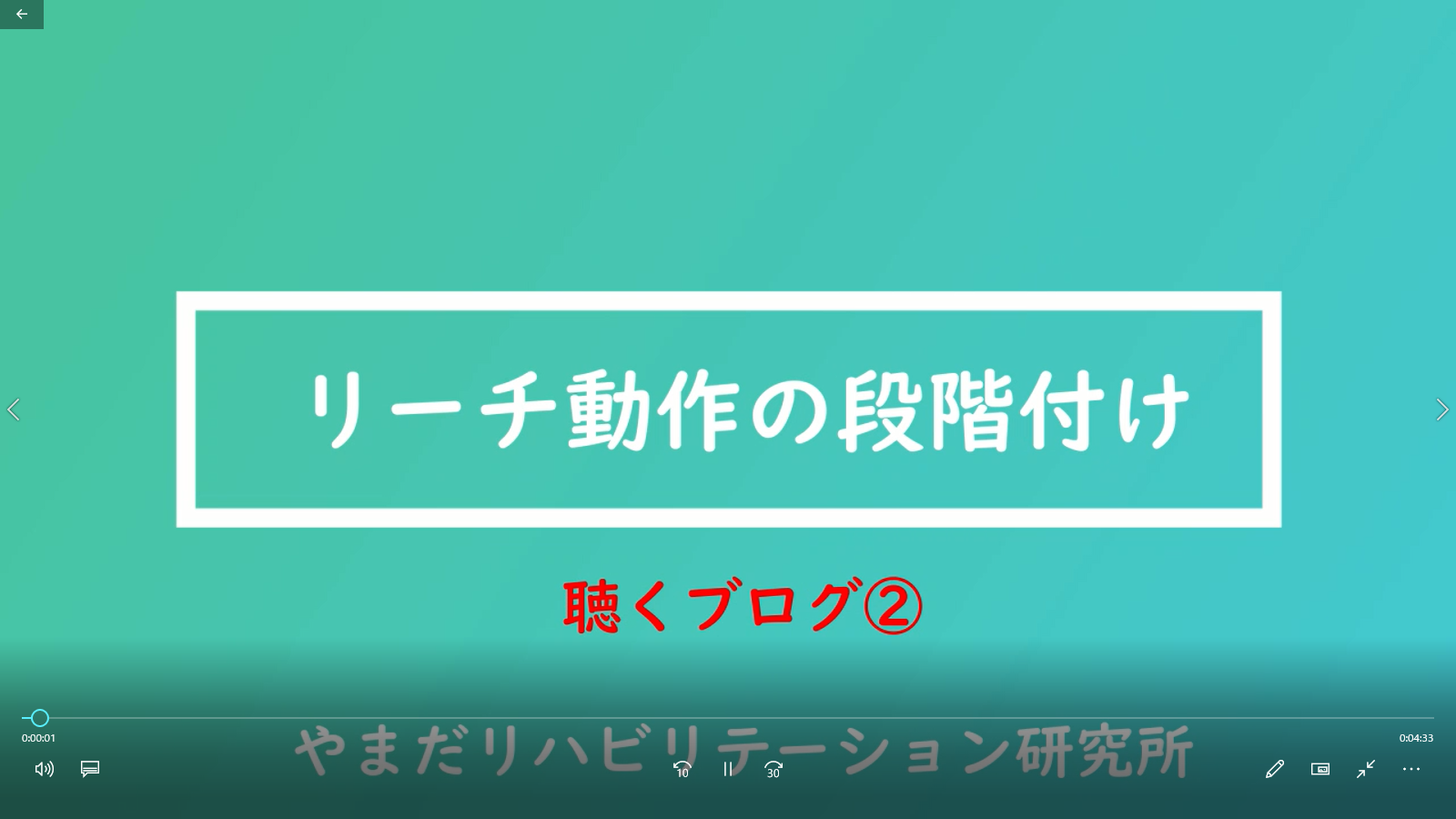 動画
動画 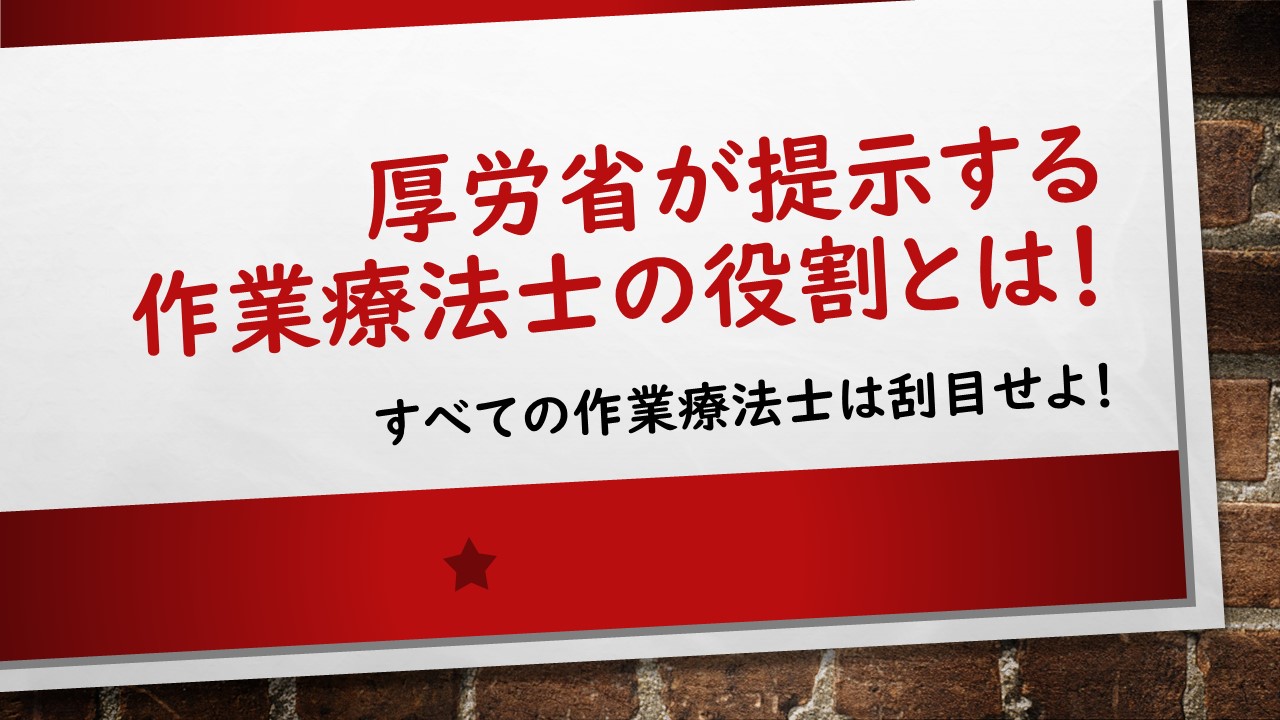 note
note  回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 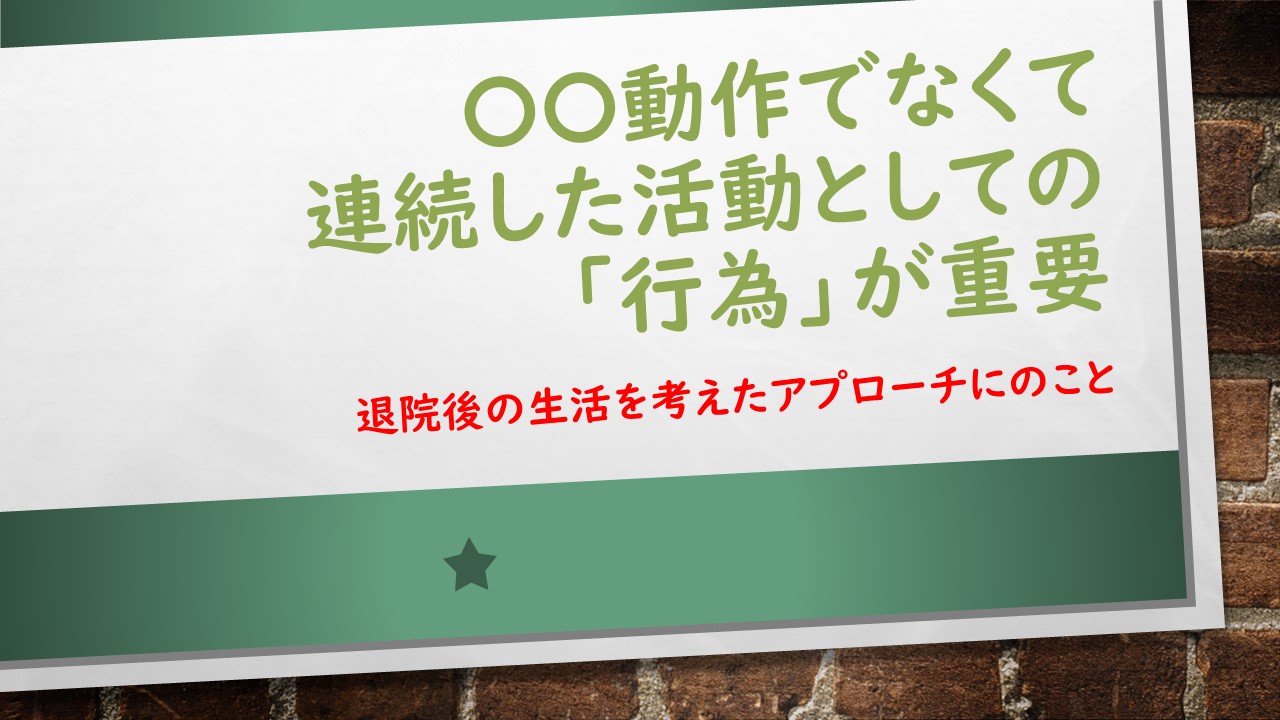 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 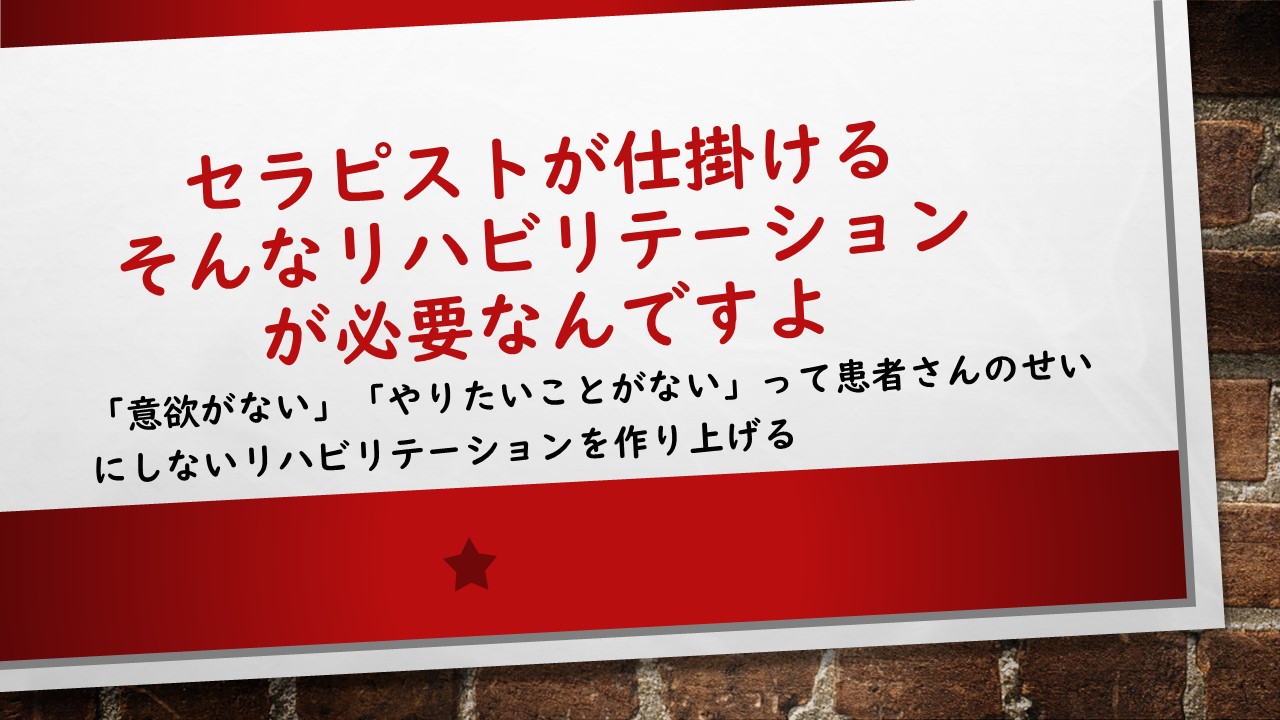 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 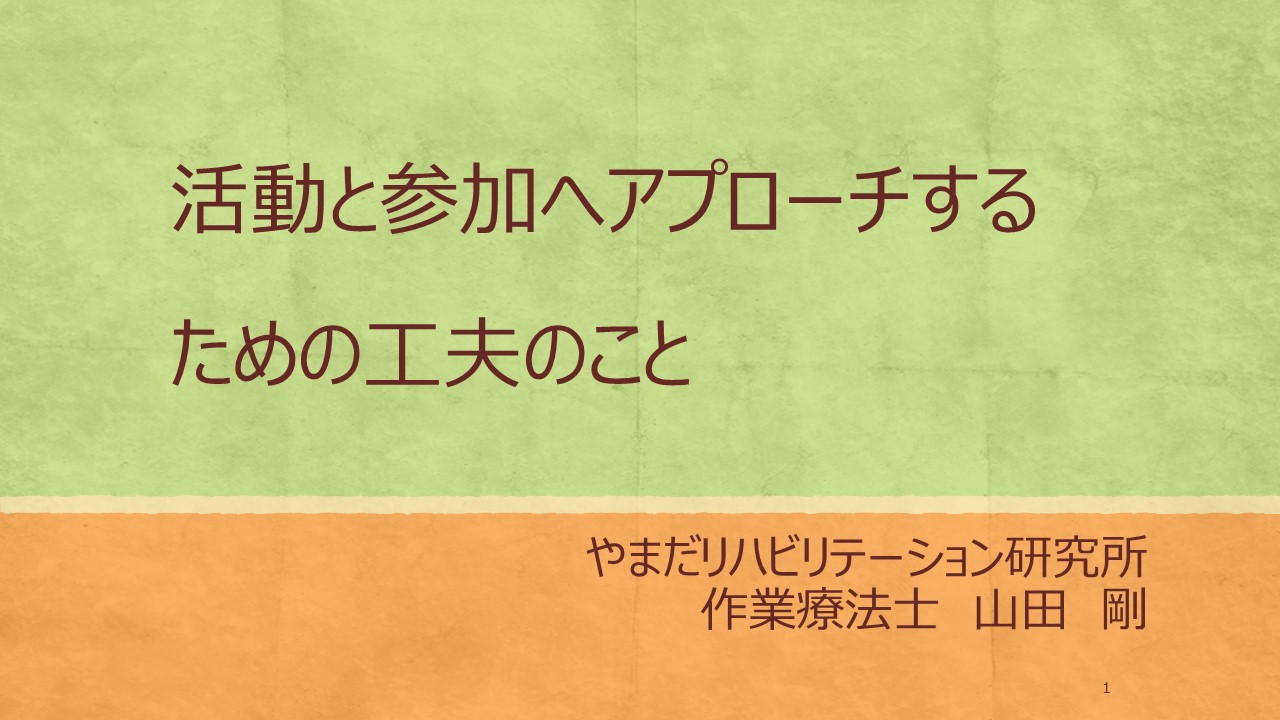 動画
動画 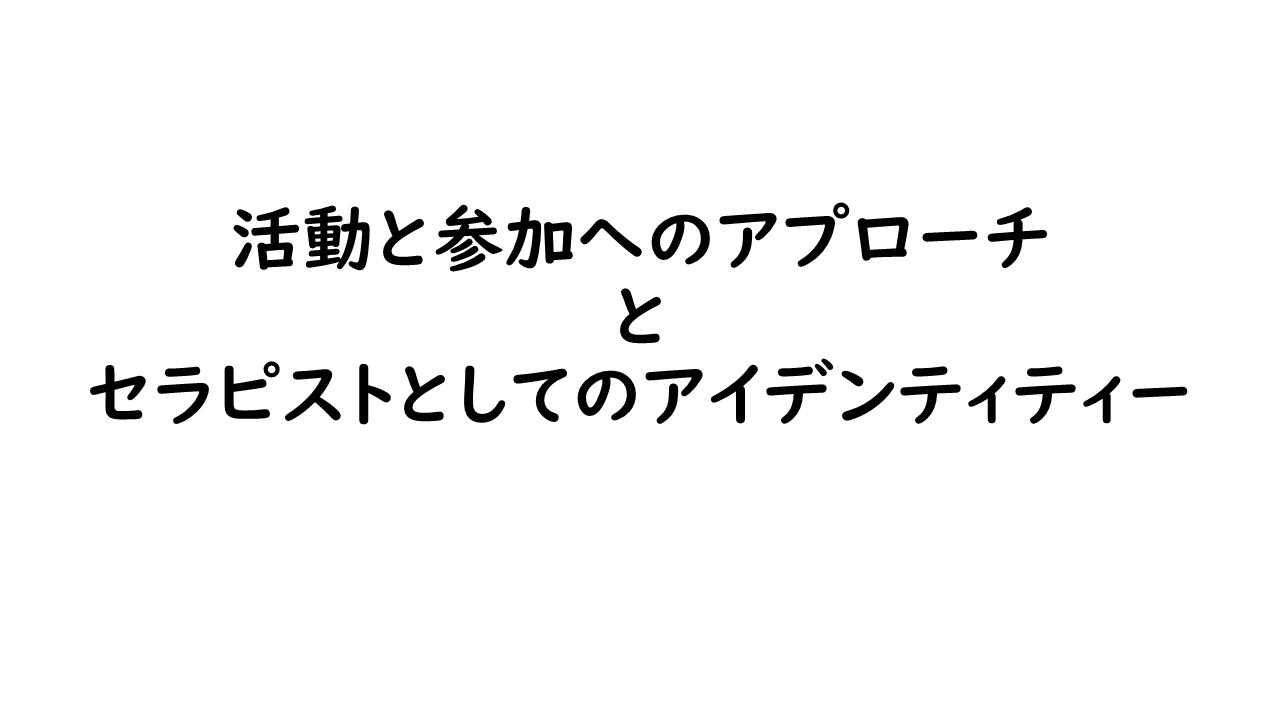 動画
動画 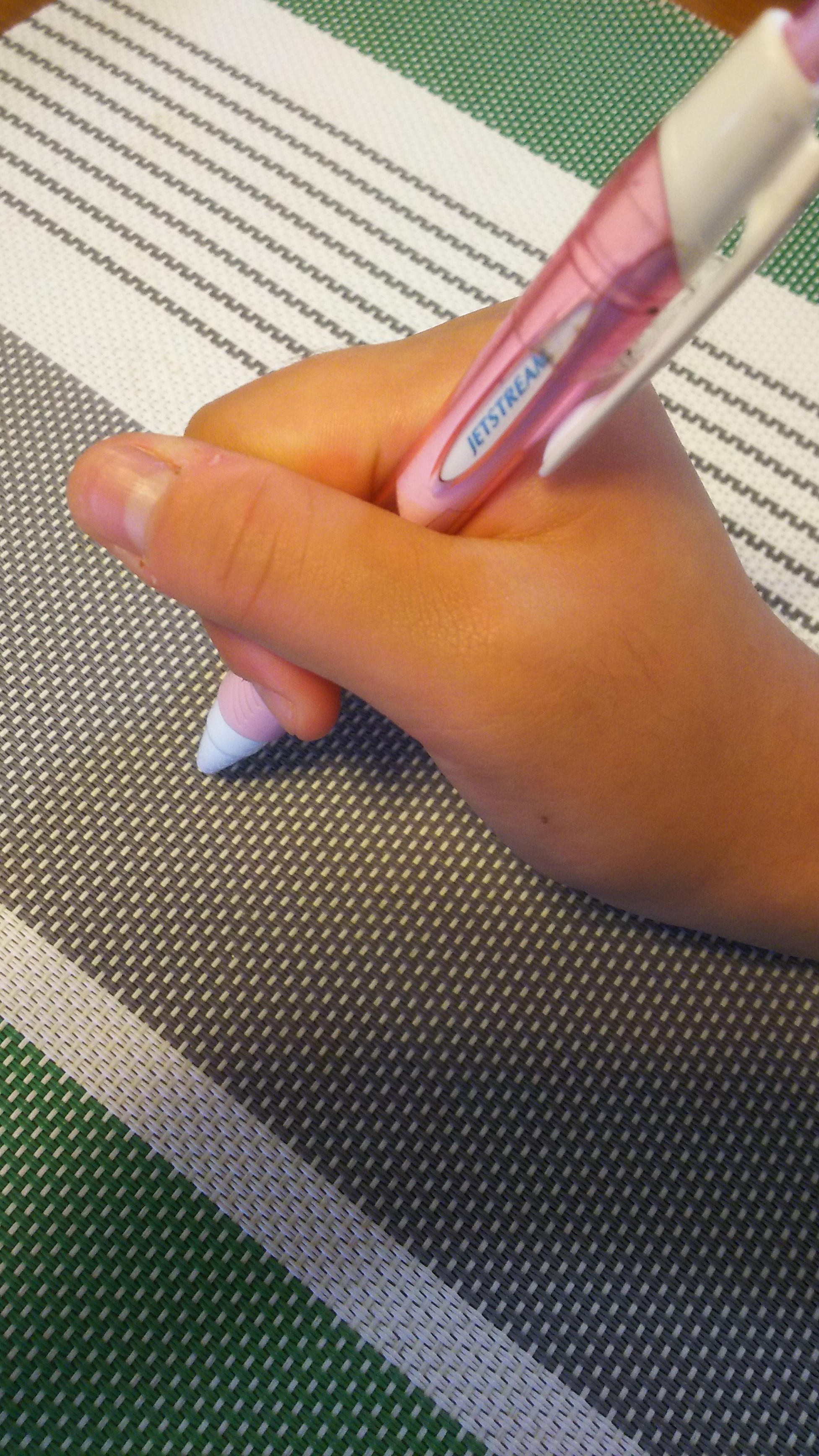 一般の方向け
一般の方向け 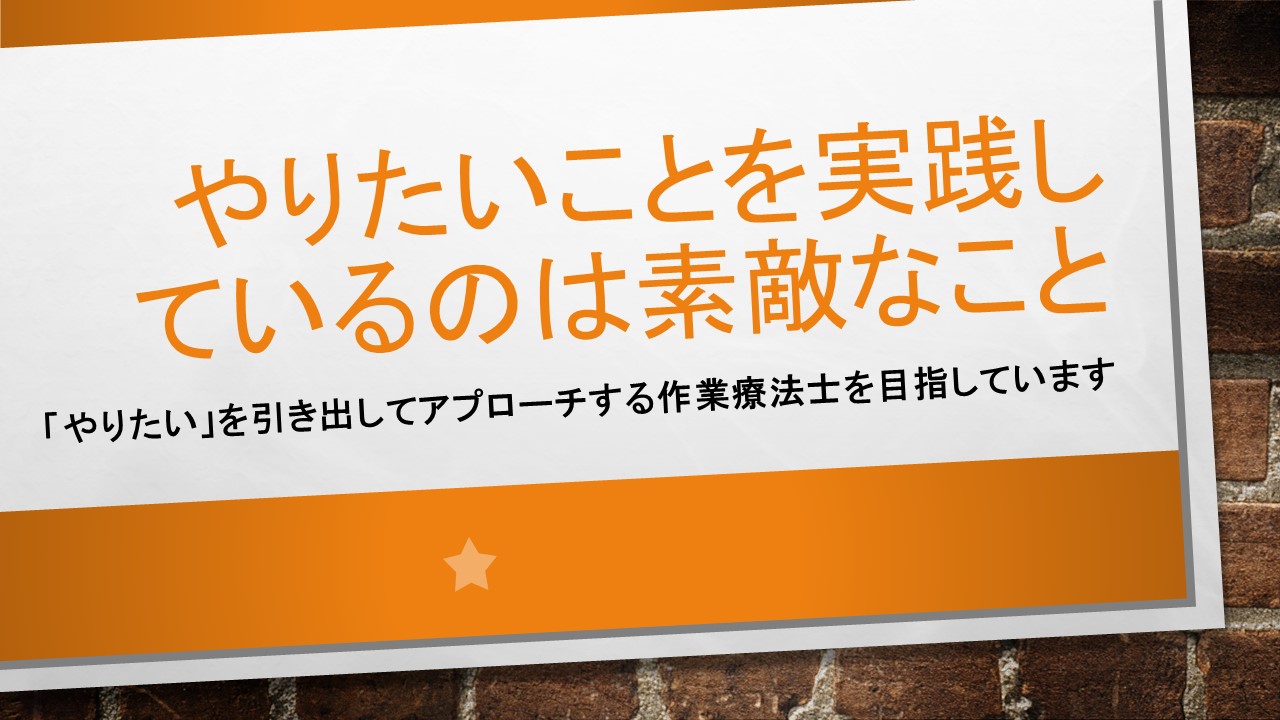 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 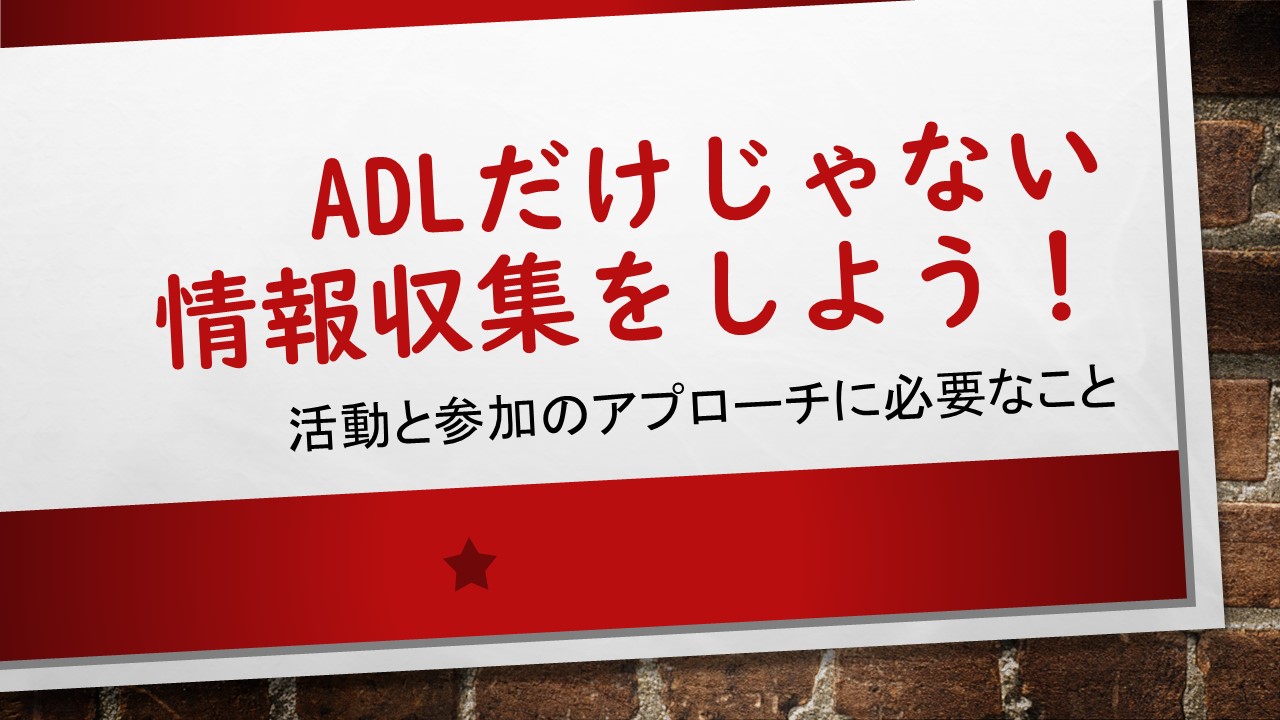 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 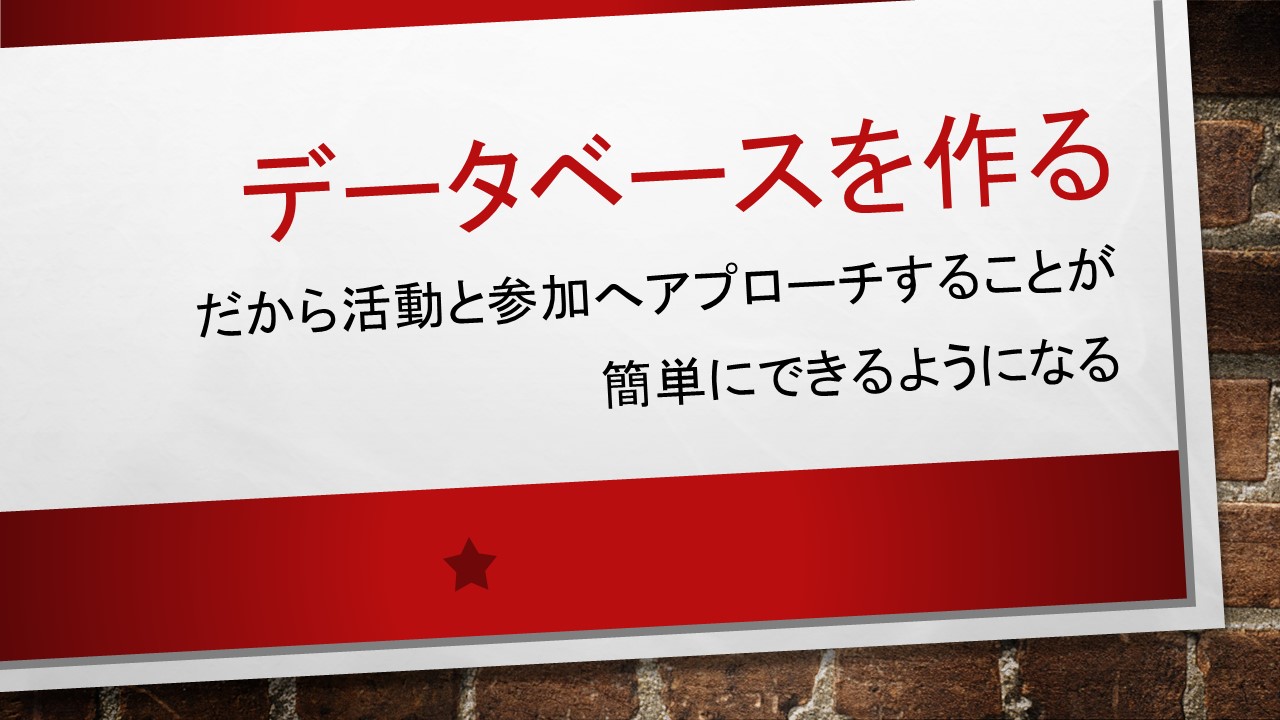 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 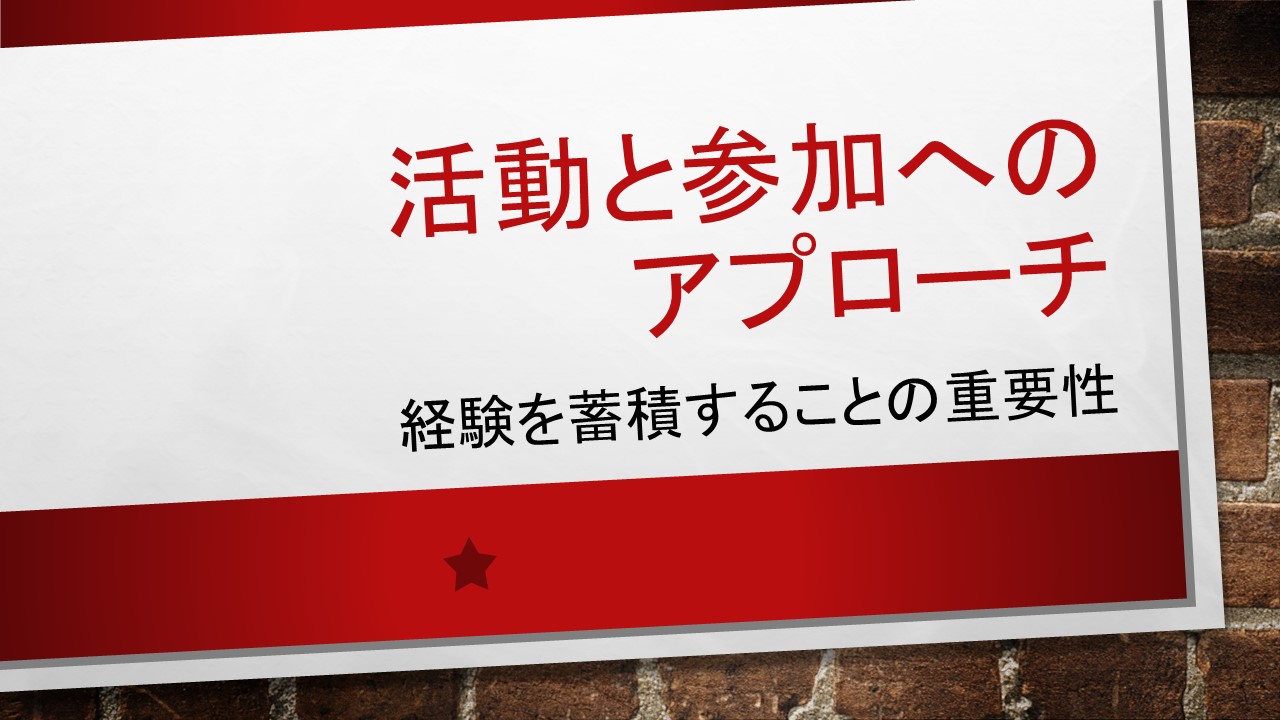 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 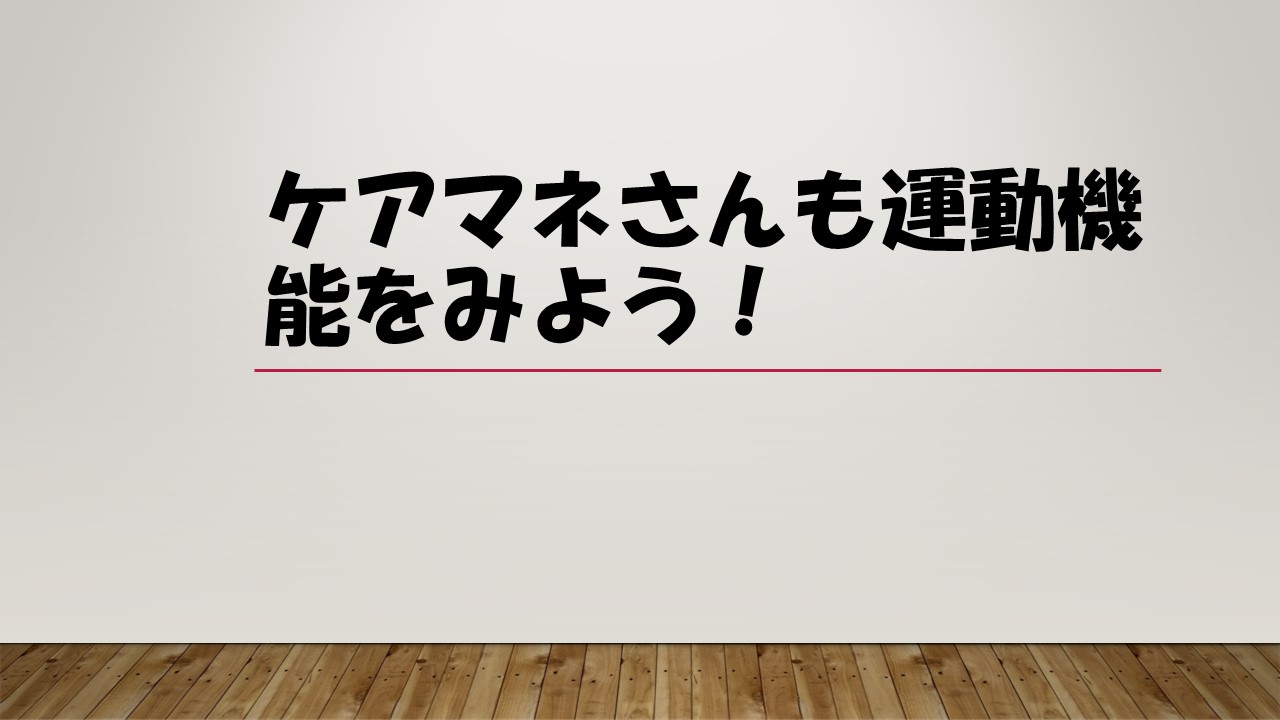 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 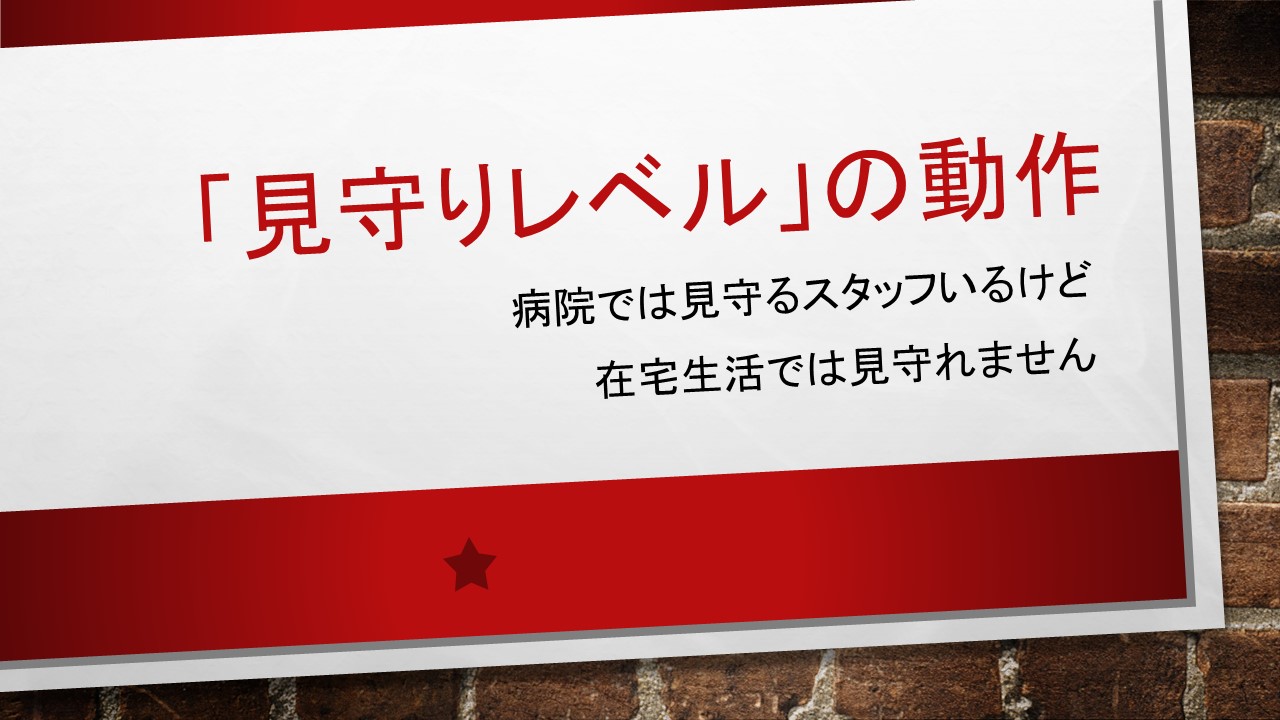 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 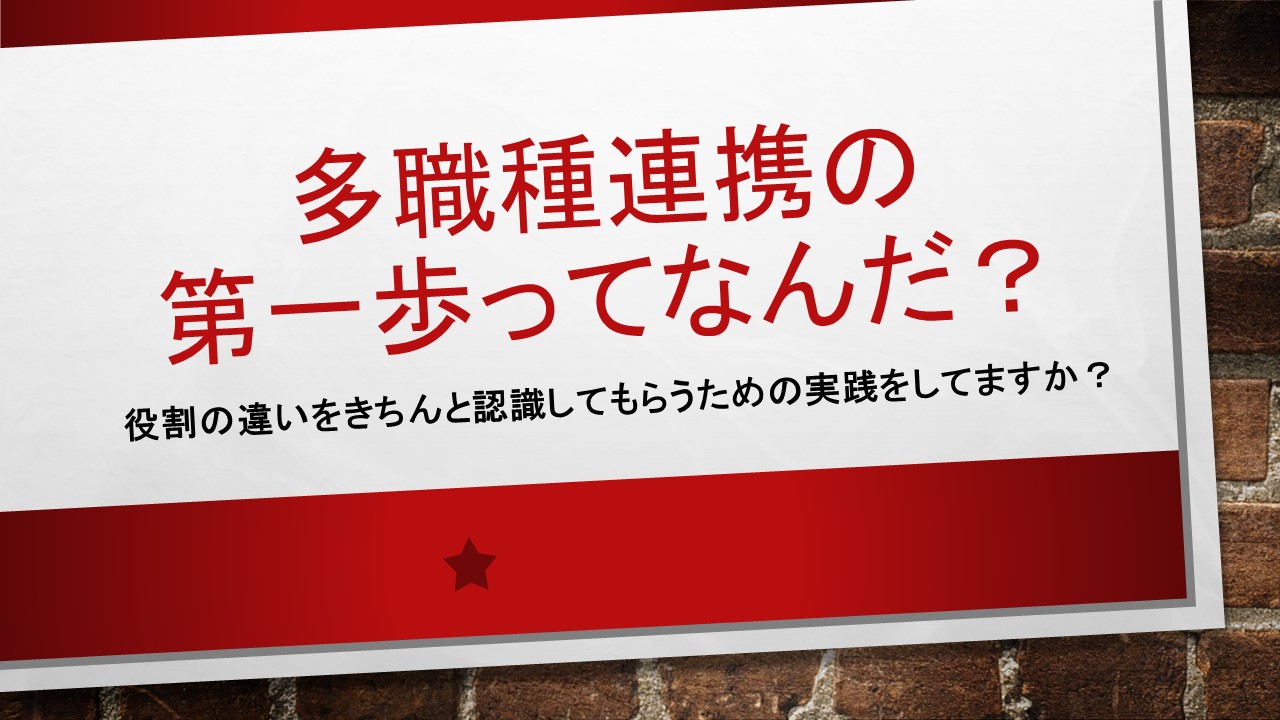 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 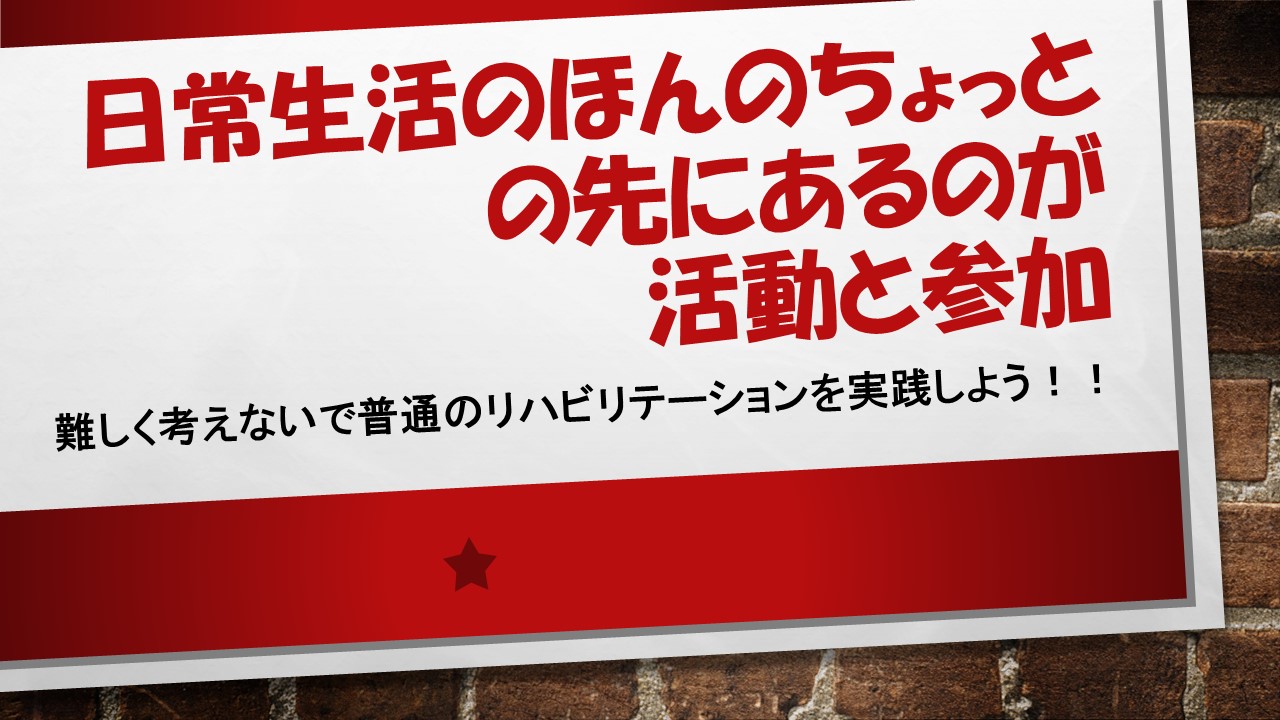 note
note