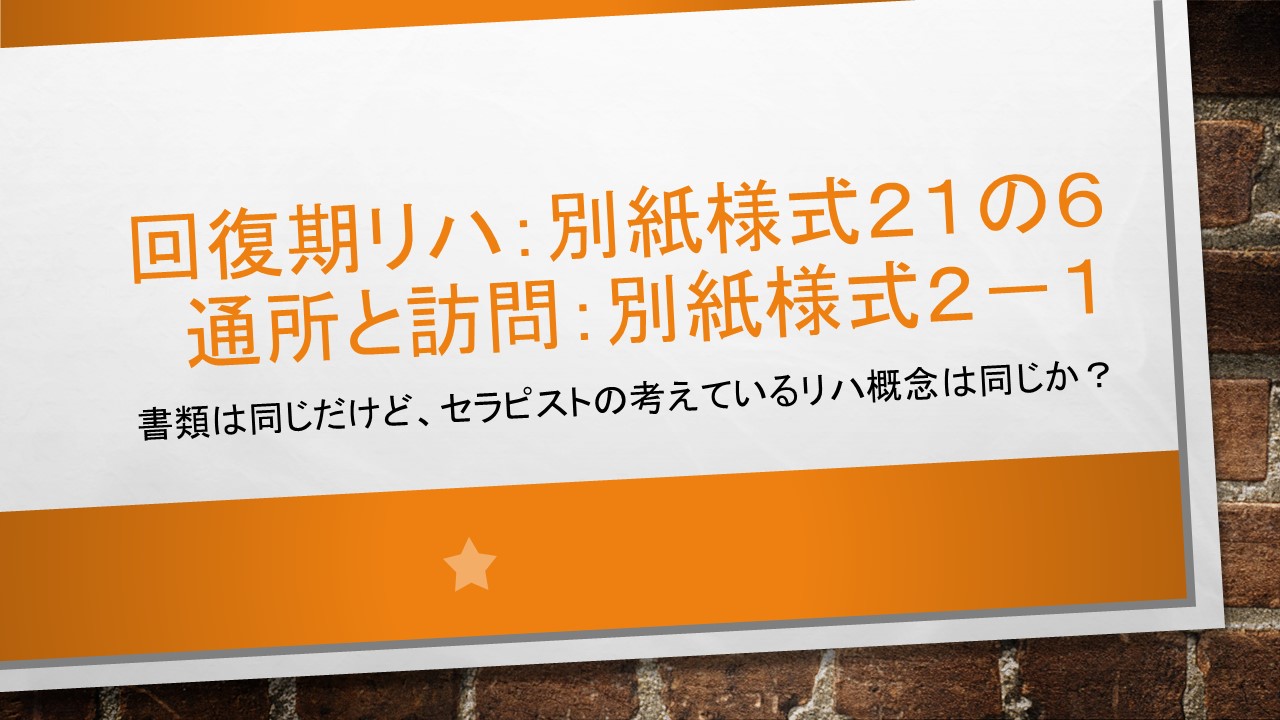 note
note 書類は共通化したけど、リハ専門職の考え方はどうなんだ?
書類を共通化したからといって、スムースに連携できるわけではないんだよってことを書いています。
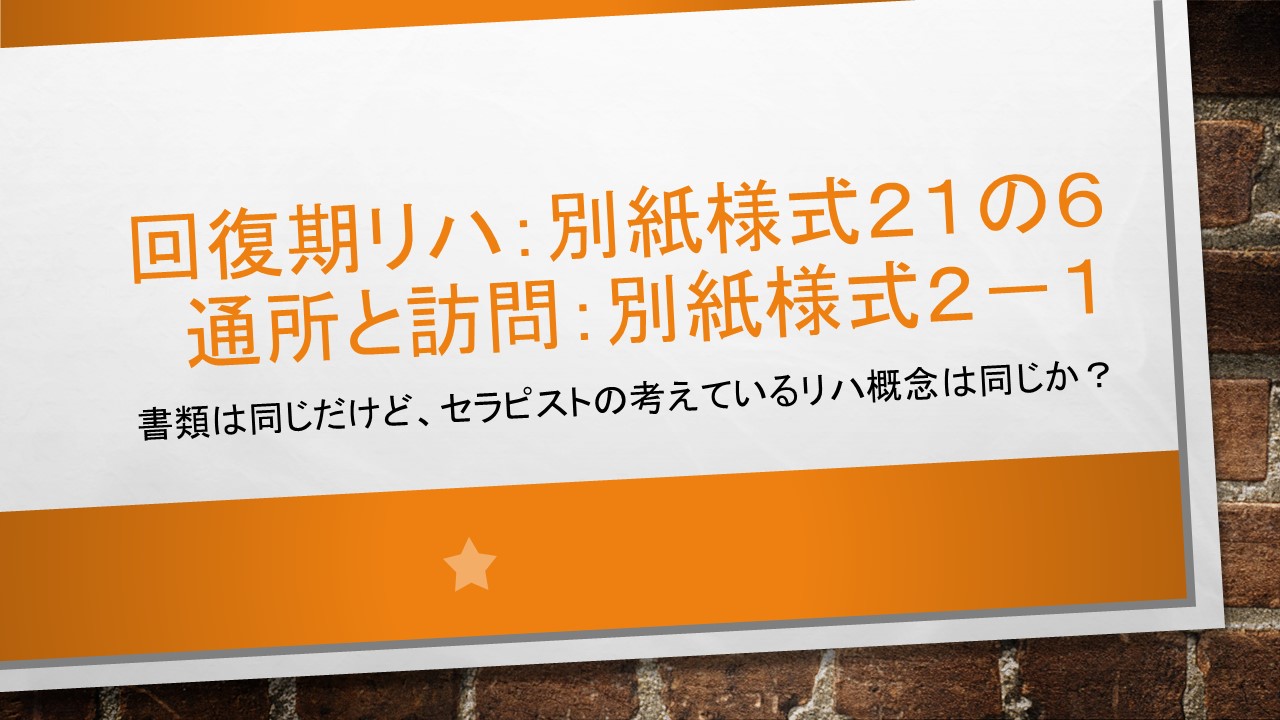 note
note 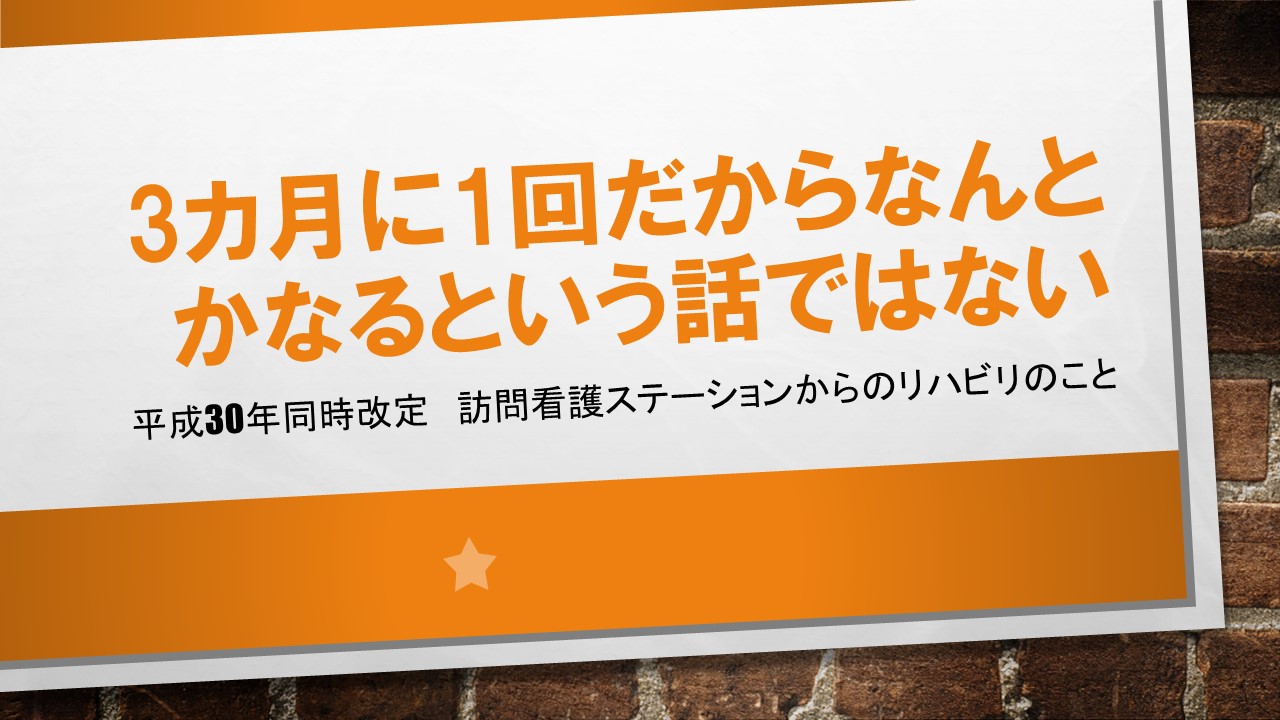 note
note 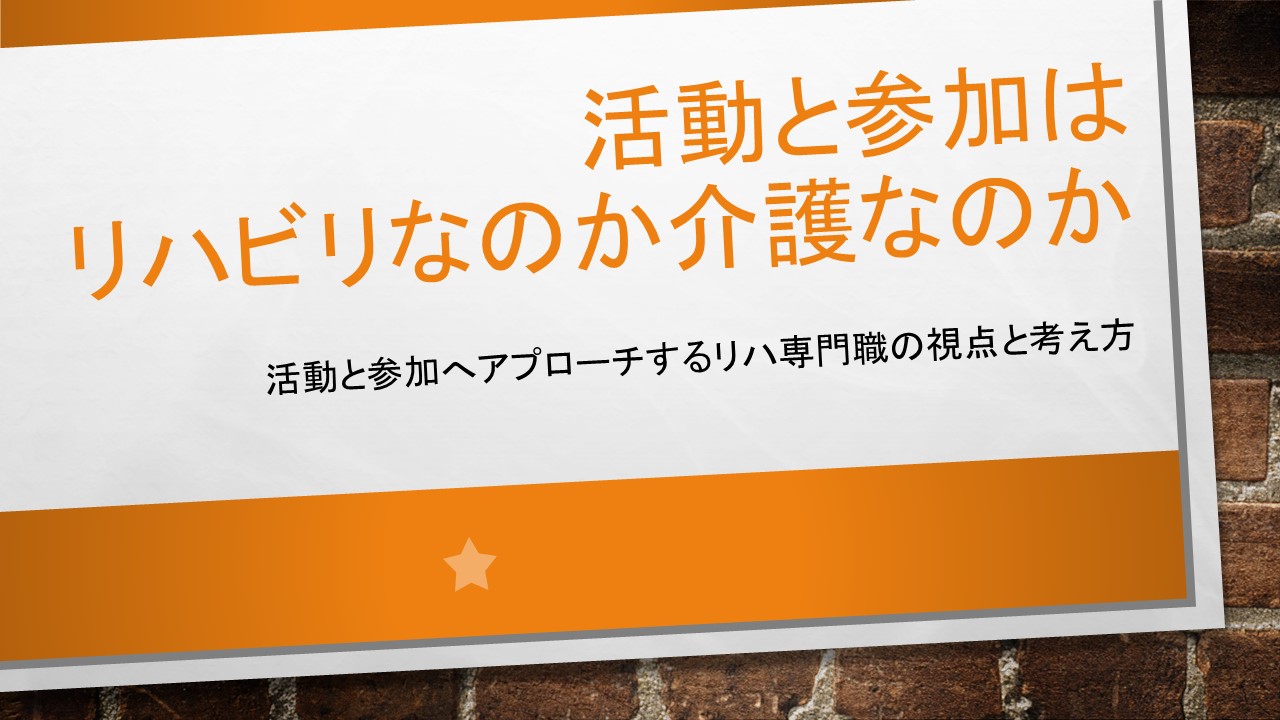 note
note 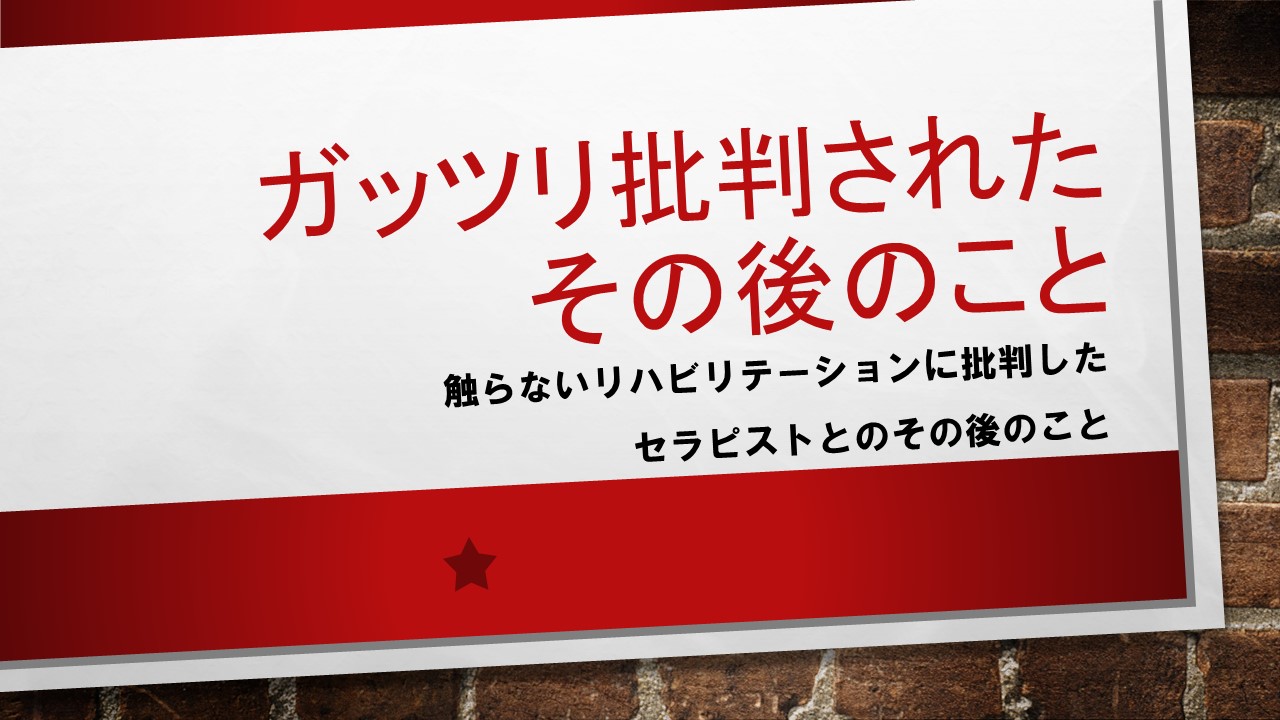 note
note 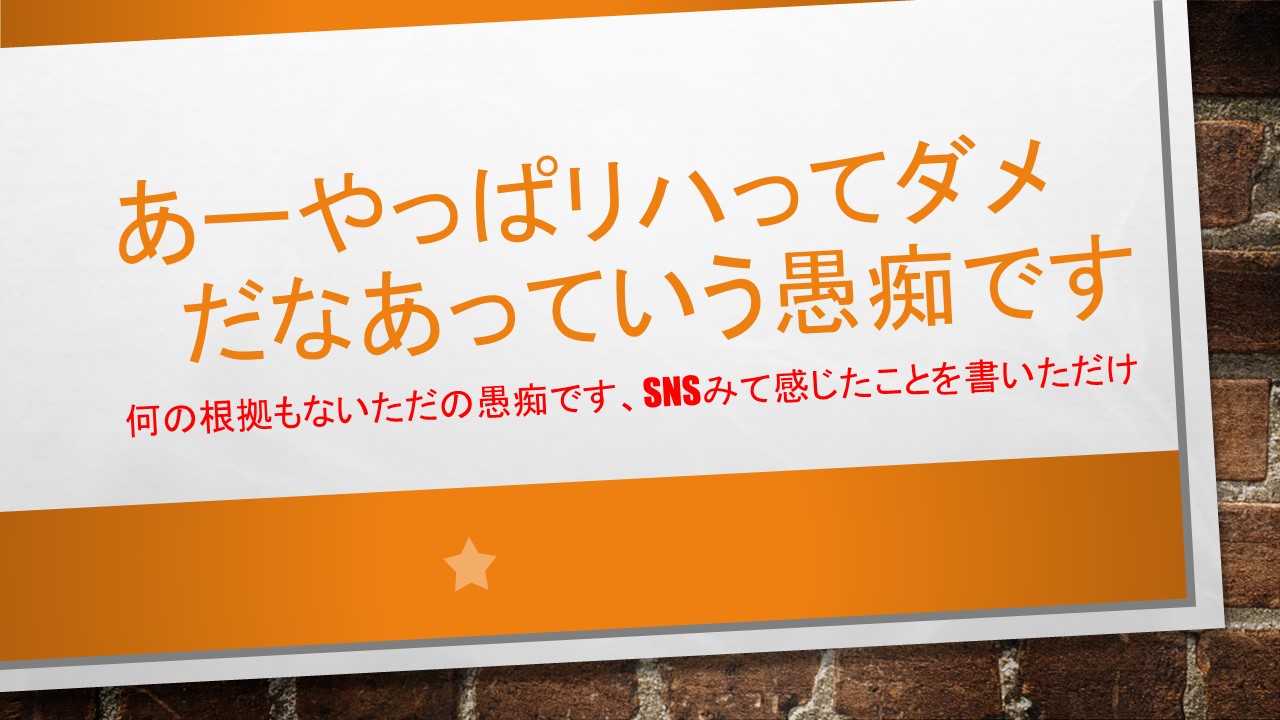 note
note  note
note 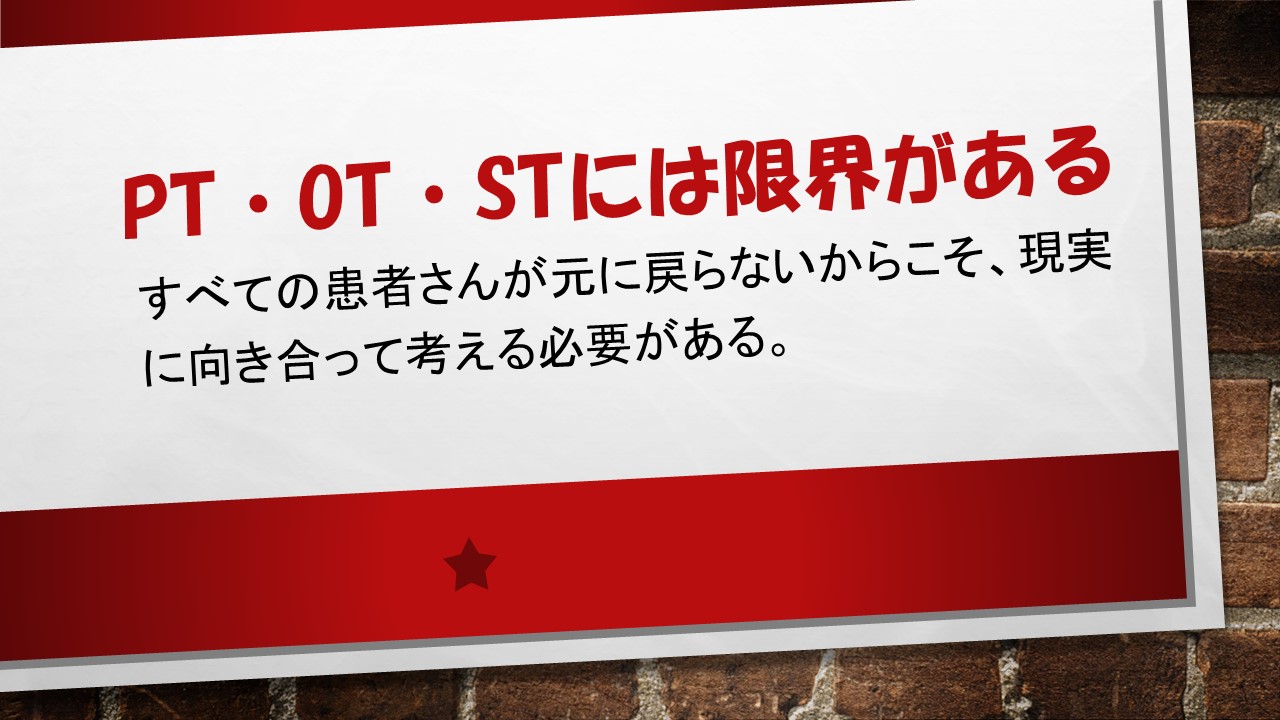 note
note  note
note 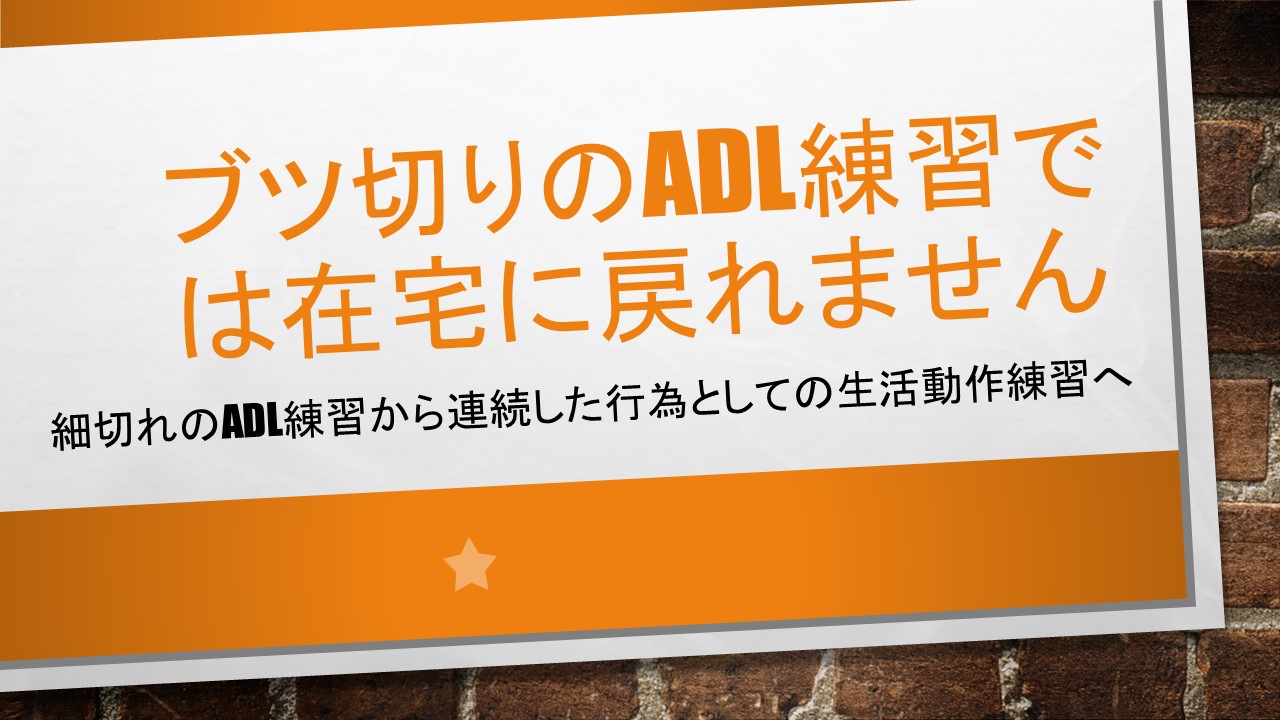 note
note 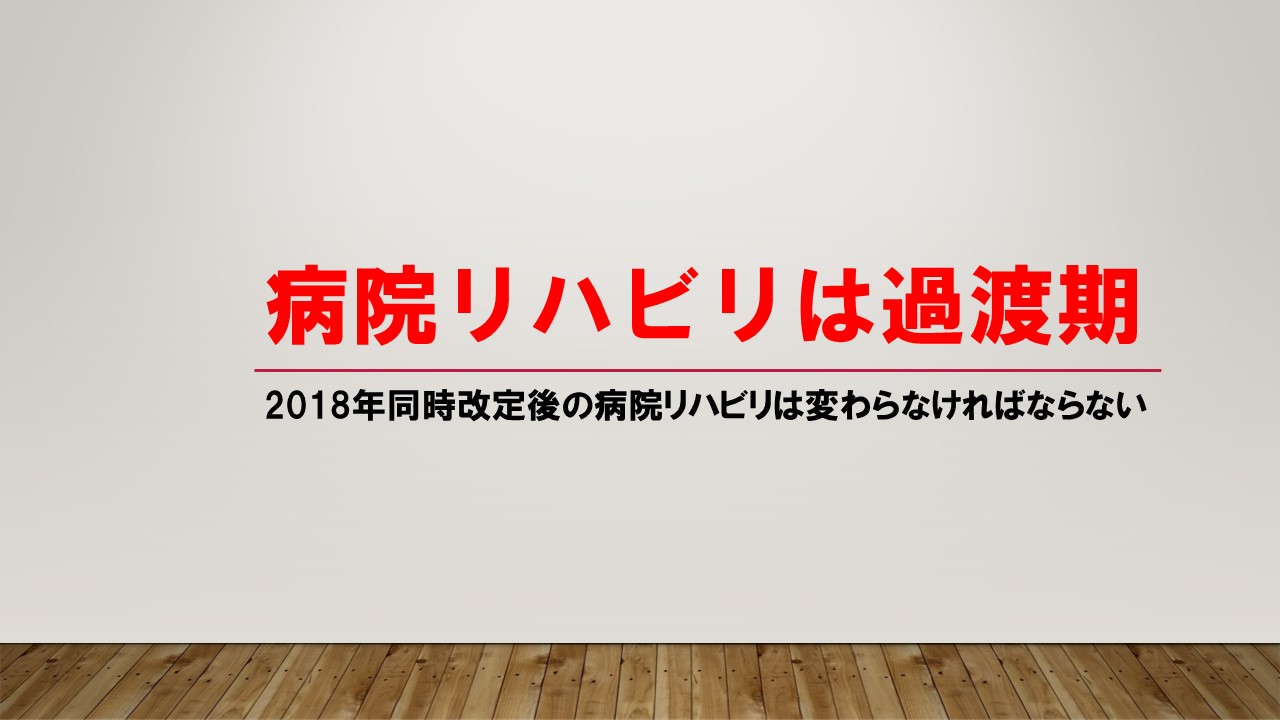 note
note 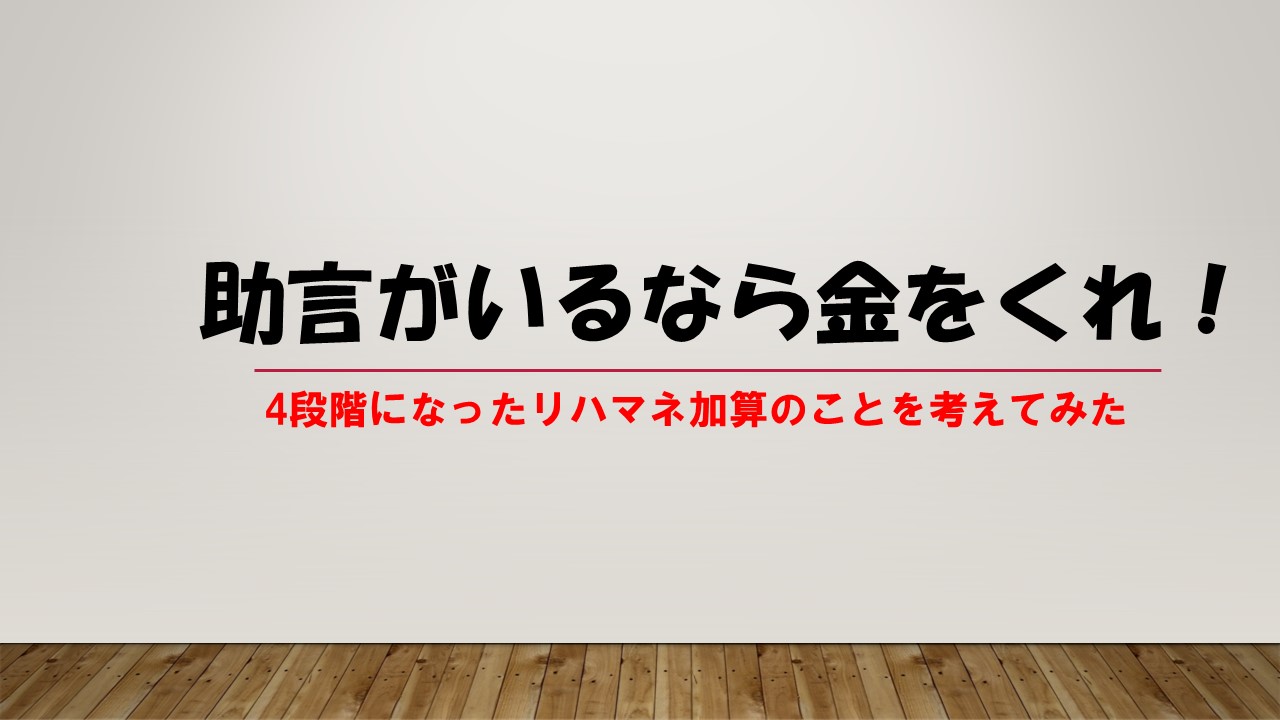 note
note 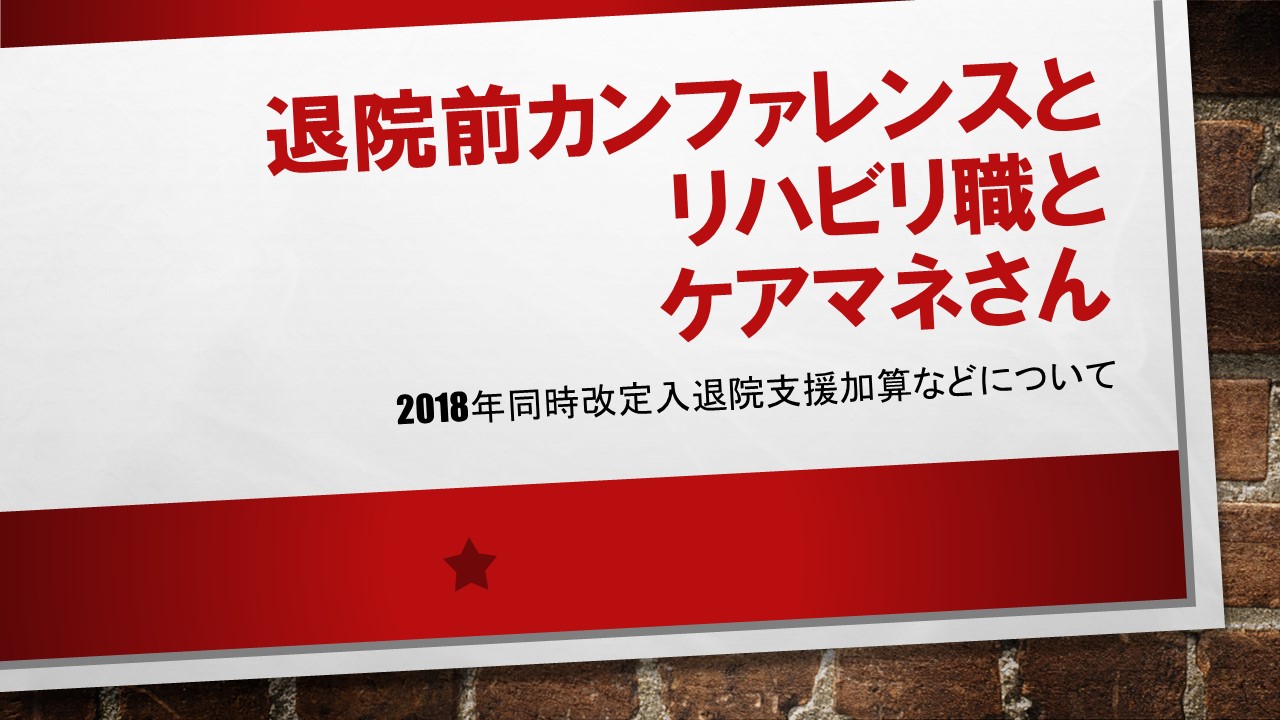 note
note 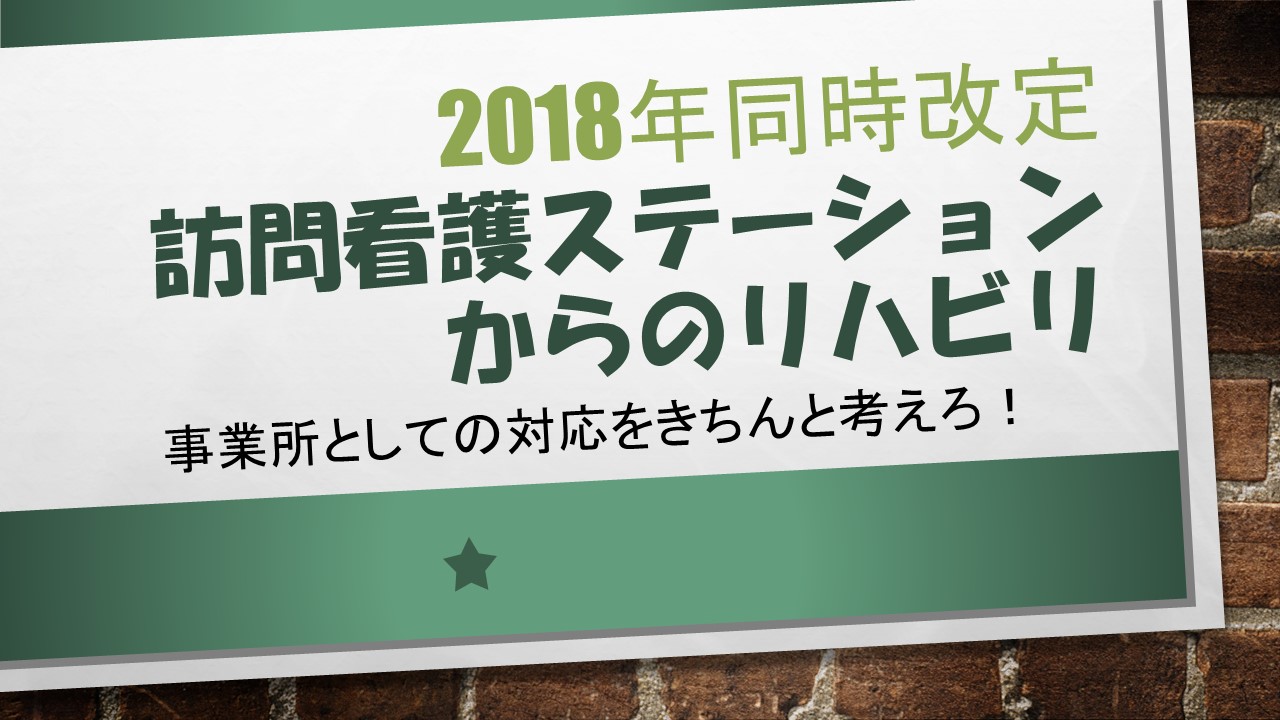 note
note 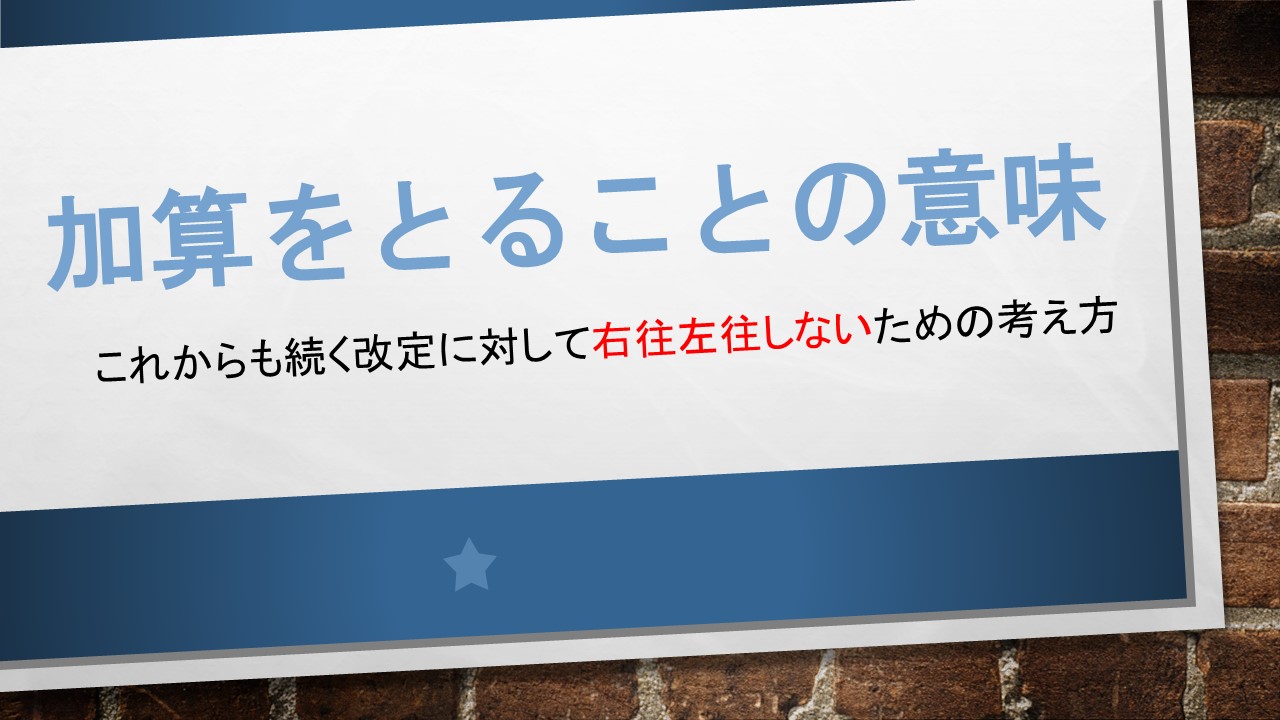 note
note 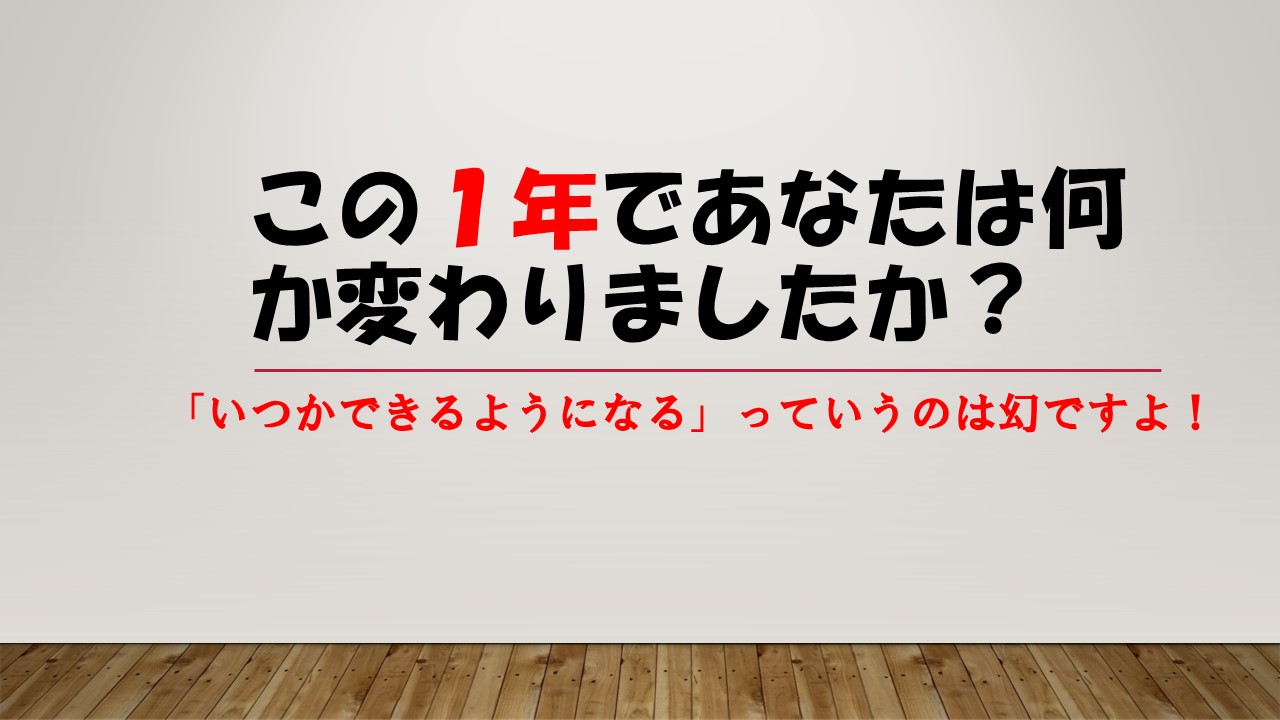 note
note 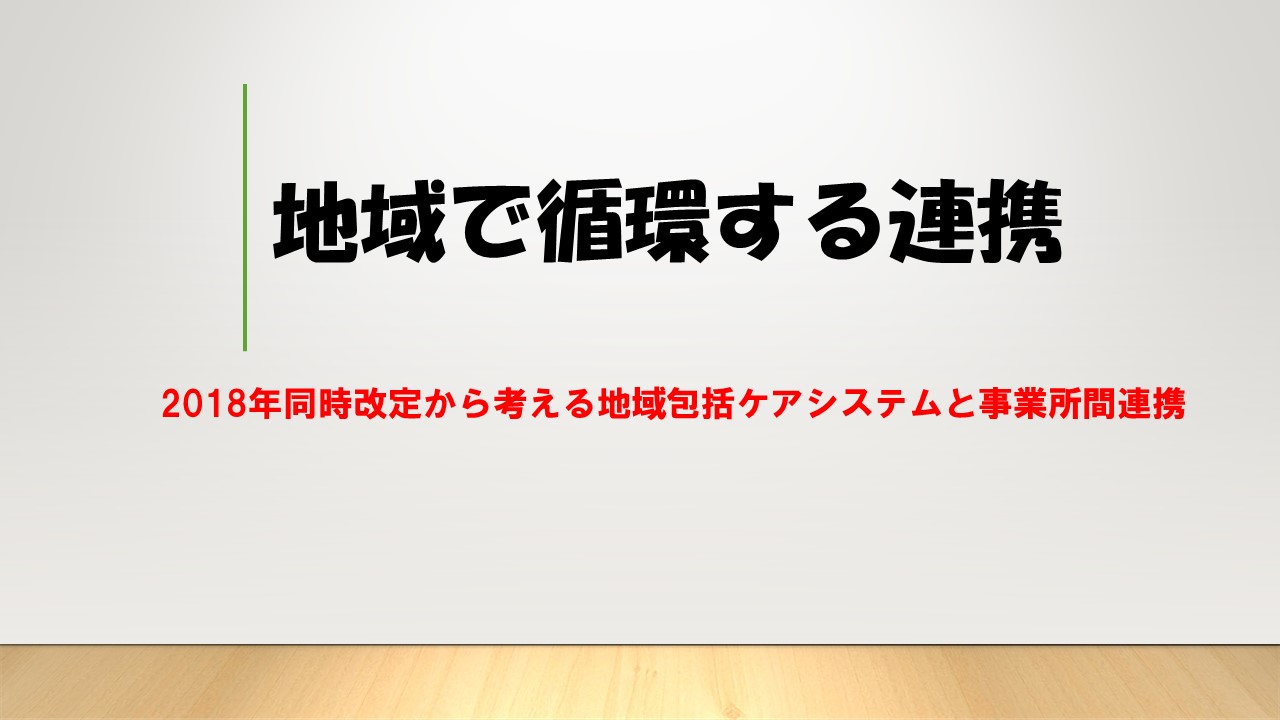 note
note 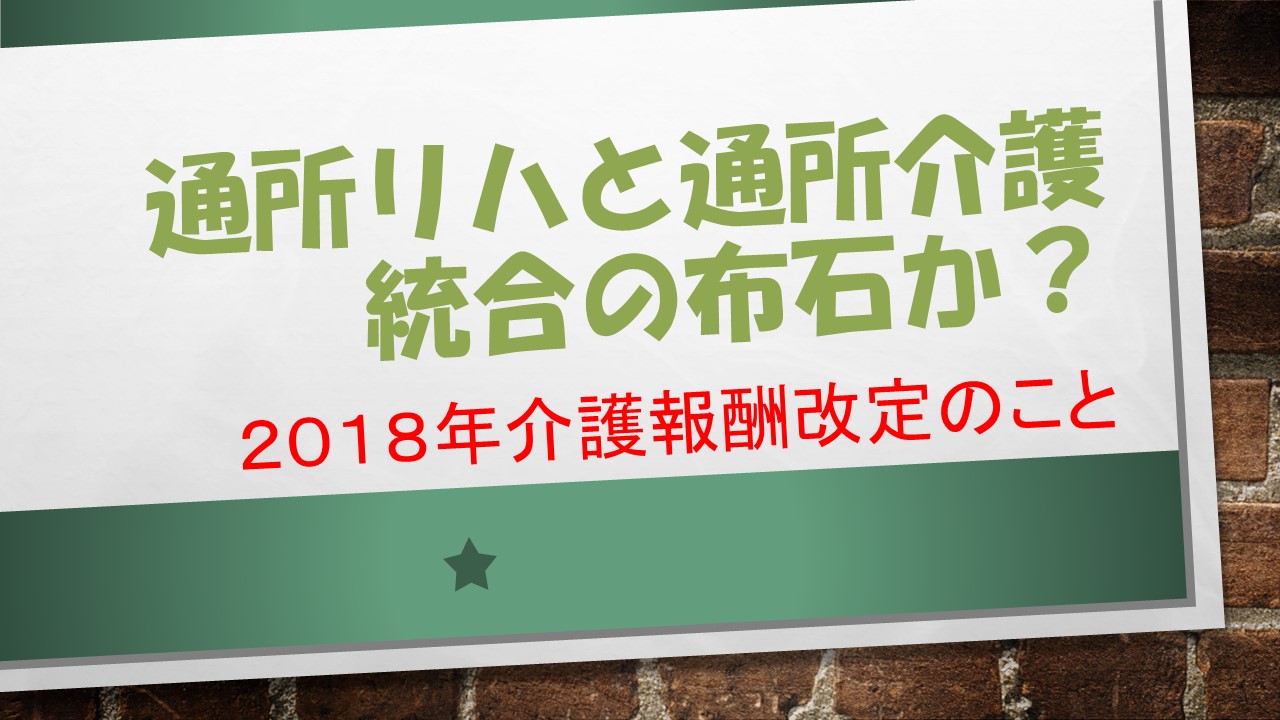 note
note 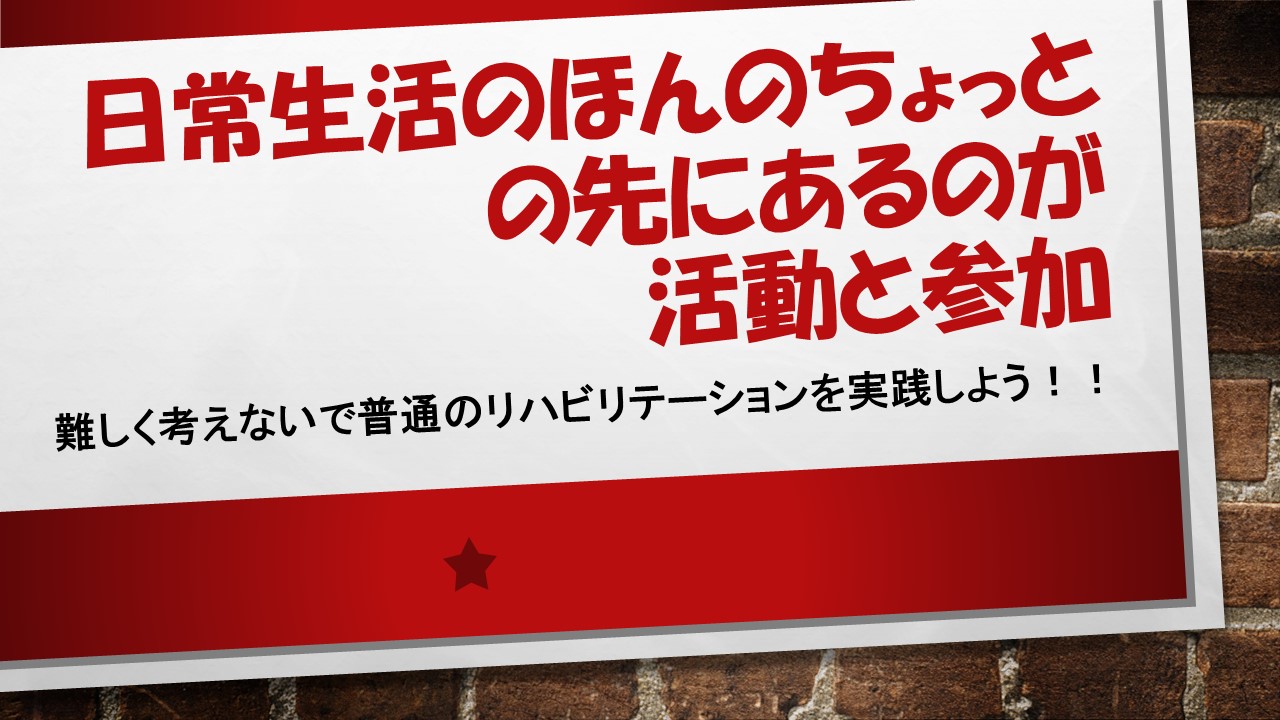 note
note 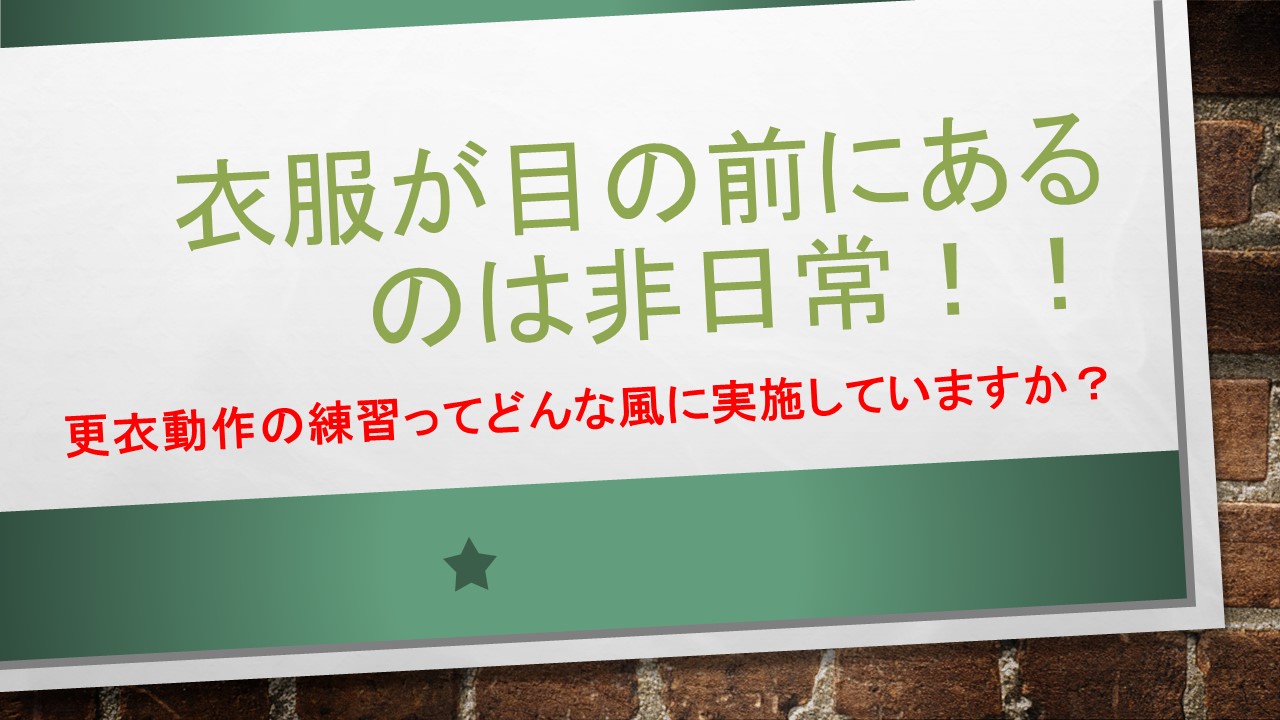 note
note 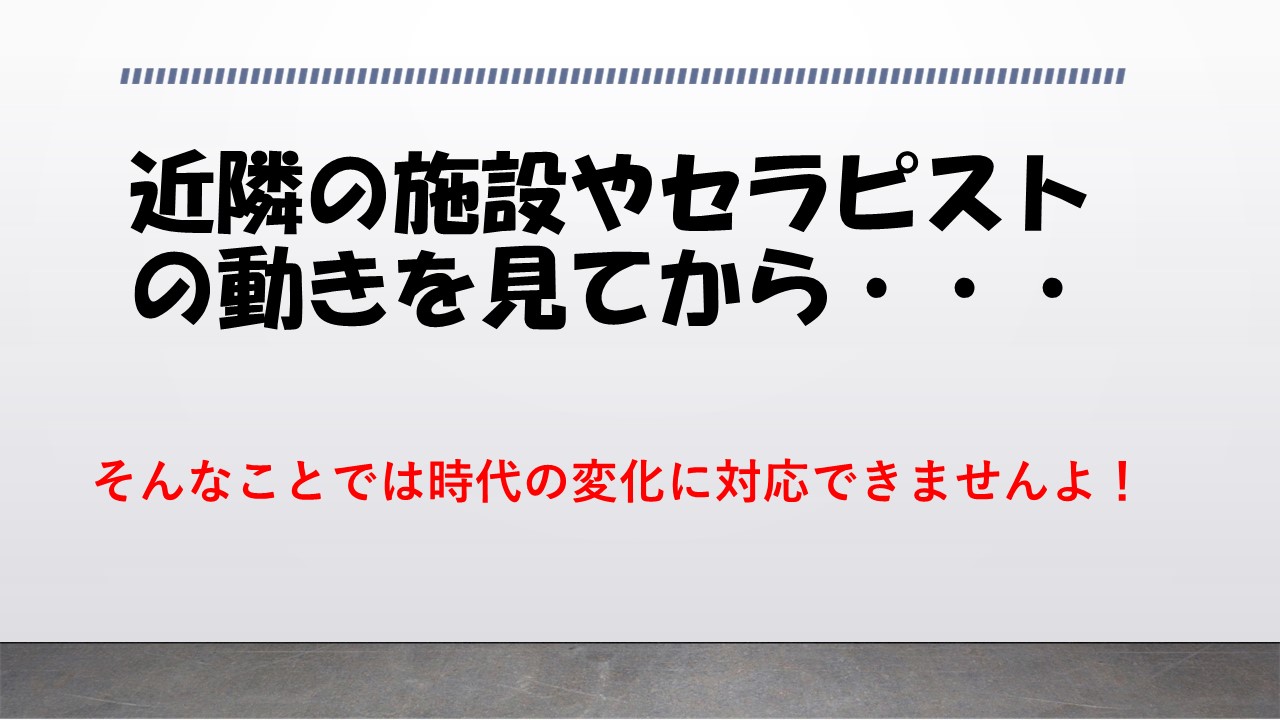 note
note 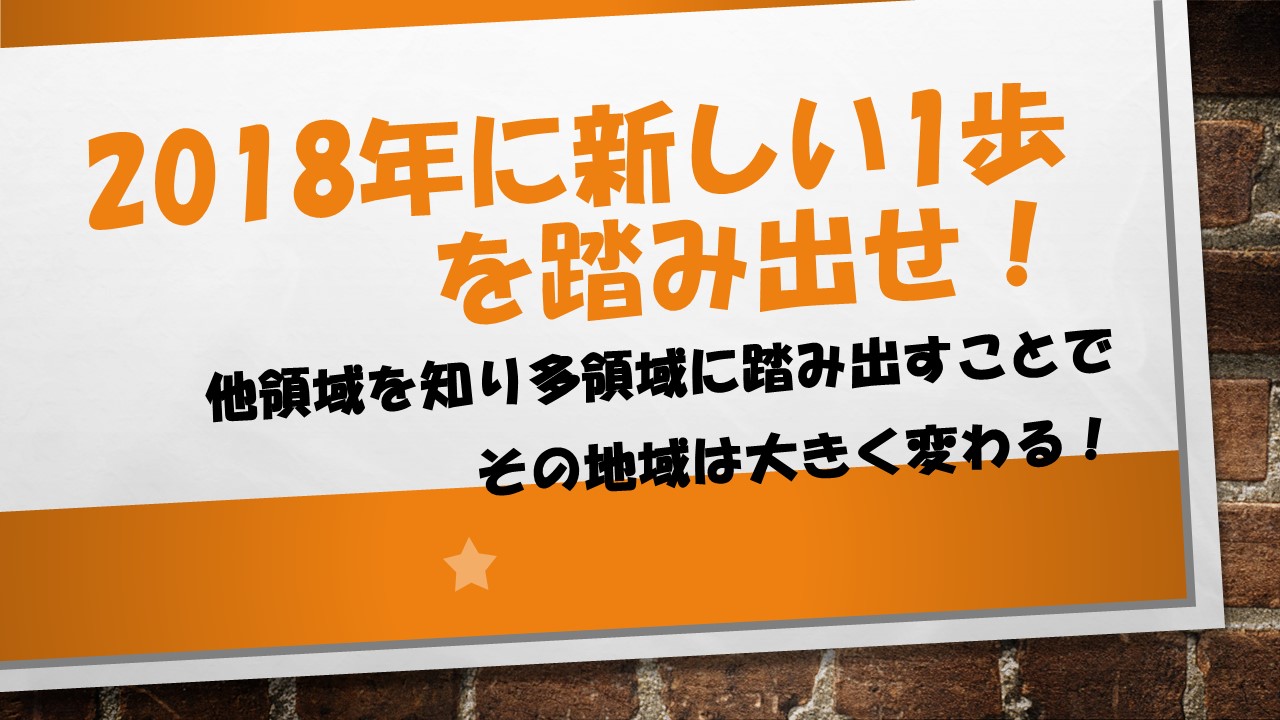 note
note 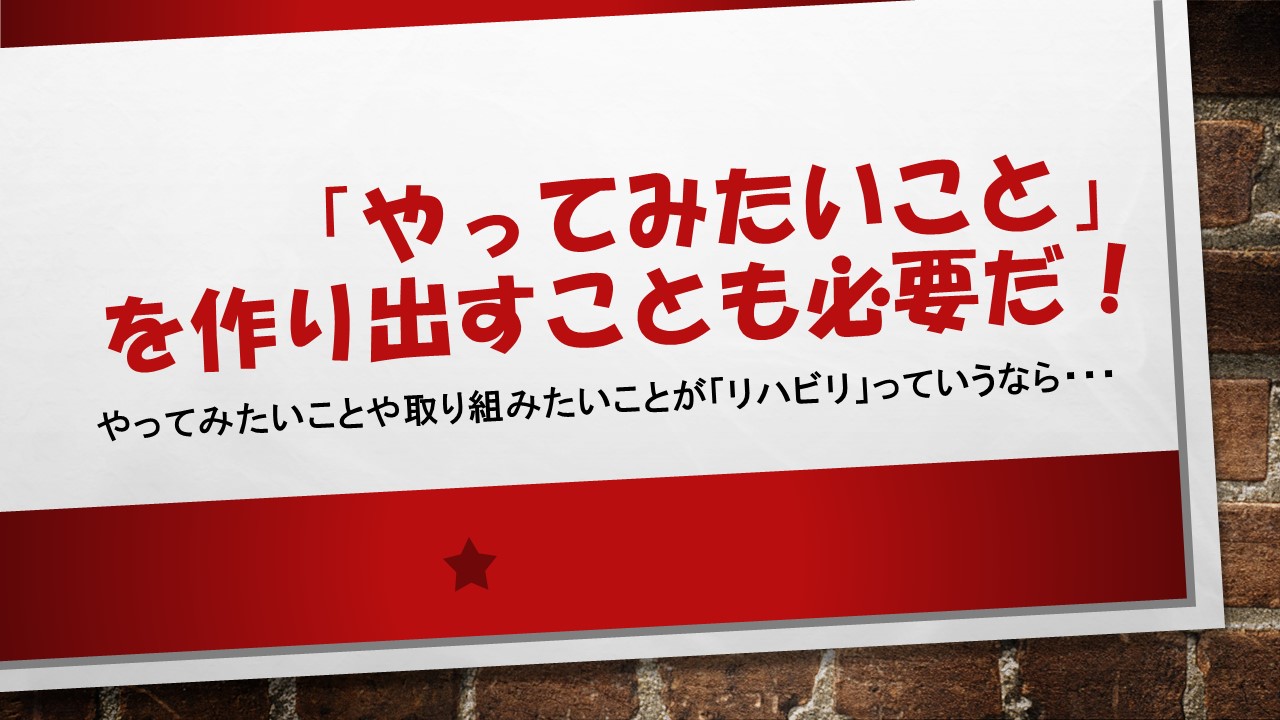 note
note 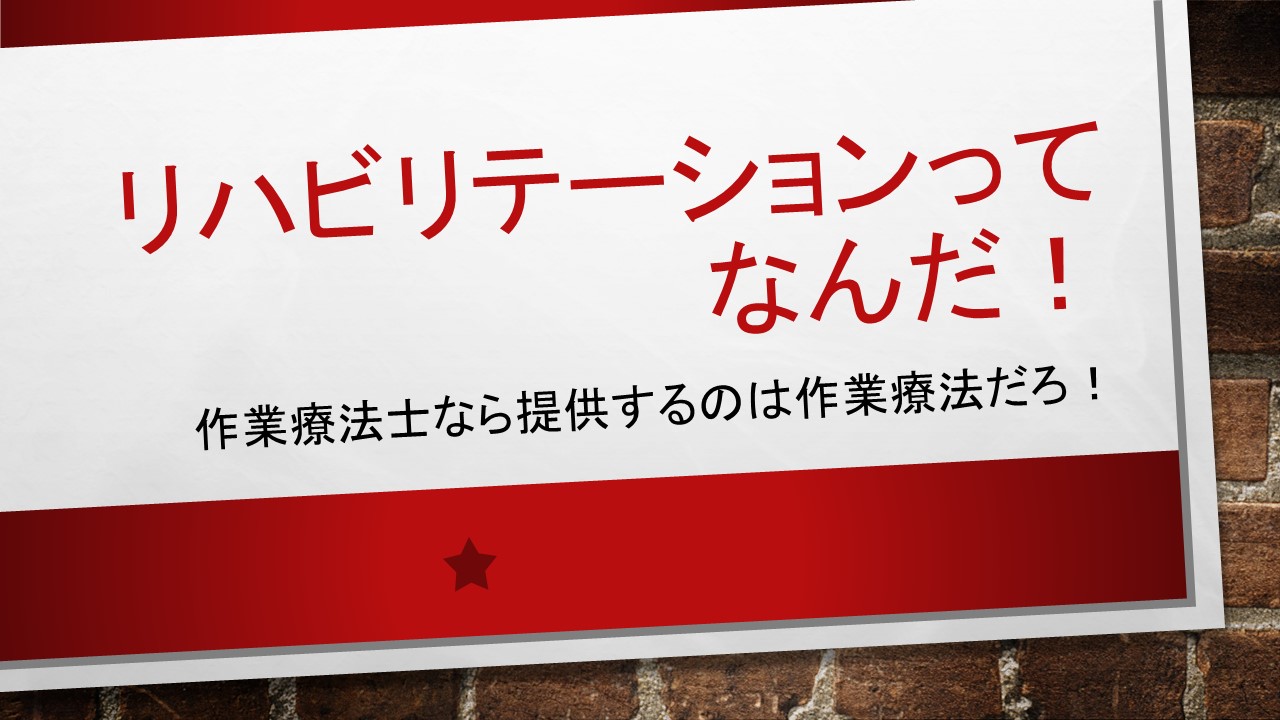 note
note 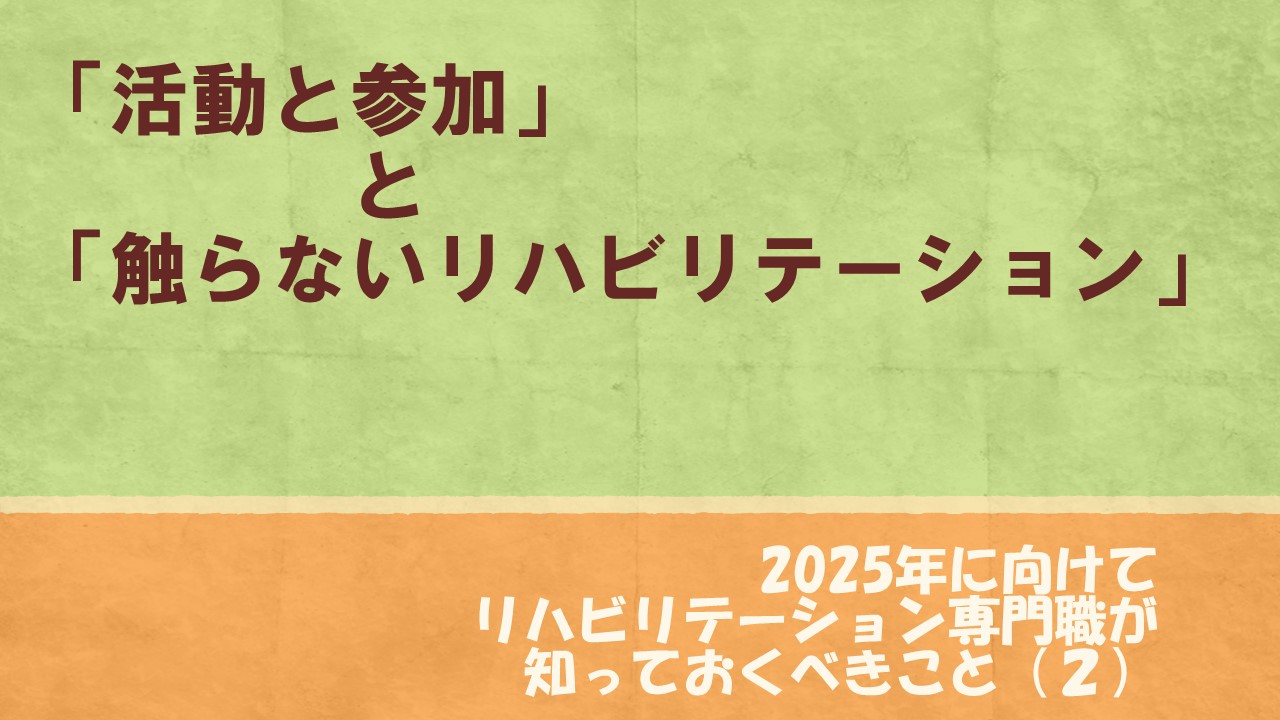 note
note 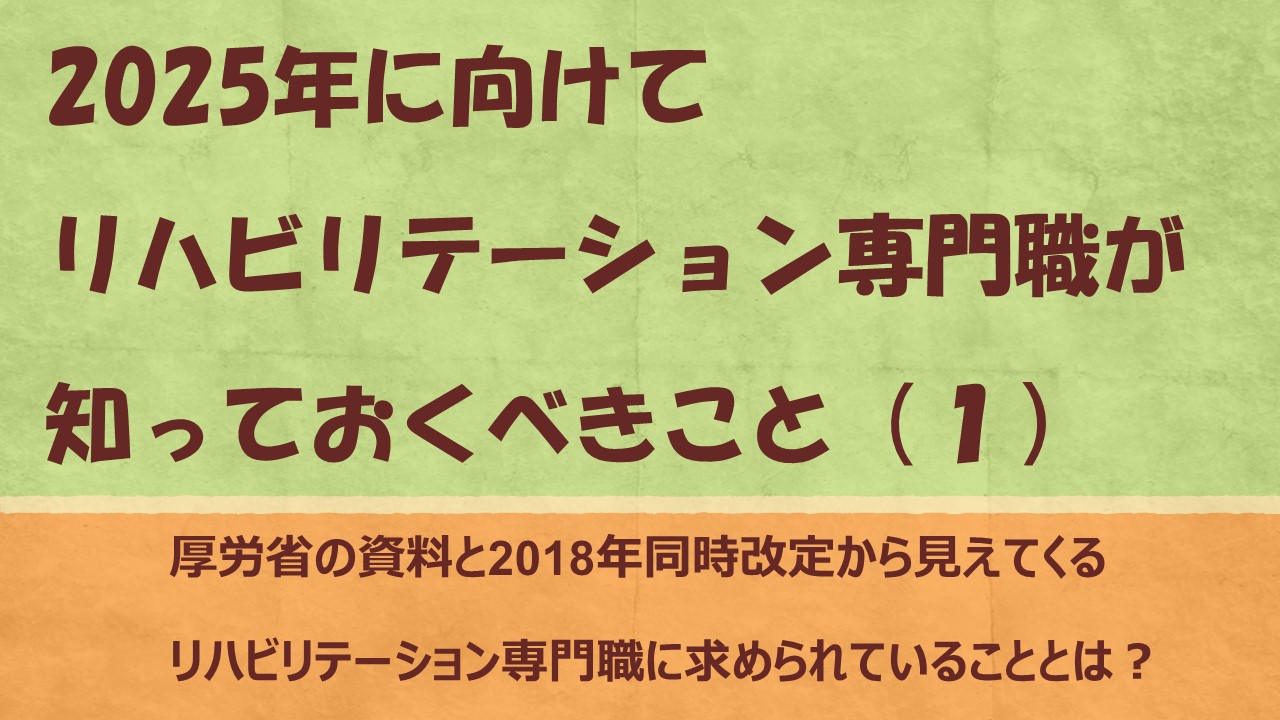 note
note  note
note 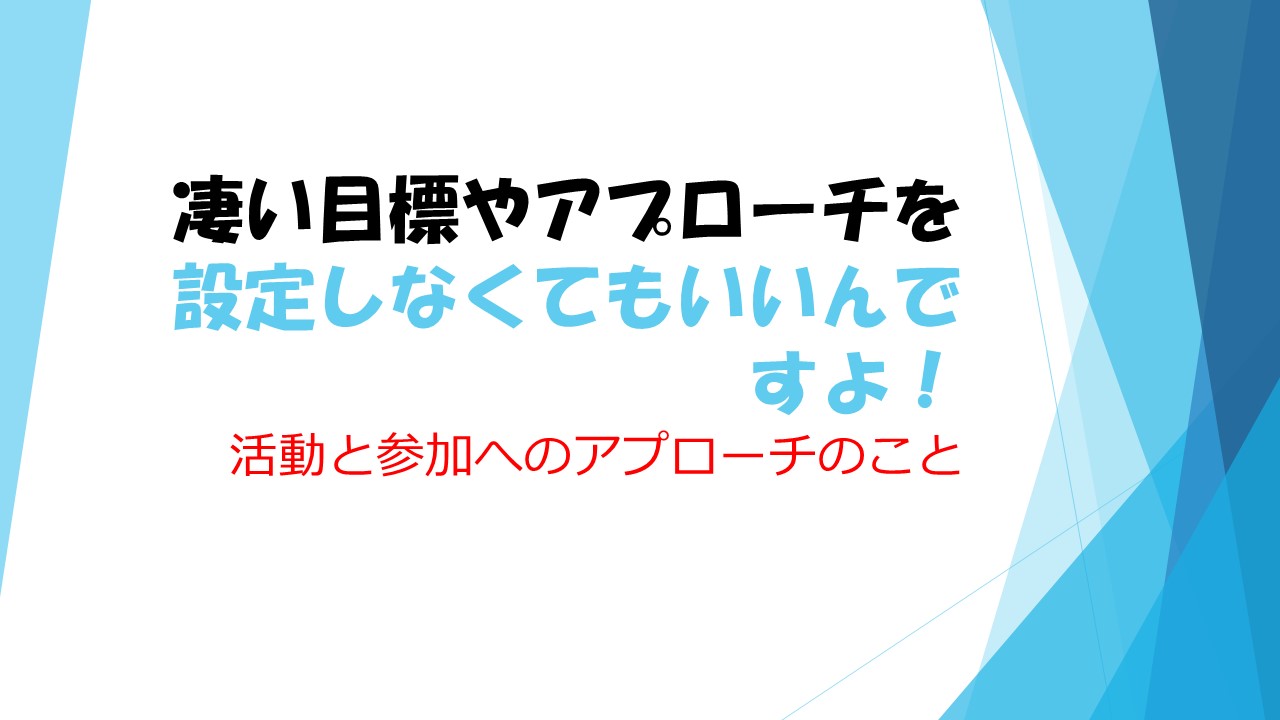 note
note 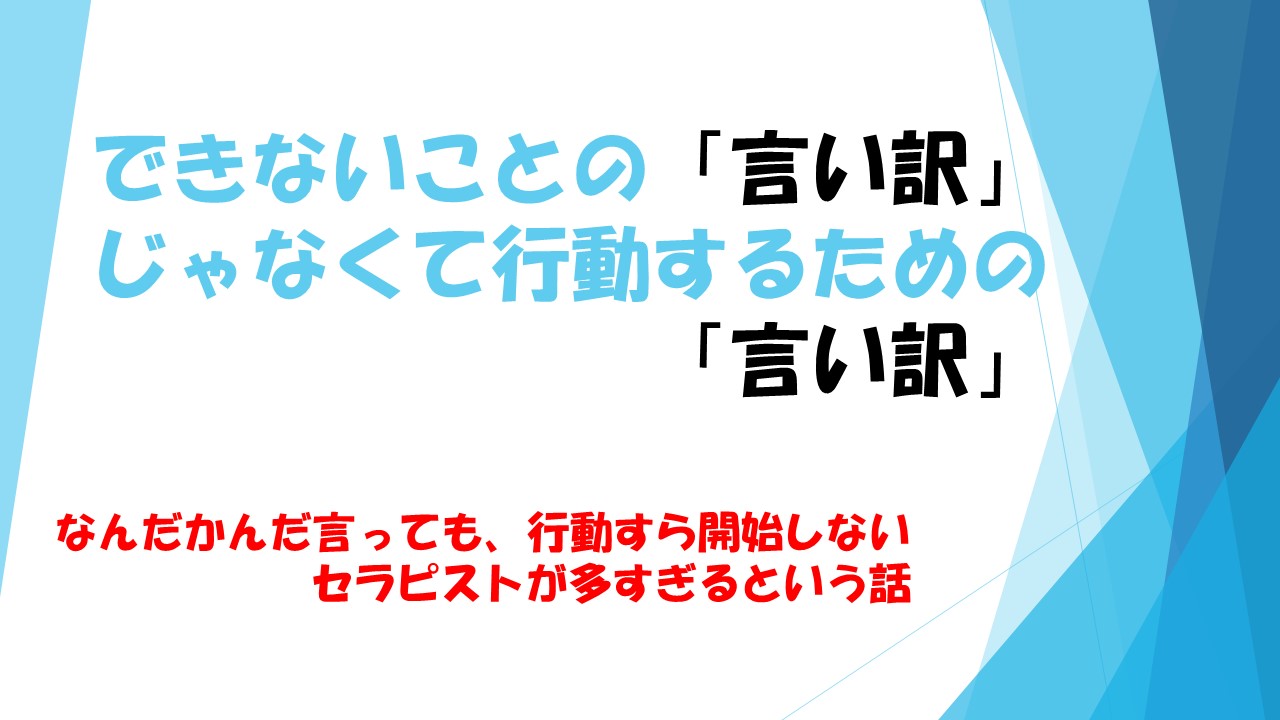 note
note  note
note 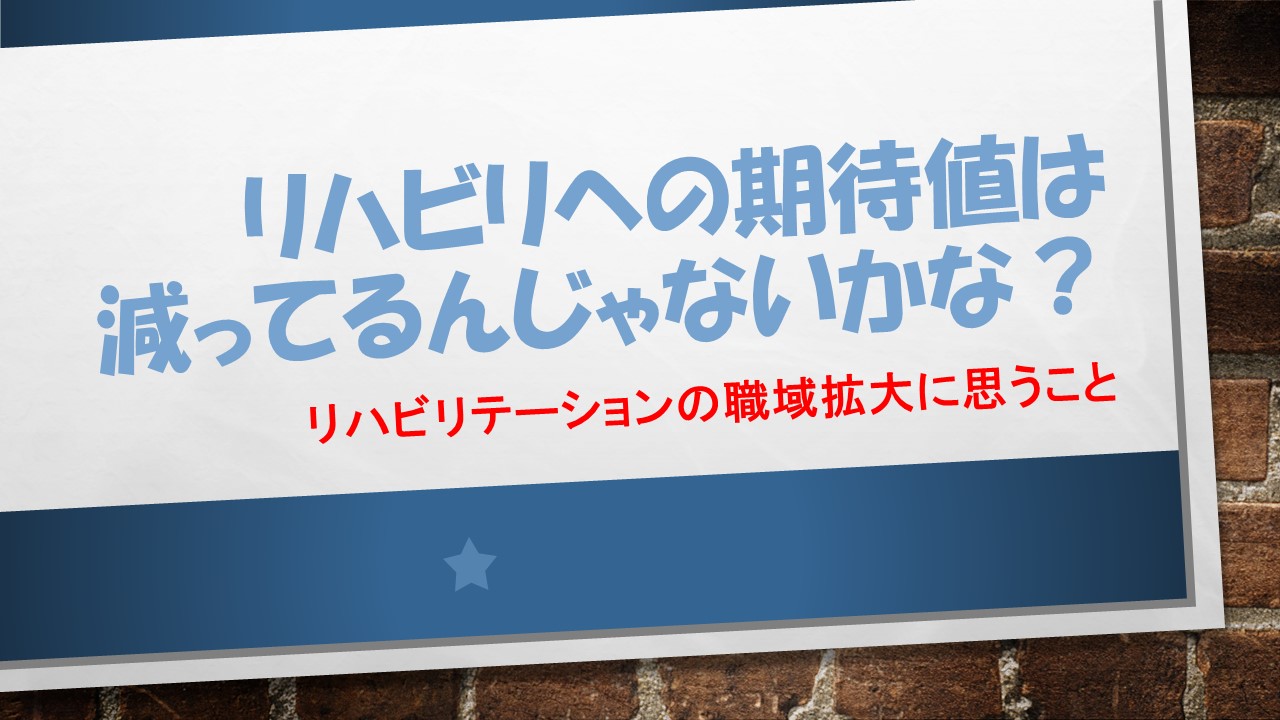 note
note