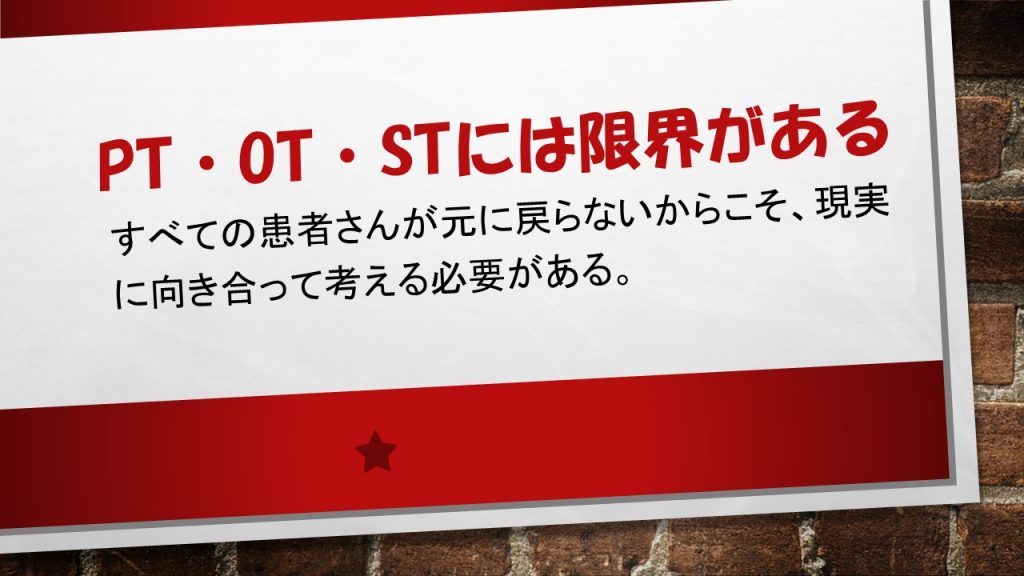
2018年1月と2月に講演した、千葉や金沢での研修会の感想が届いた。おおむね好評であるが気になる意見も書いてあった。
「地域でのリハビリテーションの実践には際限がないのでしょうか」
というような感じの意見。
[ad#ad6]
ずっと継続してやっていればいいとは思わない
- ケアマネに言われるがまま訪問を続けている
- 卒業を考えたことはない
- 付き合いの長い利用者さんを卒業させられない
そう言った意見はあちこちで聞く。
私もそう言ったケースを何人か抱えています。
だけどそれが正しいと思わないから、3年くらい前から新規の利用者さんに対しては卒業を意識して、本人や家族に利用期間の目安位について伝えている。
ケアマネさんにも目標の設定について具体的に伝えるし、ケアマネさんのプランの目標についても話を聞くようにしている。
だってね、
- リハビリすれば元通りになるわけではない
- 診療報酬も介護報酬も税金
ということを考慮すると、リハビリテーションはずっと継続するサービスではないと考えるからです。
通所リハや訪問リハだけでなく、病院のリハビリテーションも無駄と判断されれば返戻されるわけです。
だからそのこと考えないといけないなってことをnoteサイトに書いてみました。
⇒リハビリテーションの限界とサービスの適正運用
こんなお話をリアルに聞いてみたい方はこちらからどうぞ
⇒⇒講演依頼のこと
もっといろんなことを学びたい方は、ぜひお読みください
⇒やまだリハビリテーション研究所が全力でお届けする「新しい学びの形」
気に入ったらフォローしてください
やまだリハビリテーション研究所の公式LINEアカウント
フォロワーさんは300人くらいです
![]()
ID検索の場合は
@yamada-ot.com
(@を含めて検索してね)
YouTubeで動画公開しています。
チャンネル登録者が100名を突破しました
やまだリハビリテーション研究所のYouTubeのチャンネル
新しい学びの形を提供します
フォロワーさんは300名くらいです!
⇒https://note.mu/yamada_ot/
Twitter
フォロワーさんは600名くらいです
⇒https://twitter.com/yamada_ot_labo
Facebookページ
フォロワーさんは2200名くらいです!
⇒https://www.facebook.com/yamada.reha.labo
【↓↓週末にゆっくり読んでみてください↓↓】
2019年版 病院リハと地域リハをつなぐ・変える

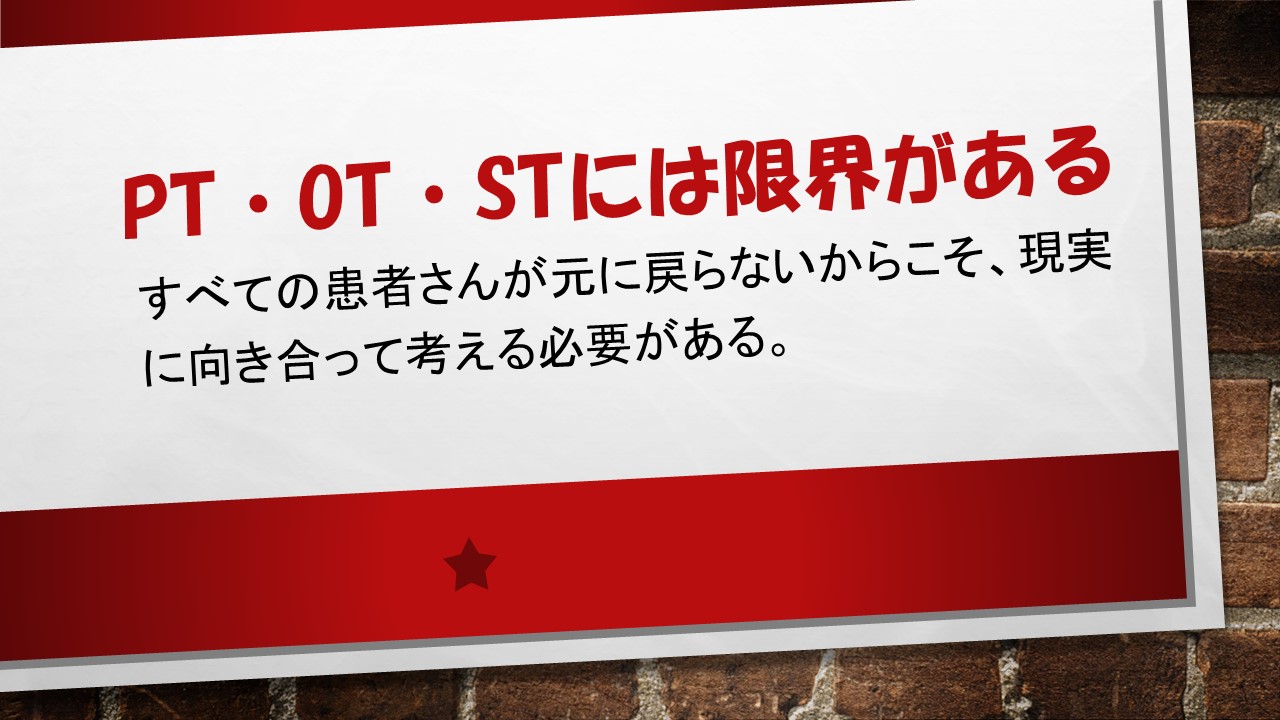
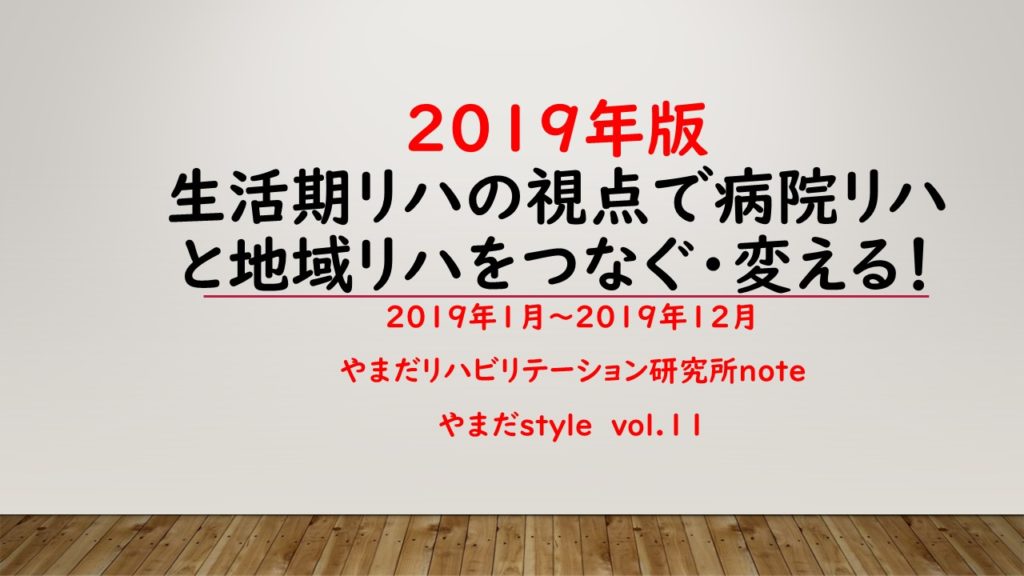


コメント