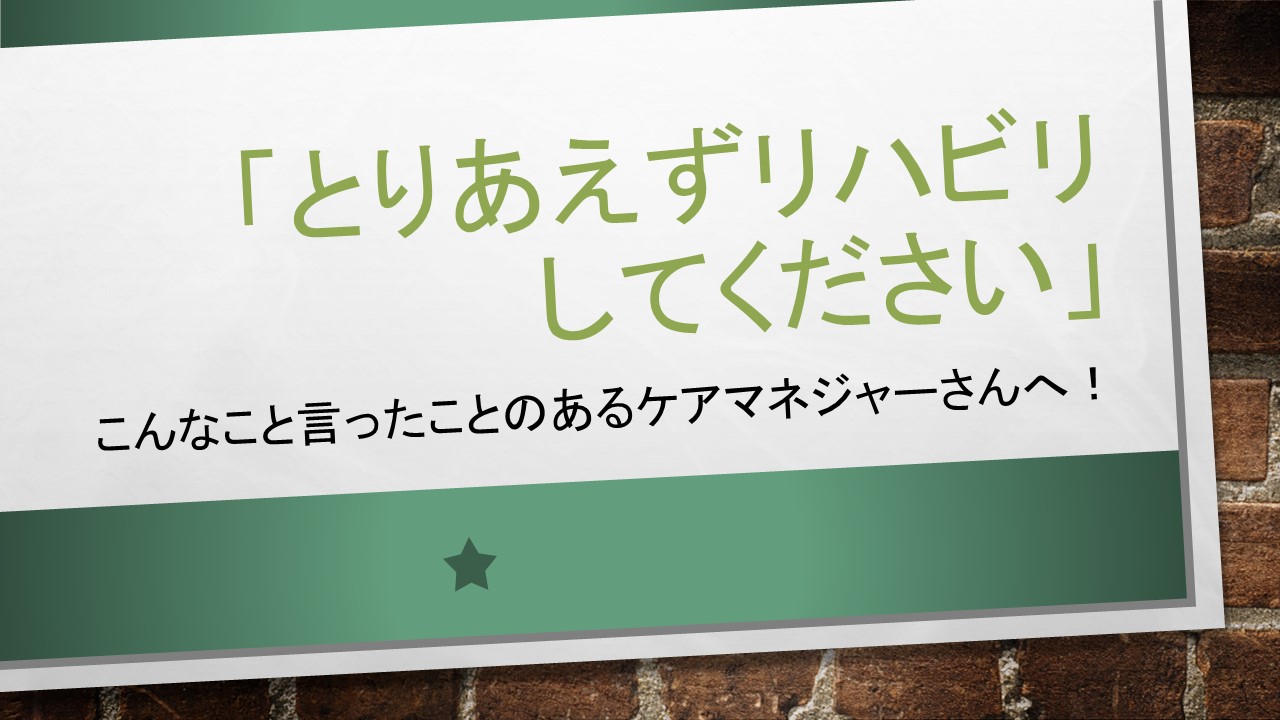 リハビリ
リハビリ とりあえずリハビリしてください!っておかしくないかな?
「とりあえず訪問リハビリ継続してください」って言われることがある。僕の提供しているサービスは「とりあえず」なんだろうか?
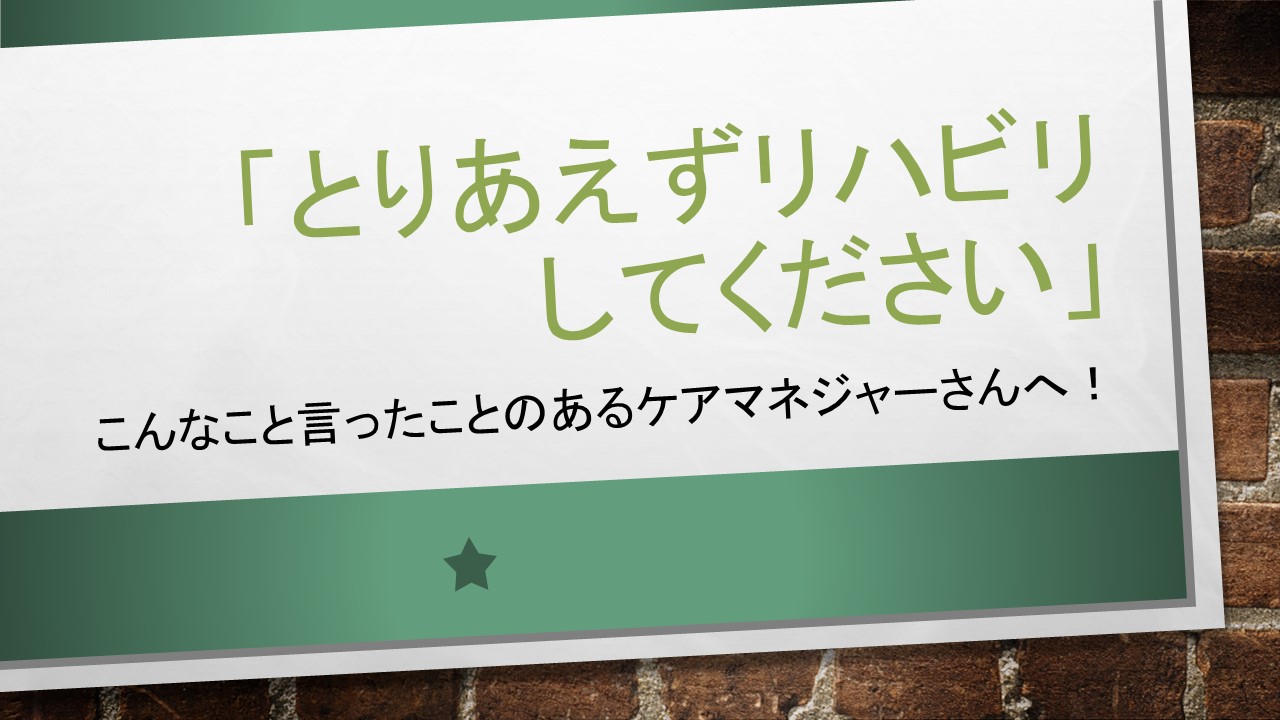 リハビリ
リハビリ 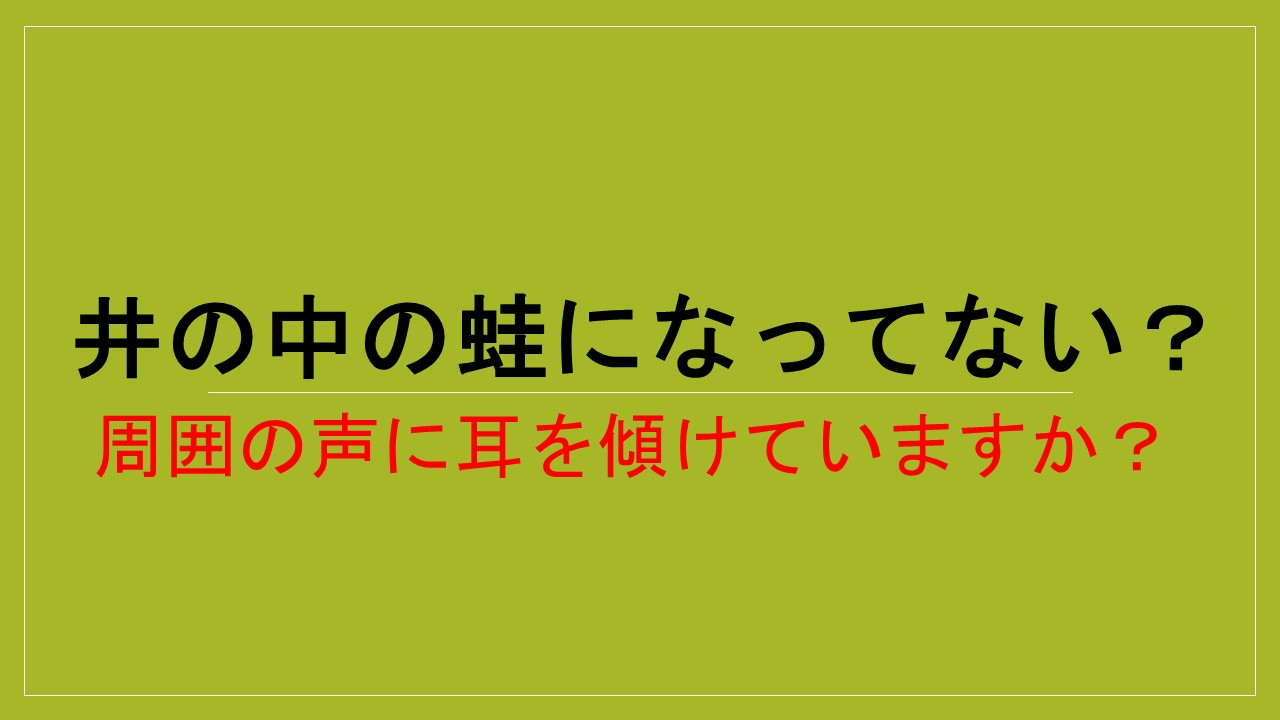 note
note 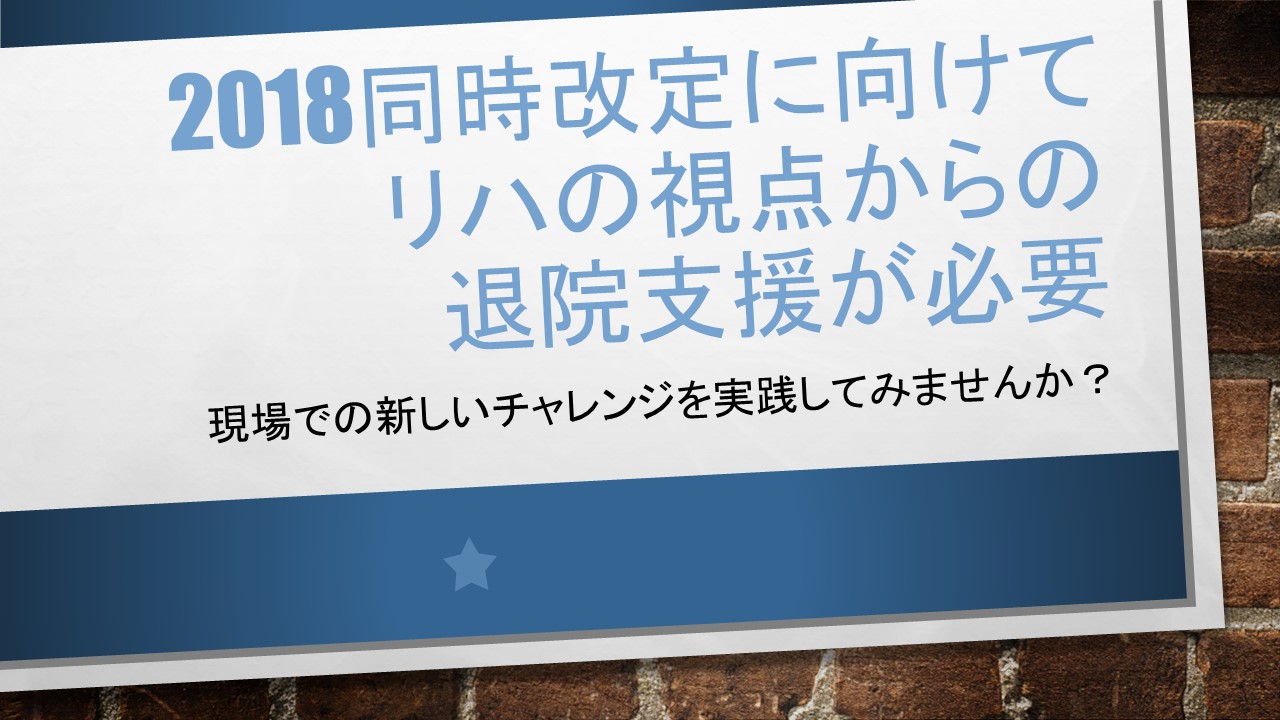 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 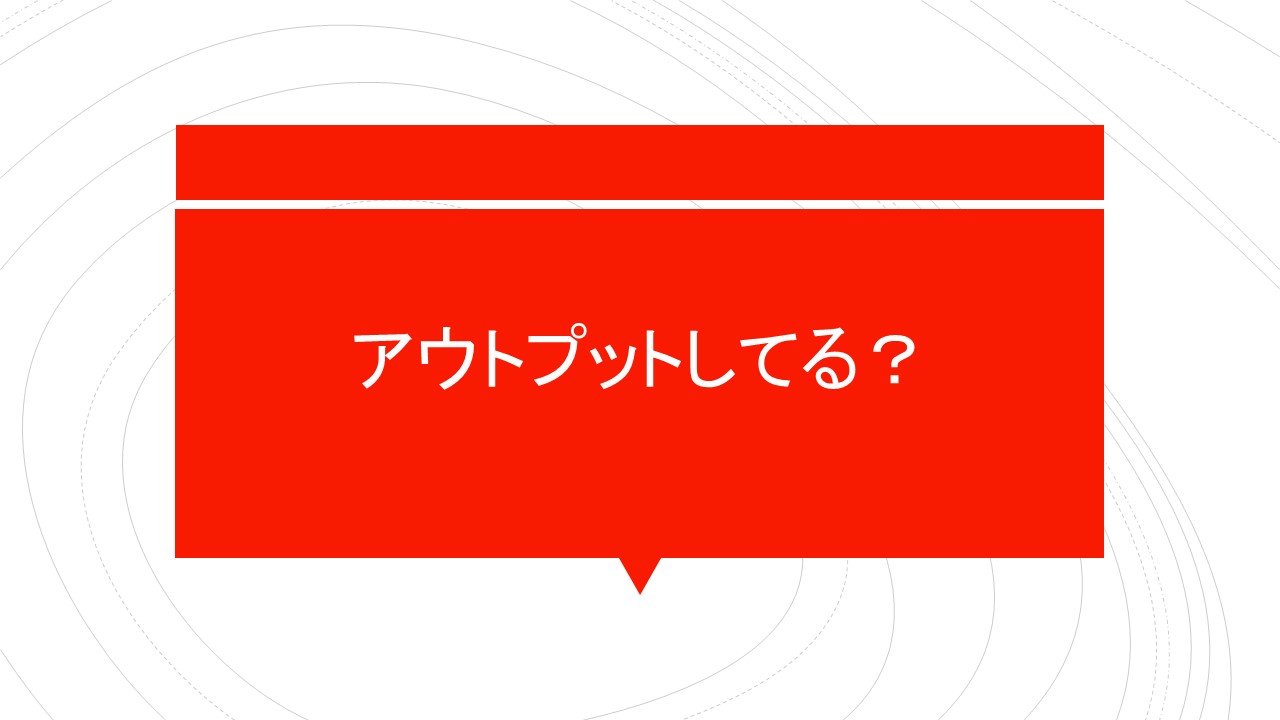 連携やチームアプローチ
連携やチームアプローチ  診療報酬・介護報酬改定
診療報酬・介護報酬改定  回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 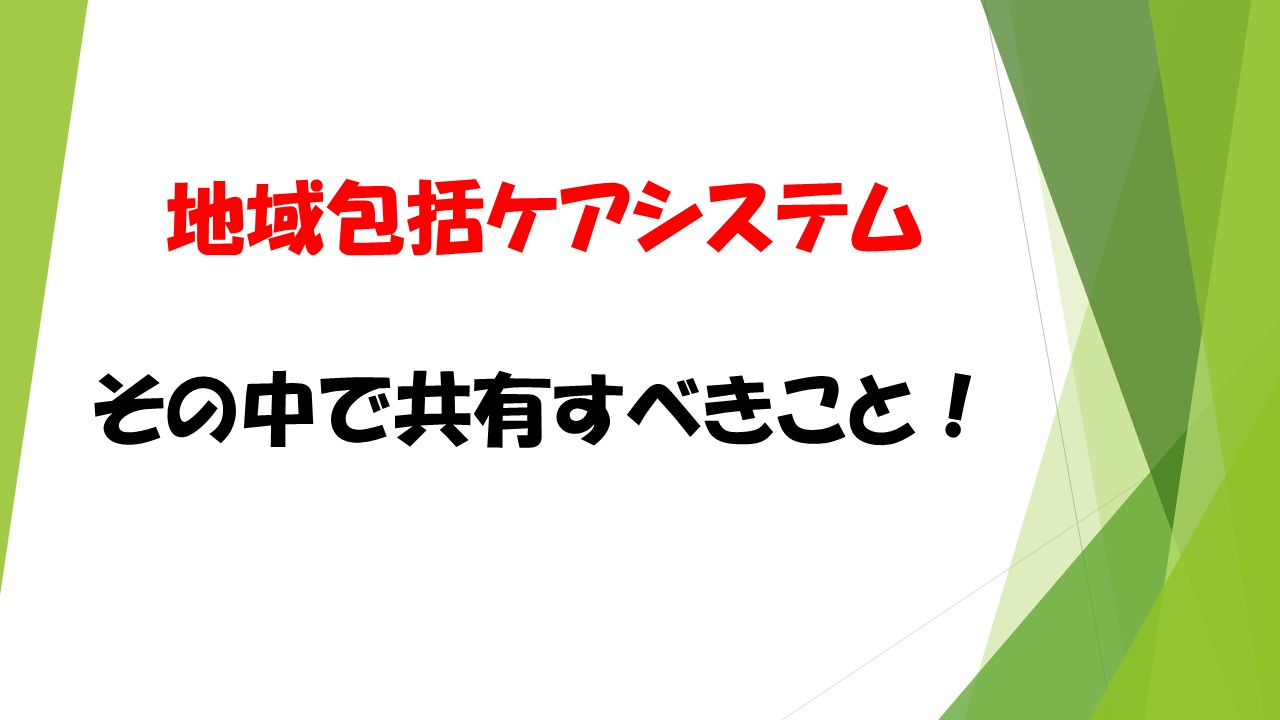 note
note 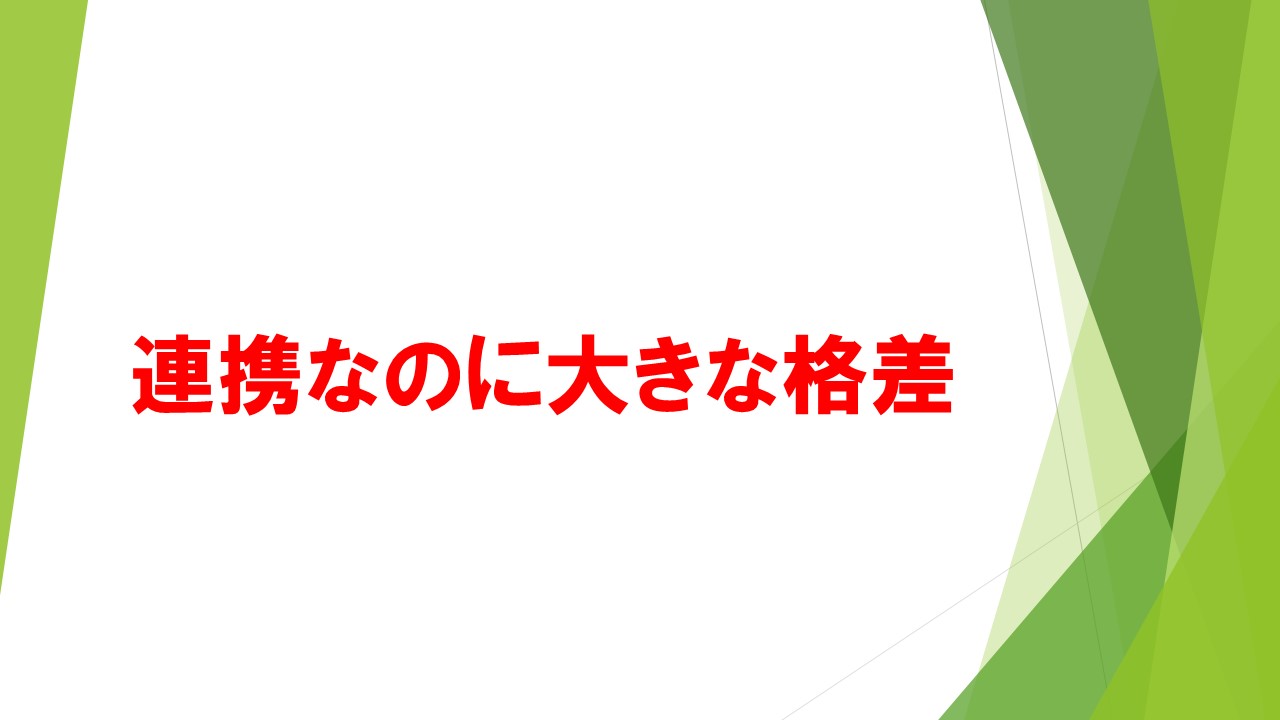 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 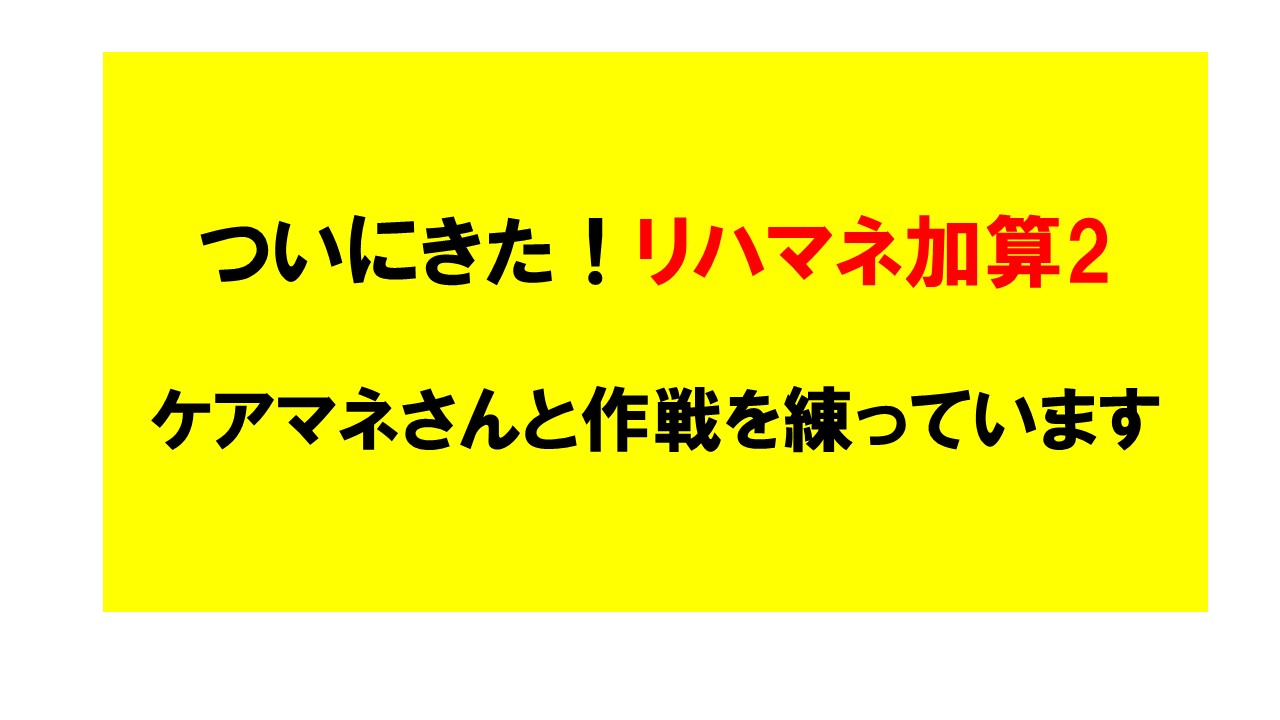 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 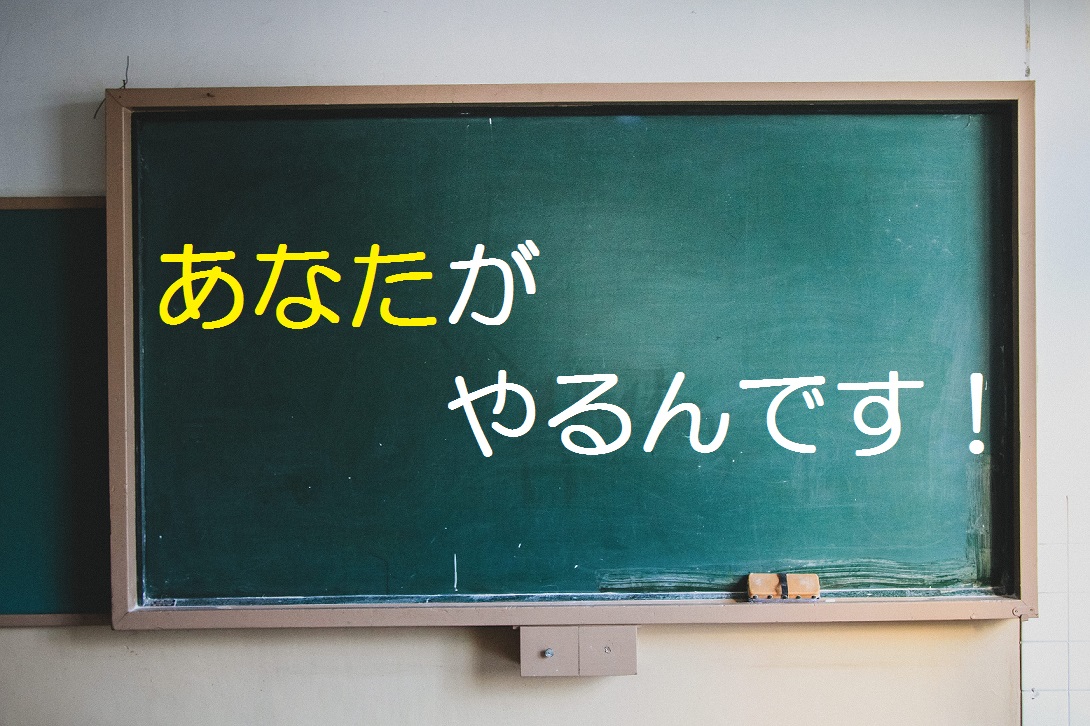 note
note  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 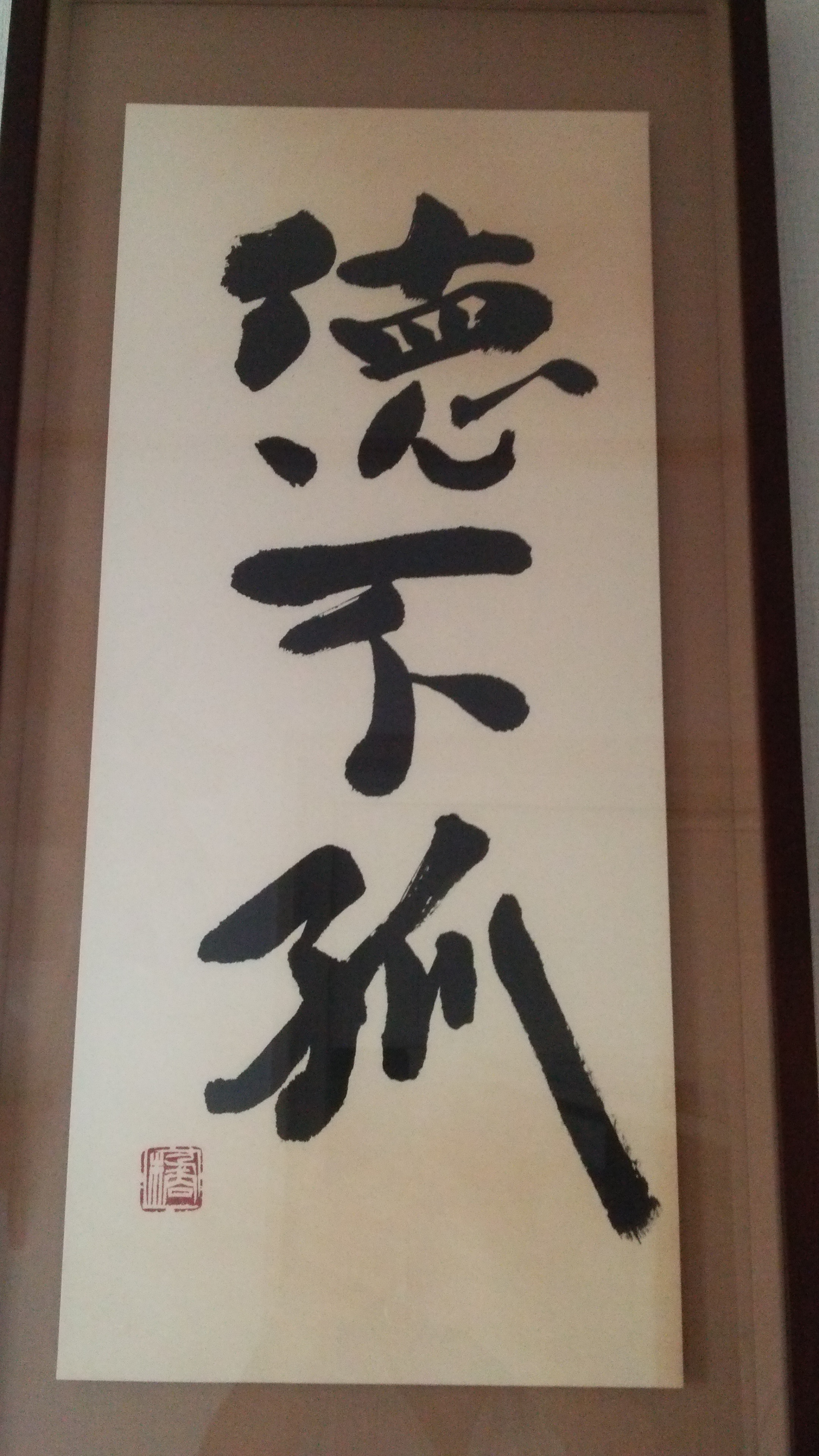 連携やチームアプローチ
連携やチームアプローチ 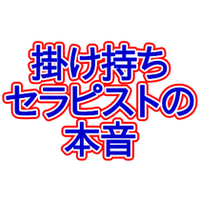 連携やチームアプローチ
連携やチームアプローチ  リハビリ
リハビリ  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 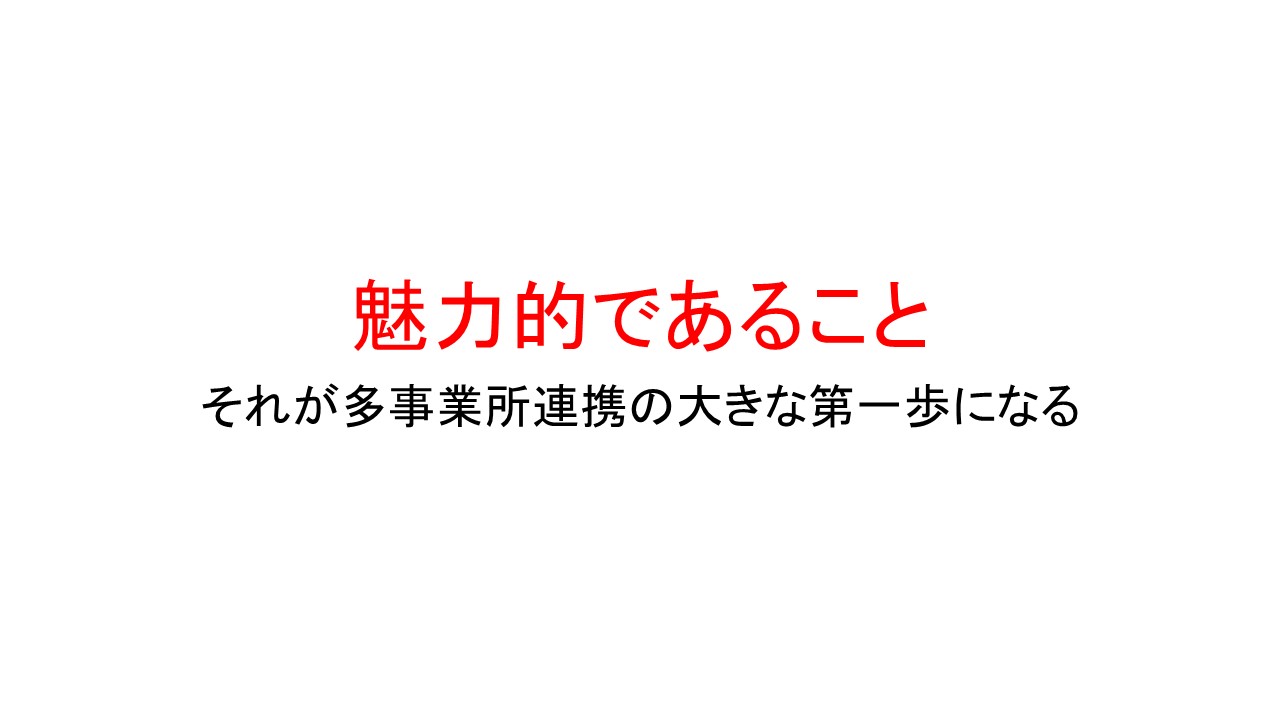 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション  子供のリハビリとか児童デイのこと
子供のリハビリとか児童デイのこと 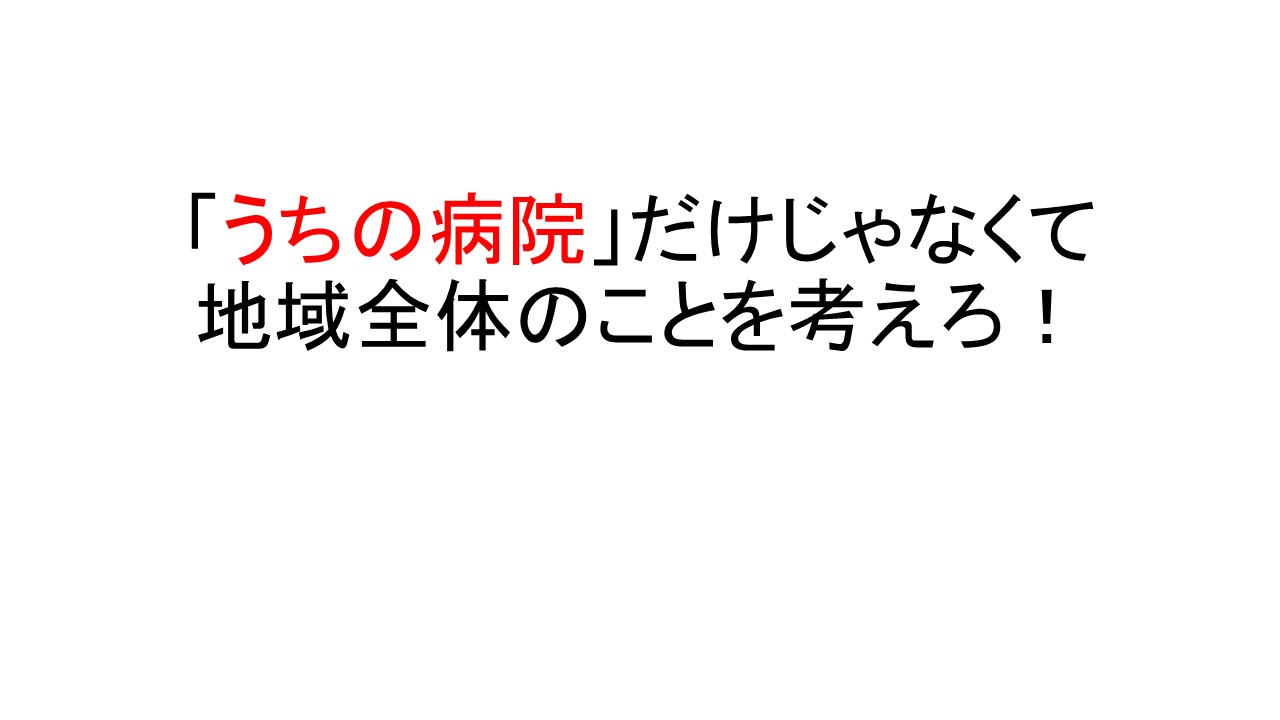 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション  地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 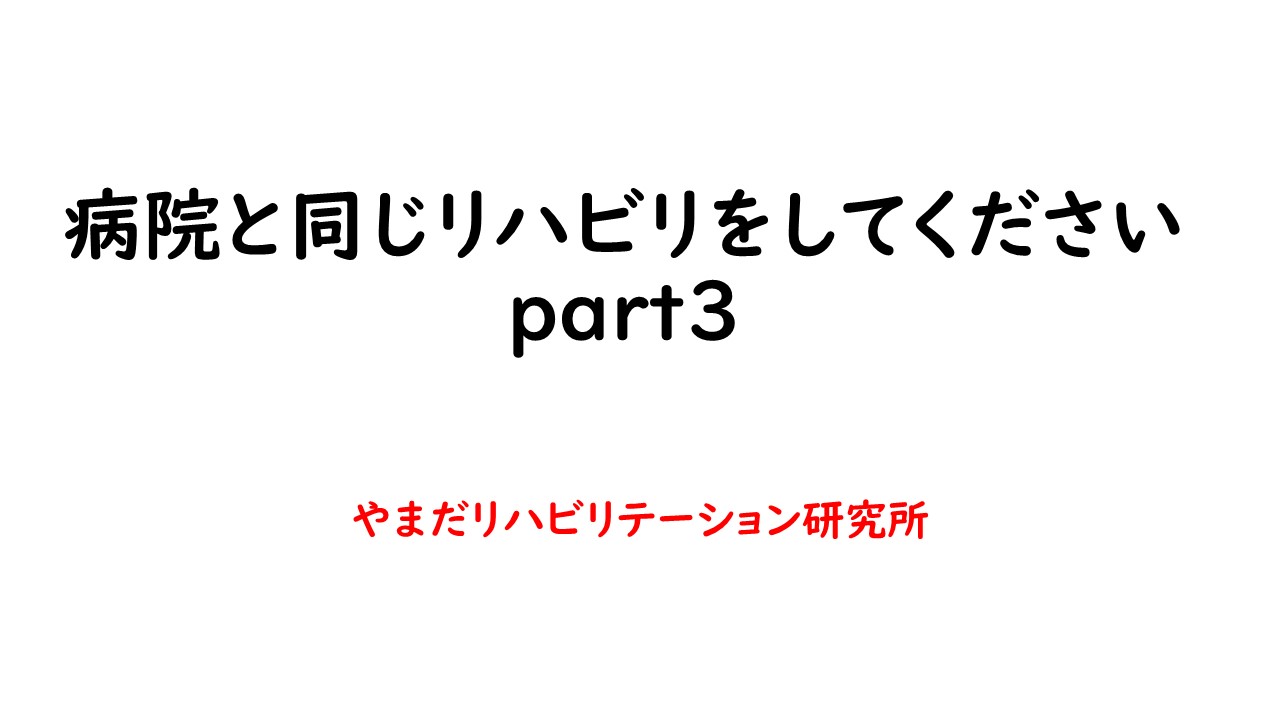 回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーション 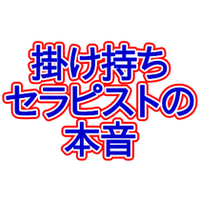 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション  連携やチームアプローチ
連携やチームアプローチ 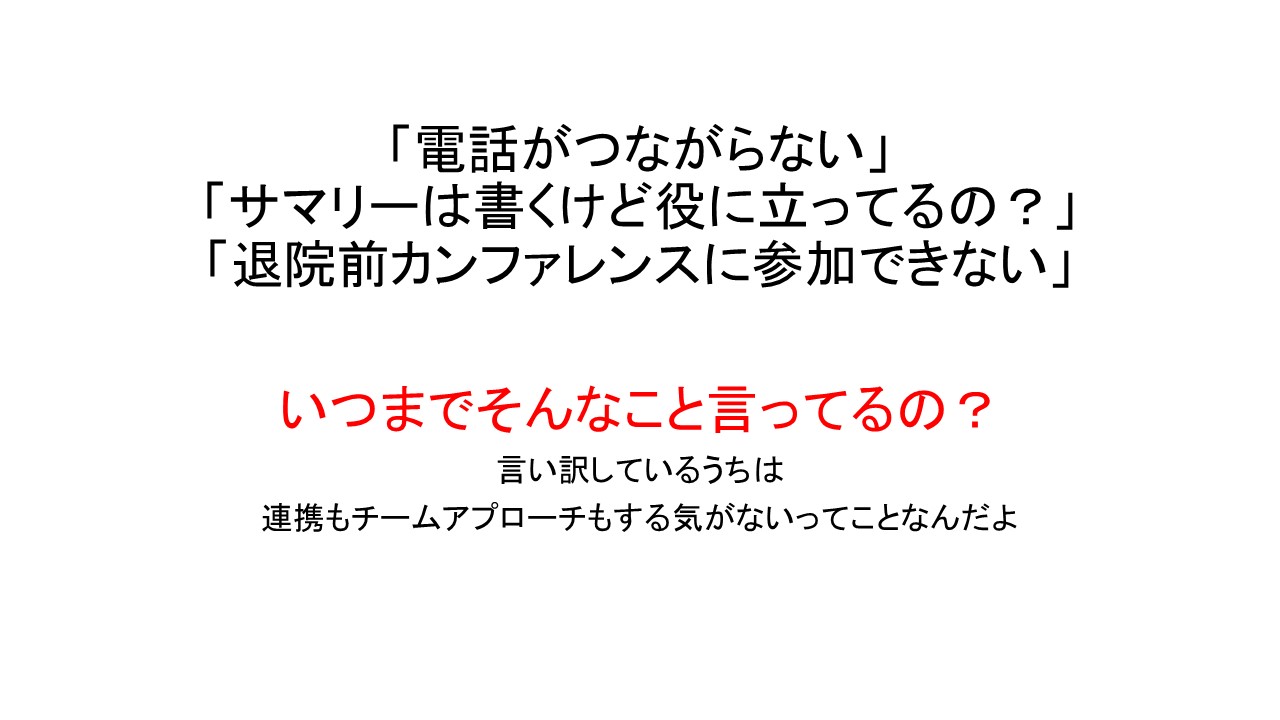 note
note  note
note 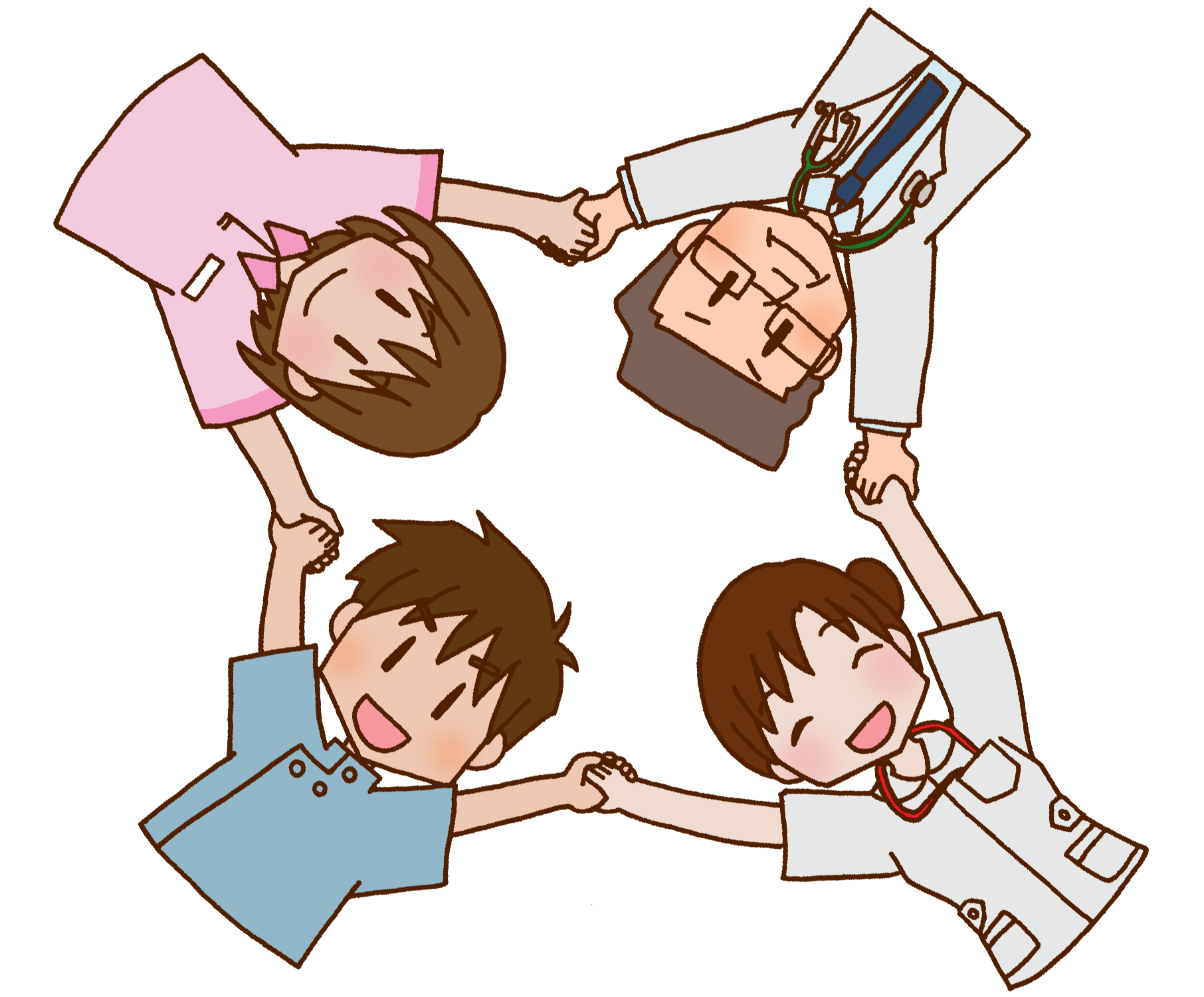 地域リハビリテーション
地域リハビリテーション 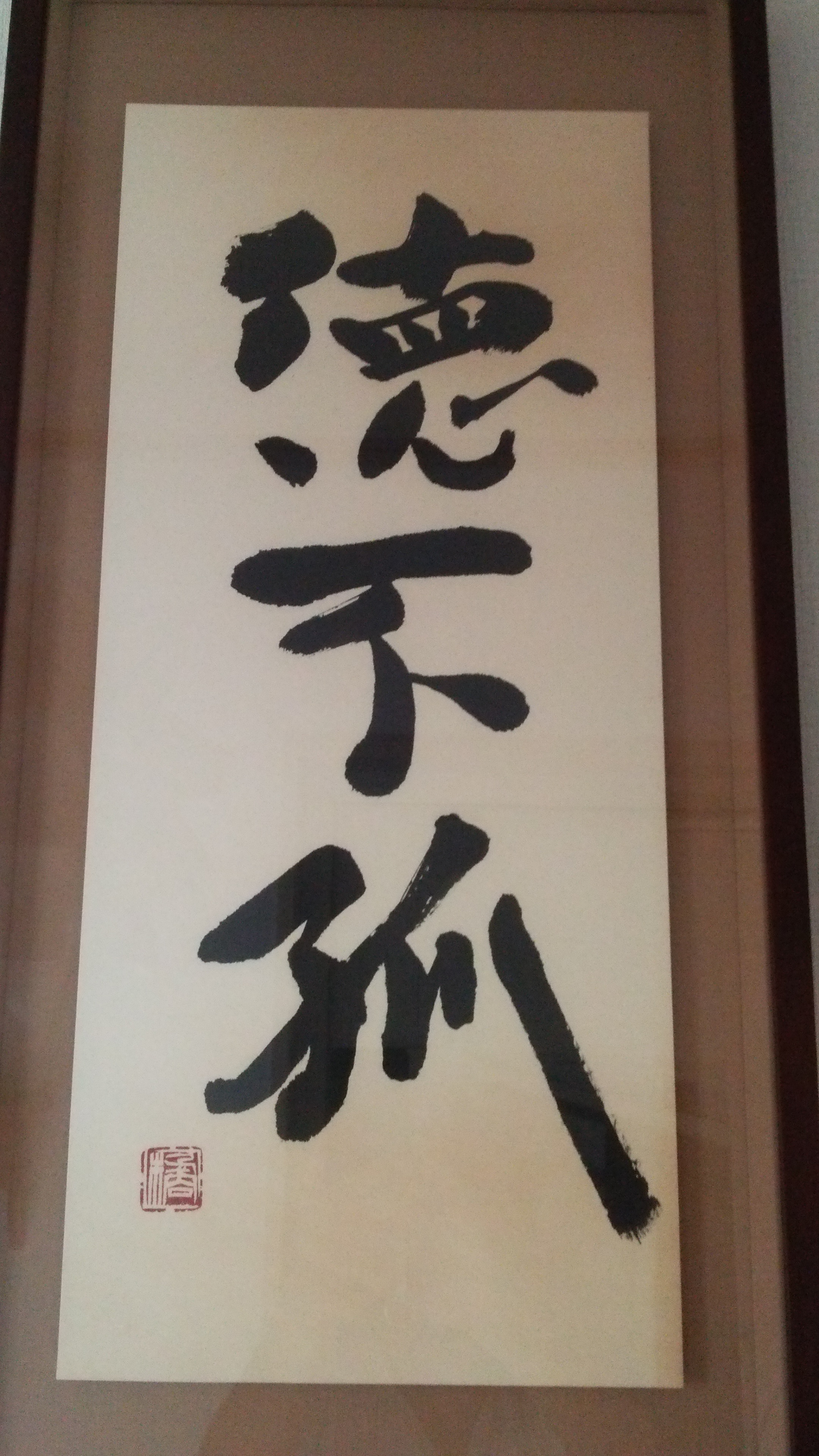 連携やチームアプローチ
連携やチームアプローチ