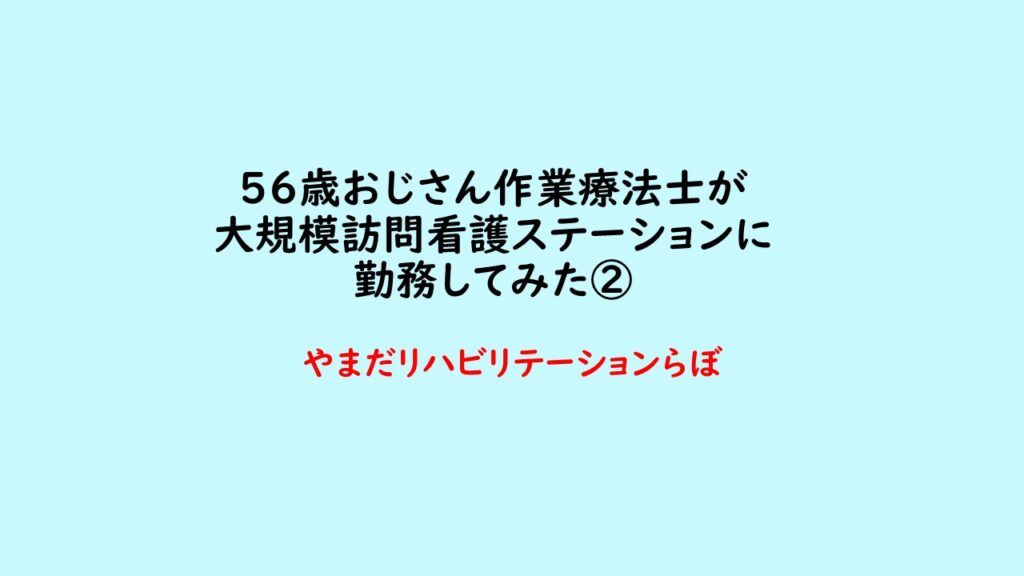
このコラムは56歳非常勤掛け持ち作業療法士が大規模訪問看護ステーションに勤務してみた①の続きです。
ご縁があり56歳で週1回勤務で非常勤として、約7か月間大規模訪問看護ステーションに勤務しながらいろいろ考えたことや実践してきたことを書いているコラムの第2弾です。育休スタッフの代行的な要員として勤務し、がっつり訪問していました。
50代で新しい職場に行くって事
これまでにも経験していることですが、56歳の私にとって非常勤の勤務、週1回の勤務とはいえ、自分自身ではやっぱりプレッシャーというものはあります。
- 事業所のトップでもある管理者(=経営者でもある)が引っ張ってきた。
- 臨床経験30年超の作業療法士
管理者さんがどれくらいのことを期待して私に声をかけてくれたのかはわかりませんが、臨床経験を積んでいる自分としては、やっぱり声をかけてくれた管理者さんに迷惑をかけることもできないし、臨床経験を積んでいる者としてやっぱり若いセラピストや看護師さんに自分の背中を見てほしいなとも思いますし、これまでの経験を少しでも伝えることが出来ればいいなとも思いながら勤務していました。
腰掛け気分で気軽に働いていたわけではないんですよね。
そうして、30代前後が中心と思われるリハスタッフの中において、やっぱり56歳の作業療法士は異質だと自分では考えていました。
前回のコラムでも書いたように、研修会で講師をしてからの勤務ということもあり、若いスタッフの皆さんは私に対して気を使ってくれているんだろうなという雰囲気も感じていたんですよね。
年齢のこと、そいう言った経緯のあることを踏まえながら、こちらからコミュニケーションをとるように心がけていました。
- 初めて使う種類の電子カルテのシステムだったので、使い方は遠慮せずに教えてもらう。
- 事業所のローカルルール的なことで分からないことは近くにいるスタッフに確認する
- スタッフが、ケースのことで話していたら聞き耳を立てて、おせっかいになりすぎない程度に困りごとの解決のアドバイスをする
- 良い取り組みや関わりをしていたら声をかけて褒める
訪問は基本的に1日7件くらい出ていましたので、
- 朝の出勤してから訪問までの時間
- 昼休み
- 最後の訪問終わりで事務所に戻ってからの時間
これらの時間を使ってとにかくいろいろ話していました。業務を黙々としているスタッフに無理やり必要のないことを話しかけたり、プライベートな会話を積極的にするって言うんじゃないですよ。業務の中で必要な事柄をいろいろ話していました。
基本は訪問業務で皆さん外に出るわけですし、もちろん昼休みに事務所に戻らないスタッフもいますし、非常勤スタッフさんで半日勤務の方もいますので、会うことのできるスタッフさんには限界はあるわけですが、なるべく時間を有効活用するように心がけていました。
同じ利用者さんを複数名で担当している場合は、なるべく私の訪問時の状況を伝えたり、他のスタッフさんに訪問時の状況を伺ったりすることも意識していました。
50代という年齢を自分でも意識しているので、周りから煙たがられないようにすることも必要だなってことも頭の片隅に置きながら、必要なコミュニケーションについては積極的にとるということを基本としていました。
7か月程度の勤務期間でしたので、自分の経験や考え方をどれくらい伝えることが出来たのかって部分ではまだまだだとは思いますが、50代の作業療法士の働き方の片鱗くらいは見せることが出来たんじゃないのかなと思っています。
管理者さんからは「やっぱり普通のセラピストとは違いますね」というお言葉をいただきました。
看護師さんとの連携のこと
看護師さんは基本的にはチーム制でした。
訪問エリア別に看護師さん全体を2チームに編成し、利用者さんを担当するというスタイルでした。朝には申し送りを兼ねたミーティングもされていました。
どこのステーションでもそうだと思いますが、リハスタッフは個別で担当することが多いですが、看護師さんは基本的にはチームで担当することが多いですよね。1人の利用者さんに対して複数の看護師さんが関わっています。だから、私が担当している利用者さんにも、複数の看護師さんが関わっています。
これまで勤務経験のある訪問看護ステーションは多くても常勤非常勤合わせて10名以内のところだったんですよね。だから、どの看護師さんもその事業所の利用者さんをたいてい知っているんですよね。でも大規模ステーションともなると利用者さんの数があまりにも多いので、すべての利用者さんの状態をなんとなく知っておくって言うのは難しいんだと思います。だから訪問エリア別にチーム制をとるというのは妥当な方法だなと思いました。
私は週1回金曜日の勤務なので、出勤日に私が担当している利用者さんのことを知っている看護師さんがその時間に事務所にいなくても、チームの看護師さんに伝えておけばその情報は共有されていました。報告書や計画書担当の看護師さんを中心に報告したりしていましたが、必ずしも会えるとは限らないですからね。
チームの看護師さんに伝えておけばきちんと伝わっていました。
何故チームの看護師さんにきちんと情報が共有されているのかということが分かったのでしょう?
私の担当している利用者さん、訪問時にちょっと不調なことが続いていたんですよね。だから訪問するたびに数週間にわたって看護師さんにその状況を伝えていました。伝えていた看護師さんは毎回異なっています。ある日、前回のコラムでも書いたように朝に出勤して、自分の担当ケースの1週間分の記録の確認をしていると、看護師さんの訪問記録に
「訪問時にケアマネの来訪あり、最近のリハ時の不調の状況について、ケアマネさんにも伝えて情報を共有」
というような一文があったんですよね。
これを見て、チームに伝えていることがきちんと情報として共有されているんだなってことが分かったんですよね。
大規模ステーションでスタッフの人数が多いからこそ、お互いの情報共有は大変だし、難しいと思います。
実際にこのステーションでも情報の共有の難しさを感じているスタッフさんたちはたくさんいました。でも、伝え方の工夫やこまめに話す機会を確保することで、きちんと情報は共有できるんですよね。
連携についての研修会においても、「週1回とか半日勤務のスタッフとの情報共有が難しい」という話はよく聞きます。だからこそ意識して情報を共有することが大切なんだと私は考えています。
大規模ステーションで人数が多いからといって、「誰かが気づいてくれているだろう」「一度言ったから大丈夫だろう」みたいな意識はアカンと思っています。
今回うまく情報共有できたケースについても、私的にはしつこいくらい毎週毎週情報を伝えていたんですよね。
チームのテーブルに近づいていくと看護師さんの方から「今日の○○さんのことですね・・・」言ってきてくれるようになるくらい、伝え続けていました。
情報を共有することの意味とか意義みたいなこと
訪問看護ステーションで、看護師さんとの情報共有の在り方について悩んでいるセラピストはけっこうたくさんいると思うのですが、
普段のコミュニケーションとして情報を共有する機会を意識的に作ることはめちゃくちゃ大切なんだと考えています。
連携についての研修会の講義の中で良く伝えているのは、以下のスライドのようなこと。
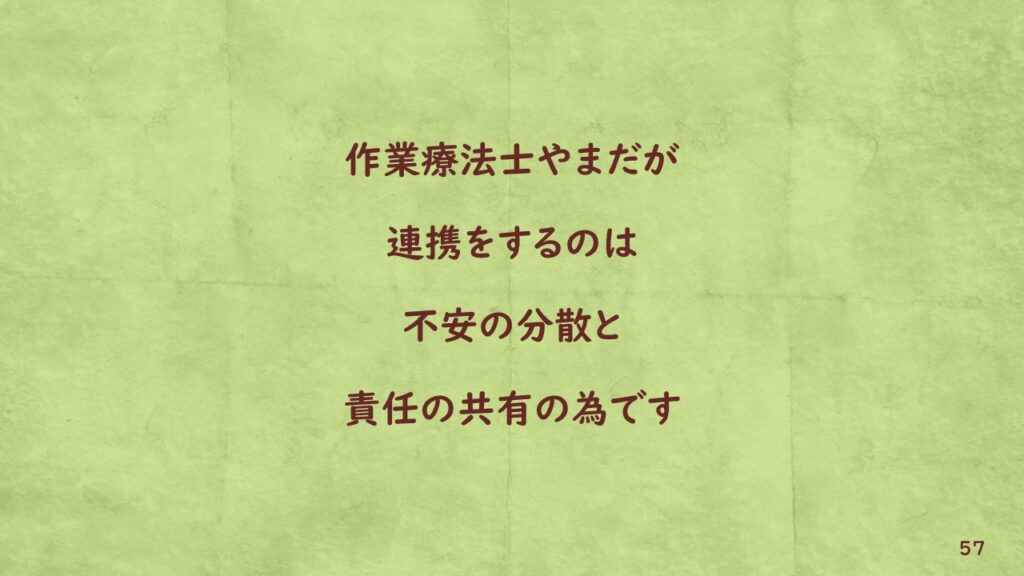
連携を私が積極的に進めるのは「不安の分散と責任の共有」なんですよね。
利用者さんについての出来事や情報、業務を進めるうえでの情報や出来事、それらについて悩んでいることや困っていることや不安なことについて「自分だけが知っていて大丈夫なのかな?」って一人で悩むくらいなら、情報を共有して自分の不安を少しでもほかのスタッフにも知ってもらって不安を分散させたい。他の人にも知っておいてもらうことで、多職種の視点で解決できるかもしれないし、自分の見落としていることに気づいてもらえるかもしれない。そうして、上司や先輩などに伝えることでその責任を自分一人で背負っているんじゃなくて、チームとして業務として対応しているんだという安心感を持てるようになるんですよね。
1人で訪問するからこそ、個別的な業務になりがちな訪問看護ステーションでの看護師さんやセラピストのお仕事だからこそ、情報共有を意図的に行うことで「不安の分散跡責任の共有」が出来るのだと考えながら、勤務先でのコミュニケーションを心掛けています。
今回のコラムはここまでです。
また続きは次のコラムに書きますね。
56歳非常勤掛け持ち作業療法士が大規模訪問看護ステーションに勤務してみた3
お問い合わせなど
ブログやSNSまとめ
- ブログ
このサイトです
やまだリハビリテーションらぼ - noteサイト
もう一つのブログサイトです
やまだリハビリテーション研究所のnote - Facebookページ
やまだリハビリテーション研究所Facebookページ - X(旧Twitter)
https://twitter.com/yamada_ot_labo - インスタグラム
https://www.instagram.com/yamada_ot_labo/?hl=ja - YouTube @yamada-ot-labo
やまだリハビリテーション研究所のYouTubeのチャンネル - やまだリハビリテーション研究所公式LINEアカウント

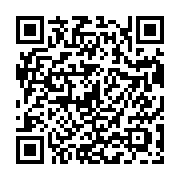

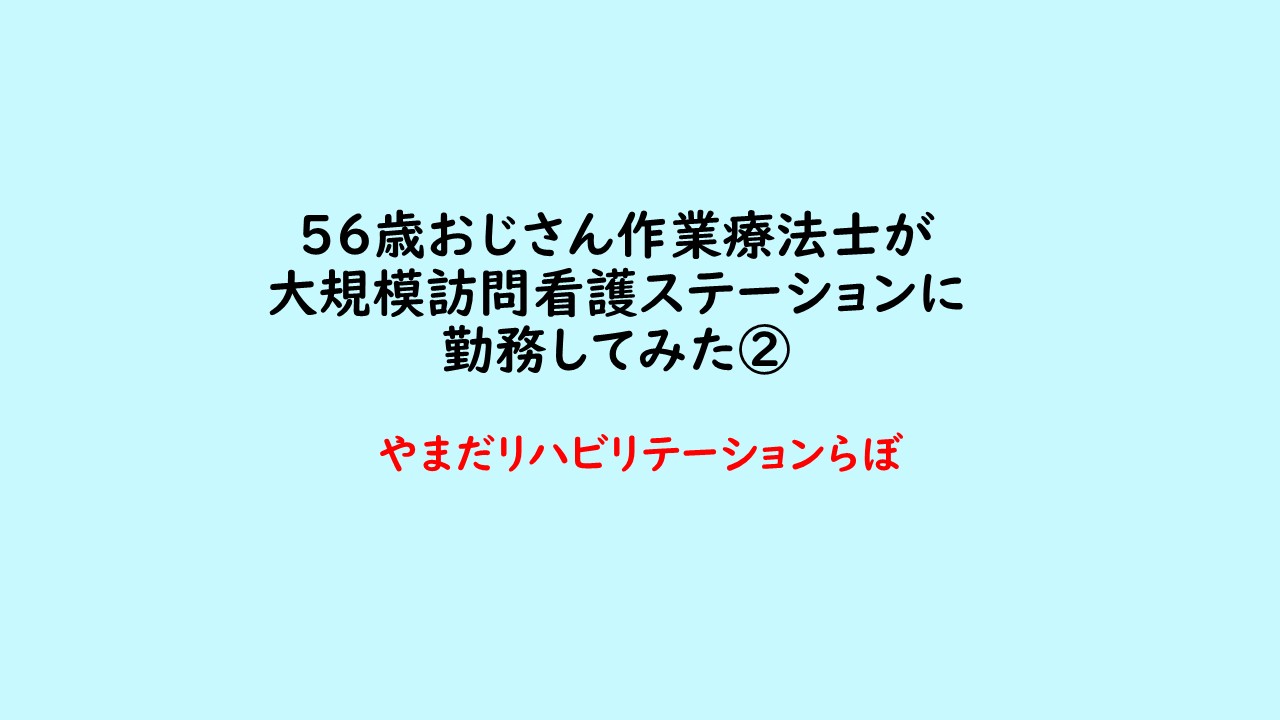


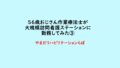
コメント