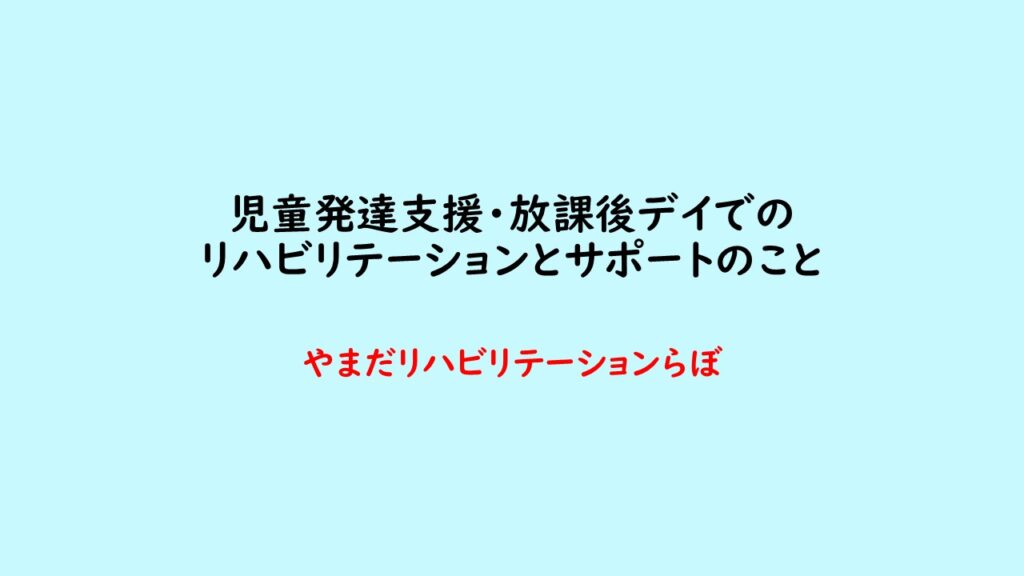
児童発達支援・放課後デイ・生活介護などの事業所で、医療的ケアの必要な子供さん達のデイに複数関わっています。看護師さんも複数配置されていて、呼吸器を装着されているような重度の子どもさんも在籍しています。リハの必要性もあるので、勤務しながらいろいろ支援しています。そうして、こういった事業所に転職されるセラピストさんも時々いますよね。
でもね、この領域ってやっぱりまだまだ理学療法士や作業療法士、言語聴覚士さんにとっては新しい領域というか、未開拓であまり知られていない。セラピストでも働いている人が少ないからね。私は10年以上前から関わっていますが、それでも、まだまだ未開拓だなと思っています。
この領域で大切なこと
この領域に転職してきた、セラピストさんが直面する大きな悩みというか課題は「リハビリテーション業務に専念することが難しい」ということです。
このことについて悩んでいるセラピストさんはたくさんいます。
◆1人職場の作業療法士が抱える悩みのこと&それへの回答
病院でのリハビリテーションは、リハビリをする時間も確保されているし、場所も確保されているし、道具もある。ものすごく環境が整った場面でリハビリテーションだけをすることが可能です。スケジュールの中でどの患者さんをどの時間にリハを実施するのか決まっているところがほとんどかな。
それに対して、児童発達支援や放課後デイでのスケジュールって結構たくさんあるんですよね。特に重度の子どもさん達が通う場ではホントいっぱい色々あるんですよね。
バイタル測定、医療的ケア、入浴、おやつや食事、レクなどの活動、そんな風なスケジュールがあって、その間にリハビリテーションの時間があります。
とうぜんながら、リハビリテーションをする業務以外にも、時間帯によっては、入浴にかかわったり、食事にかかわったりすることが必要な職場もあります。
私は時短勤務というか非常勤で時間も限定された関わりをしているので、リハだけをしていますが、同じ勤務先の常勤のセラピストさんはリハ業務以外にも入浴や排せつ食事などの介助にも関わっています。
リハビリテーションが優先して業務が遂行されるわけじゃないというのが、この領域で躓くというか従来の職場とのギャップを覚えるセラピストさんが多い一番の要因だと思っています。
セラピストがいる職場だからといって、リハが優先されないこともあるんですよ。
リハビリテーションに対しての認識
先日も経験の浅い作業療法士さんの指導に行ってきました。
◆リハスタッフの現場での指導について「セラピストのサポート・教育のこと」
そこでも伝えたことなんですが、リハビリテーションはマンツーマンで関わる時間だけがリハビリテーションじゃないんですよね。
その時に来所されている利用者さんのリハの助言もしたんですよね。
- 車いすから床に下りる
- 床座位からあ車椅子に乗る
- 床座位からつかまり立ちをする
こんな練習をしました。これまではこんな練習してなかったとのことなんですが、運動機能的には練習すればできそうだったので挑戦しました。
これを周りで見ていた、介護スタッフさんもちょっとびっくりされていました。「あんなこともできるんやね」みたいな感じかな。
これね、リハで練習を始めるわけですが、少しでも動作的に可能になれば、普段のケアとか以上の時にも取り組むことが出来るようになるわけですよね。これまではスタッフが全介助で車椅子から降りていたのが、一人で出来るようになる。それを繰り返し行えば、運動機能も維持できる。それってリハビリテーションですよね。
マンツーマンでの取り組みを周りに広げることも作業療法士や理学療法士の役割で、広い意味でのリハビリテーションなんですよね。
リハビリテーションに対して胃の枠組みというか捉え方を変えていく必要があるんじゃないかなと思います。
病院でのリハビリテーションと施設でのリハビリテーションではその枠組みとか進め方を変えていくことが必要。セラピストはそこに適応していくことが大切。
生活を見る事
こんなことも指導では伝えました。
生活を見ることが大切ですよってことを強調しました。
リハビリは大切だけど、作業療法士として考えるのは生活のこと。
つかまり立ちや伝い歩きの練習を提案した時にね、
手近にあった棚とかテーブルを使って歩こうとしたら、棚の上とかテーブルの上を若手作業療法士さんが片付け始めたんですよね。だから、
「片づけないでそのままにしておいて」と伝えて、
伝い歩きの練習を始めた。
ケースバイケースだけど、何でもかんでも環境を整えて練習することが大事なのではなくて、いろんな状況でも活動を遂行することも大切。
そんなことも伝えてきました。生活の場所ではいろんな環境があるわけですからね。
訪問看護、子供のデイ、高齢者のデイいろんなところでの勤務経験があり、働いているからこそ、生活でのリハビリテーションの在り方を日々いろいろ考えています。
そんなことも指導しました。
これからの領域
児童発達支援、放課後デイはまだまだセラピストにとっては未開拓な領域です。
だからこそ悩みを抱えながら働いているセラピストさんはたくさんいるし、管理者さんや経営者さんもリハビリテーションの進め方で悩んでいるのかもしれない。
だけど、そんな事業所であったもリハビリテーションは必要だと思うので、サポート事業所としていろいろお手伝いさせていただけたら嬉しいです。
臨床経験30年超、57歳の作業療法士が色々お伝えしますよ。
◆サポート事業の概要
◆サポートの事あれこれ

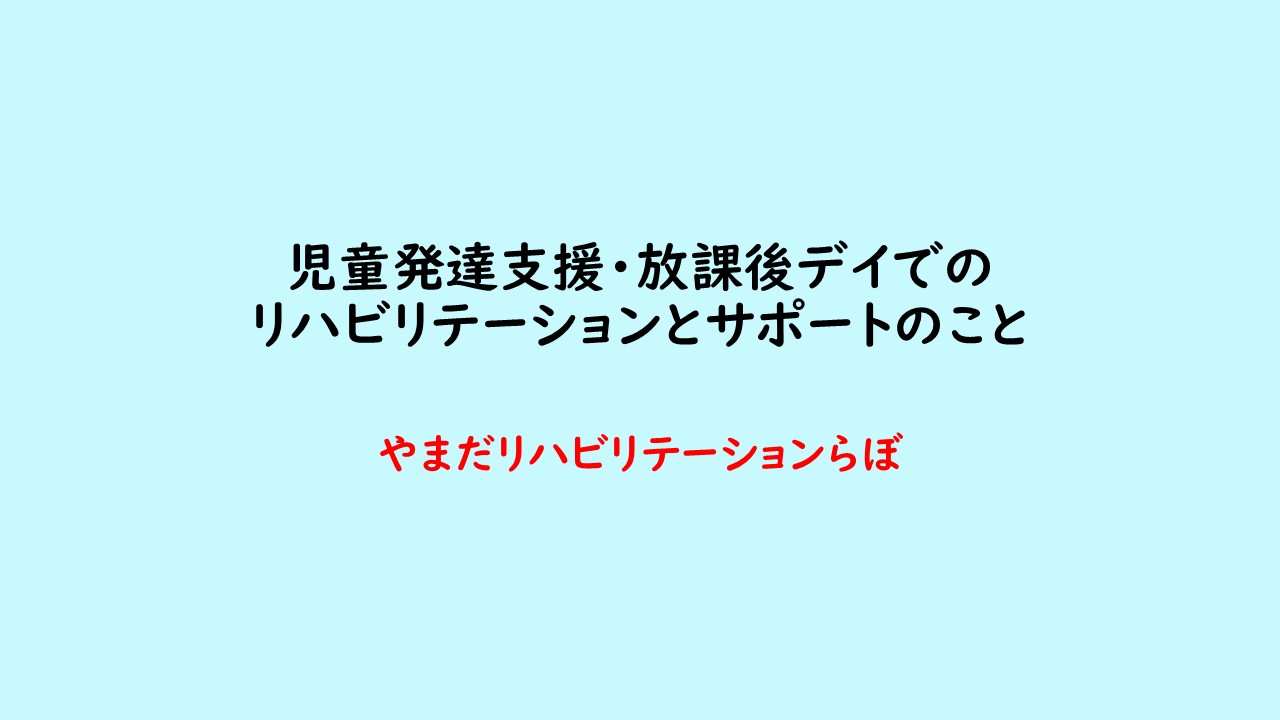


コメント